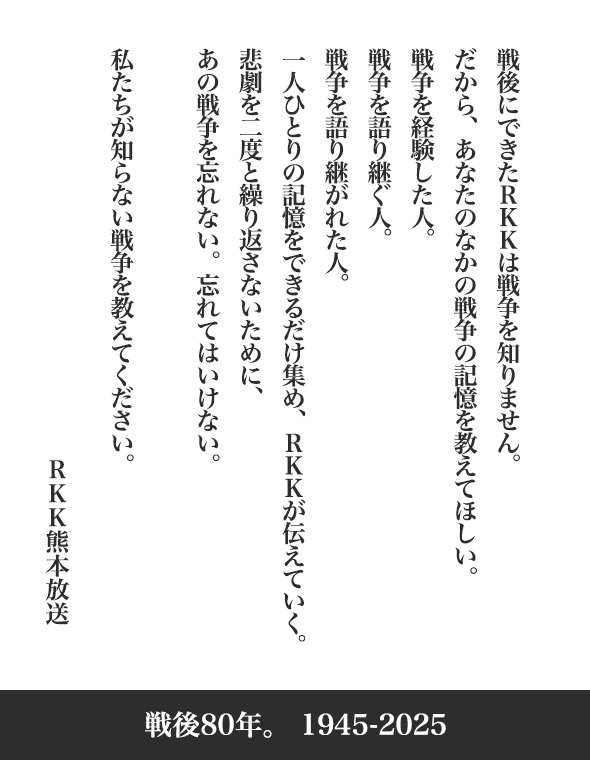
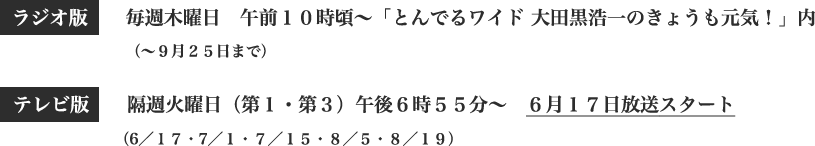

���،��₢�����������͂Ɋ�Â��ċL�ڂ��Ă��܂�

���h�s ���V���� (70��j
�F�{�s�E�k��@�������(70��)
���Ƃ��ł��鎄�����́A���80�N�Ƃ����ߖڂ̔N��...

�F�{�s�E������ ��������i40��j
1916�N���܂�̑c���̎�L�ł��B�y�ȉ��A�c���̎�...
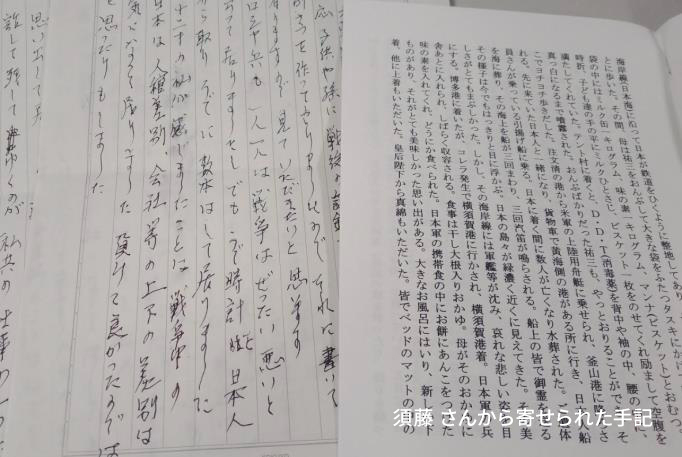
�F�{�s�������@�{������ (90��)
90��̎��́A�I����Ƒ��ƂƂ��Ɍ��݂̖k���N�A��...
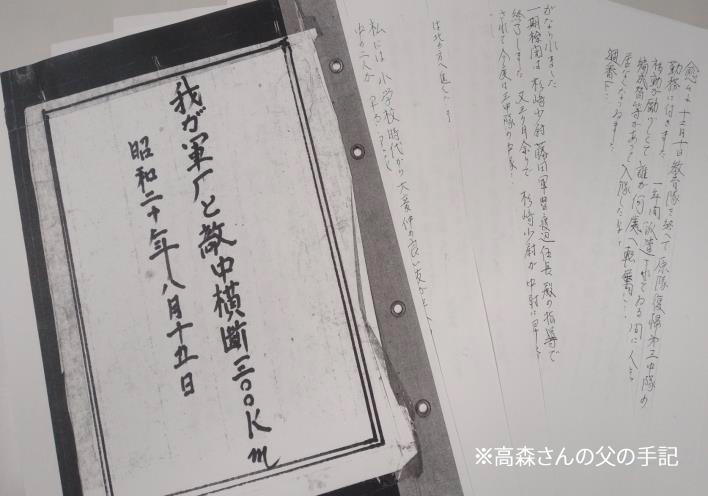
��v��S ���X����i70��j
1945�N8��7���A���͖��B���k���̊X�n�C�����ւ̈�...

�F�{�s ���V����i90��j
���̕��͑̂��������������߁A���͂��x���1944...

�v�钬 �q�{����i60��j
���A���̉Ƒ����o�������펞���̘b�����`����������...

�F�{�s ��������i90��j
1945�N�A�푈�̍Œ��A���{���D���ł���Ƃ����틵��...

���h�s ��{����i70��j
1918�N���܂�̎��̕��́A�����m�푈���A�C�R��...

�F�{�s ���c����i80��j
�I��̔N�A����9�Ŗk��B�ɏZ��ł��܂����B��...

���k�S ��������i80��j
1945�N�A����3�̍��̋L���ł��B�����A�����Z��ł����F�{�����k�S�ł��틵���������A���яd�Ȃ��P�Ɍ�������...

����s ���i����i98�j
���N�X�W�ɂȂ鎄�́A���܂�Ă��炸���Ƃ��̒n�ŕ�炵�Ă��܂����B18�������펞���̋L���Ƃ��đN���Ɏc���Ă���...

��v��S �j���i40��j
�c��������c���͐푈�̌���b���Ă��܂����B�c���͗��R�ʼnq���������Ă���A�K���͒��тł����B���B�ɂ����c���́A...

�e�r�S �c������i70��j
���̉Ƒ����o�������푈�Ɛ��̐����ɂ��āA�M�����点�Ă��������܂����B���̕��͓������ŏI����}���A�Ⴊ�}...

�F�{�s ���i����i70��j
����́A�F�{���P�����A�F�{��w�Y�w�l�ȂɈ�t�Ƃ��ċΖ����Ă������̐e���ɂ��L�^�ł��B����������Ɉꕔ������...

�F�{�s ��������(40��)
�c���͓V���o�g�ŁA��s�@�̐����m�����Ă��܂����B1945�N�̂�����A�����@�����A���͑��ڂ�����������A�L���s...

�F�{�s ��{����i102�j
1923�N���܂�̎����I����}����O�A1944�N��21�ŌF�{���疞�B�̈ƎR�i����j�ɏZ�ގo�v�w�̂��Ƃֈڂ�...

�F�{�s �j���i40��j
��N4���A���̑c�ꂪ100�ő��E���܂����B�c���20�ŌF�{�ɗ���܂ōL���ŕ�炵�Ă���A���O�͐푈�̋L������...

�e�r�S ���R����i40��j
�S���c�ꂩ�畷�����A�Y����Ȃ����i�ɂ��Ă��`�����܂��B1929�N���܂�̑c��́A1945�N8��9������16�ł�...
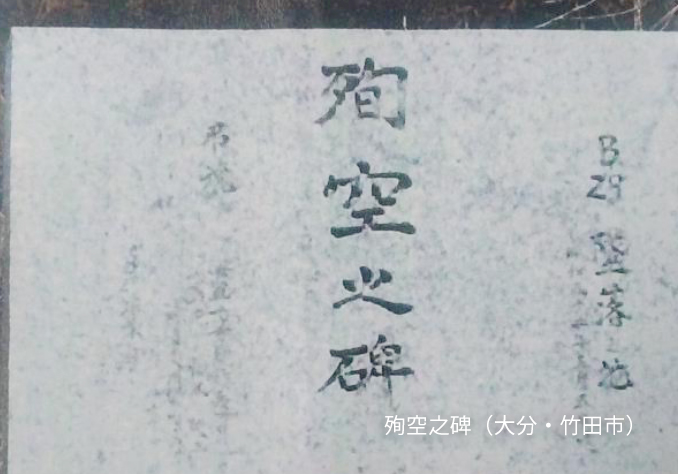
���h�s �◜����i90��j
�푈��̌������҂Ƃ��āA�ł��L���Ɏc���Ă���̂́A���h���ł̋�ł��B1945�N�A�A�����J�R�ɂ����{�{�y�U...

�F�{�s ���삳��i70��j
1922�N���܂�̕��̐펞���̌o����Ԃ�����L�ł��B���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B1945�N7��1��...

�F�{�s �`����i80��j
1910�N���܂�̎��̕����A1987�N���ɑ��푈�̌���������ۂ̘^���L�^���܂Ƃ߂����̂ł��B����1941�N9����...
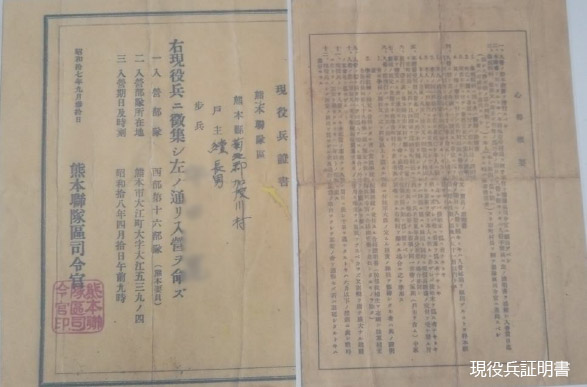
�F�{�s ���삳��(70��)
1922�N���܂�̕��̐펞���̌o����Ԃ�����L�ł��B���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B�����m�푈��...
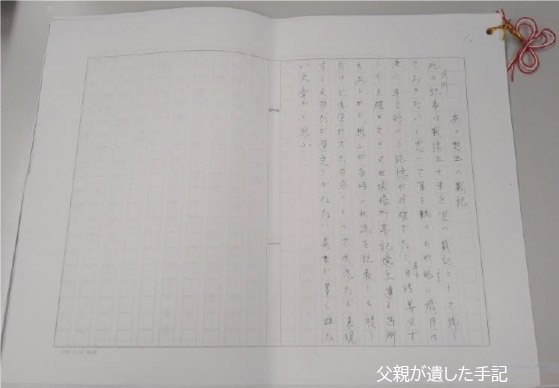
�F�{�s �|������i�U�O��j
���Ƃ���펞���̎ʐ^�Ȃǂƈꏏ�ɁA�r���}�ł̐킢�Ƃ݂����L��������܂����B���������x�[�X�Ɉꕔ��...
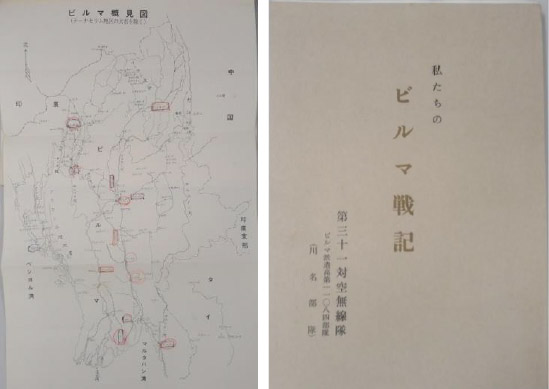
�F�{�s �b�コ��i�V�O��j
1916�N���܂�̕����������߂Ă�����L�ł��B�ȉ��A��L���甲���������e���L�ڂ��܂��B�������ɏ]���Ȃ���...

�F�{�s ����i�U�O��j
���N�X�R�ŖS���Ȃ�����́A�F�{�`(�F�{�s)�߂��Ő��܂�炿�A10�l�ȏ�̌Z�������܂����B �������w���̍�...

�F�{�s �R�{����i�U�O��j�V���s �Ό�����i�T�O��j
�V���s���{���ł́A�����ߌ�5���ɂȂ�ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ����̉����������Ă��܂��B���̉��́A�s�m�ΊC������...

�ʖ��S ���c����i�T�O��j
1931�N���܂�̎��̕ꂩ�畷�����b�ł��B�ꂪ���w�Z�ɒʂ��Ă������́A�����y�ɖh�Ђ����Ԃ�A�~�}�܂ƃ���...

�F�{�s �₳��i�X�O��j
1945�N�t�A����9�̎��̏o�����ł��B���̓��́A�ǂ��܂ł��L����悤�Ȕ�������ł����B�����A���͌F�{�s��...

�F�{�s �ɓ�����i�V�O��
���̗��e�́A�푈�Ƃ��������̎����t����ɉ߂����܂����B�P�X�P�Q�N���܂�̕��͐��O�A�܂ɐG��Đ푈�̑�...

�F�{�s �ɓ�����i�V�O��j
2020�N�ɖS���Ȃ���1919�N���܂�̕�́A�펞���A�����̐l�������ł������悤�ɁA���g���u�R�������v�ƌ����...

�����s �₳��i�U�O��j
�P�X�S�R�N�T���B���R���狌���q����(�����q���� �y�ь����{�����̑O�g)�ɑ��A�}�j��(�t�B���s��)�ɐ����H��...

�F�{�s ��������i�W�O��j
�I��܂ł̂P�X�S�S�N�`�P�X�S�T�N�ɂ����ẮA��������P�ɑ����܂����B�A�����J�R�̐퓬���͗ΐ�̏��Ⴍ��...

�F�{�s ��������v�ȁi�X�O��ƂW�O��j
�������v�w�͏I��̎��A�P�O�ƂX�B�Q�l���ɍ��̏�쒬(�F�{�s)�ɏZ��ł��܂����B�I��܂ł̂P�X�S�S�N�`�P...

�F�{�s �n�ӂ���i�V�O��j
���̉Ƒ��ʐ^�Ɏʂ�j�����A�P�X�S�Q�N�����A�����Y�C�R�q����i���j�ɏ������Ă����`���i�����Q�U�j�ł��B�`��...

�ʖ��s �X����i�W�O��j
1945�N�W���̋L���ł��B�R�Δ����������́A�V��(�F�{�s)�������F�V�H���ɏZ��ł��āA���̓��͂Q�K�łR�Ώ��...

�F�{�s �j��(20��)
����ɏZ�ޑc��(90) �͂P�O�̎��ɒ���s�Ŕ픚���܂����B�c��͖��N�A�������������ꂽ�W���X���̕��a�F�O��...

�F�{�s �R������i�U�O��j
�P�X�R�O�N���܂�̖S����ɂR�O�N�قǑO�ɕ������b�ł��B�펞���Ŏv���o�����Ƃ͂ƕ����Ɓu�Ƃɂ����Ђ����������B...

�F�{�s �R������i�U�O��j
�����P�T�̖S���ꂪ����Ă��ꂽ�A�P�X�S�T�N�W���P�O���̌F�{���P�̘b�ł��B���̓��A��ƗF�l�͂Q�l�Ŋw�Z...

�F�{�s �ēc����(60��)
�Q�O�P�U�N�A�F�{�n�k�Œz��P�R�O�N�̎���͑�K�͔���B�ǂȂǂɑ傫�Ȕ�Q���o�܂����B���̕Еt���̍ۂɌ���...

�F�{�s ���삳��(70��)
�������e���畷�����b�ł��B�P�X�Q�U�N���܂�̕��́A�P�W���납�璆���E���֍s���A�R�������H��...

�F�{�s ���{����(�X0��)
�P�X�R�Q�N���܂�̎��́A�P�Q�`�P�R�̎��ɋ�P���o�����܂����B�F�{�s�ւ̋�P�͂P�X�S�S�N�㔼����P�X...
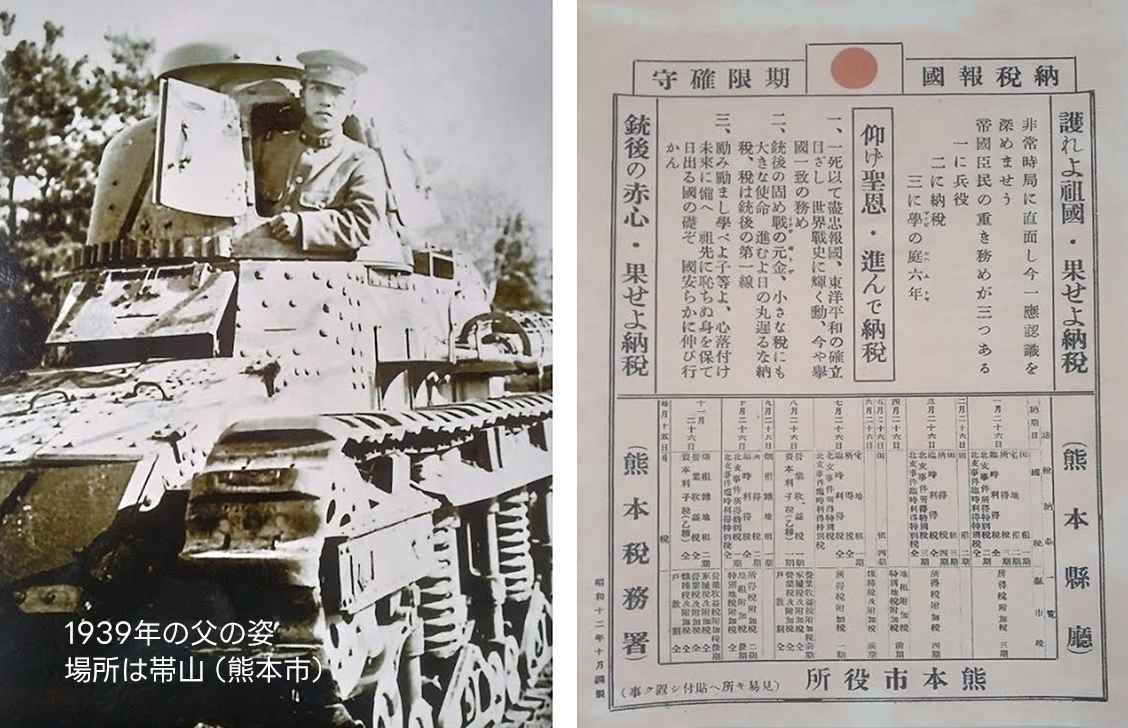
�F�{�s �b�コ��(80��)
�P�X�S�T�N�B�����Q�̍��̋L���ł��B��s�@�̉���������A�h�֓�����B������J��Ԃ��Ă��܂���..

�F��s �{�c����(90��)
���A���{�̑����̎�҂��������ꂽ�ٍ��̒n�ʼnߍ��ȉ^����w�����܂����B�������̈�l�ł��B��� ��...

�F�{�s �Ћ˂���(80��)
�P�X�S�T�N�̌F�{���P�������������A�قږ����A���W�I����uB�Q�X���@�A�i�����j���痈�Ă���v��...

���v��S �l�ۂ���(90��)
�����m�푈���͂��܂������A���͏��w���ł����B���͂P�X�S�R�N���납�玭�����ŌR���H����c��ł��܂�...

�F�{�s �O�c����(40��)
�����ɏo���������Ƃ�����c��(1919�N���܂�)�́A�c�����̎��̖����ŁA��퓖���̘b�����Ă����...

�F�{�s ���i����(80��)
���͎����Q�̎��A�o����̑�p�ŖS���Ȃ����B�P�X�S�T�N�P���X���̂��Ƃ������������B���ꂩ��W�O�N...

�F�{�s �X����(70��)
�S���Ȃ������́A1920�N���܂�ŁA���R��U�t�c�P�R�A���̏��тƂ��āA�t�B���s���̃l�O���X���ŏI��...
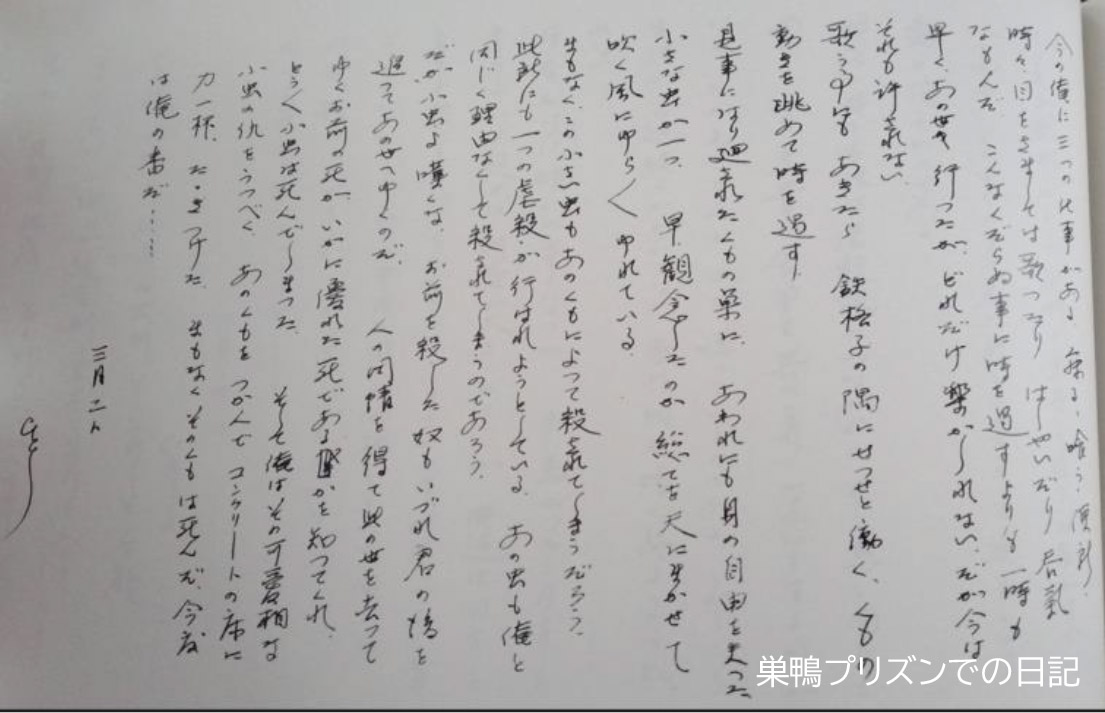
�F�{�s �X����(70��)
B����ƂƂ��āA�i��Y�̔��������Ă��ꂽ���̓��L�B�y�ȉ��A�����L�z���ꕔ�����قڌ����̂܂�...

�ʖ��s ���c����(40��)
1923�N���܂�̑c�ꂩ�畷�����b���ł��B���̑c��͑����m�푈���ɖ��F�̖k�A�\�A�Ƃ̍����t�߂̍���...

�F�{�s ����(80��)
�P�X�S�S�`�P�X�S�T�N�ɂ����ē������w�����������͋ʖ��s�ɏZ��ł��܂����B�����@�����P���鋰�ꂪ��...

�F�{�s ���{����(80��)
�P�X�S�T�N�V���P���̌F�{���P�B�F�{�s�̖{�����w�Z�̋߂��ɏZ��ł������́A�R�l�Z��̒��j�ŏ��w�R...

�F�{�s ���{����(80��)
�����o������O�ɁA�{��(�F�{�s)�̎���ŎB�e�����ʐ^�B��n�t�B���s�����畃�́A�S�N�Ԃɓn���Ď���...

�F�{�s �j��(40��)
�P�V�N�O�A�W�R�ŖS���Ȃ����c���̘b�ł��B���̎��ɓˑR�c�����푈�̘b�������̂́A�c�����W�Q�̎�...

�F�{�s �]������(70��)
�P�X�T�O�N���܂�̎��ɂ͐푈�̎��̌��͂���܂���B�����A�푈�̏��Ղ͑̌����Ă܂��B�������������w...

�F�{�s ����(80��)
�F�{���P�̂��̓��A���͂S�ɂȂ�������ł����B�F�{�s�̔���̓y��ɂ�������̐l����̕��ɑ�...

�F�{�s ����(80��)�`��
�����U�B���̌F�{�s������؈�Ōo��������P�B�h�ɓ����悤�Ƃ������A�u�h���̂��R���Ă���v...

�F�{�s �{�c����(80��)
���̐푈�̋L���ł��B�I��O�̎����S�̂���A(�P�X�S�T�N)�ԉ��R(�F�{�s)���z���ē�̕����甚���@...

�F�{�s ����(90��)
�P�X�S�T�N�V���P���̌F�{��P�ł́A�t�͊w�Z(�F�{�s)�̗��ɂ����B�u�q���[�b�v�Ƃ��������āA��...
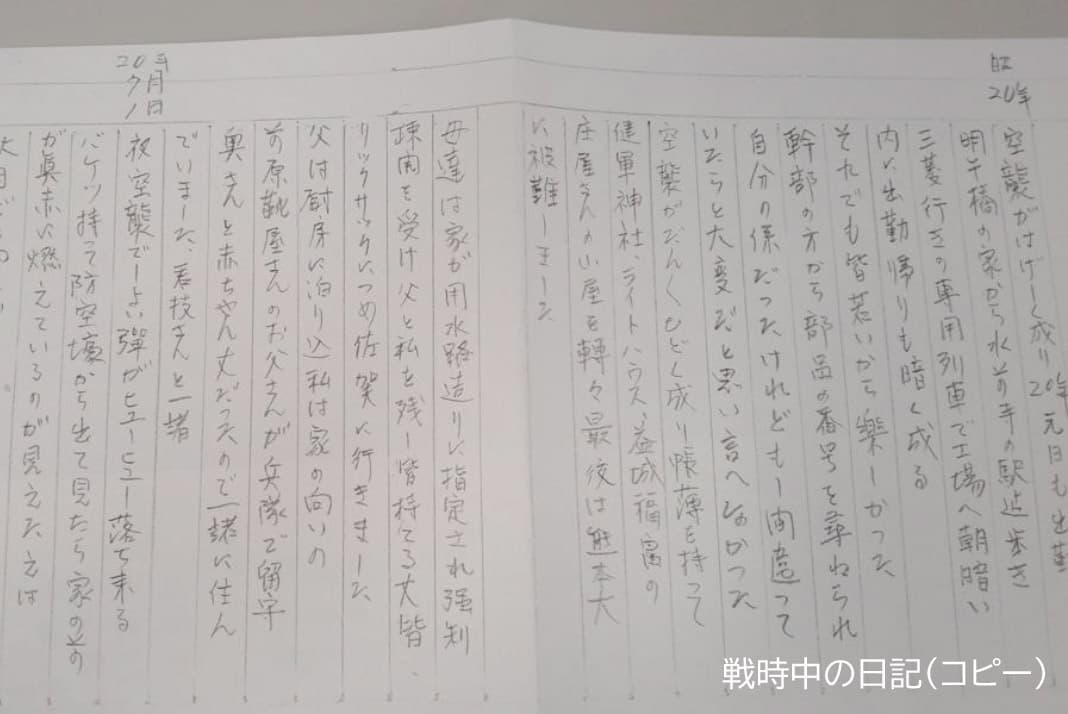
��v��S ����(70��)
��Q�N�O�ɂX�U�ŖS���Ȃ����ꂪ�A�F�{���P�̏��������߂Ă��܂����̂ŁA�����肵�܂��B�y�ȉ�...

�F�{�s �Ћ˂���(80��)
�P�X�S�T�N�̌F�{���P�������������A�قږ����A���W�I����uB�Q�X���@�A
�i�����j���痈�Ă���v�ƌx������������A
�����@���߂Â��Ɓu�E�[���A�E�[���v�Ƌ�P�x���Ă����B
�h�ɓ����Ă��A�O�ł́u�h�[���v�u�h�[���v�Ɖ����苿���Ă����B
��́A�Ƃ𖾂邭���Ă���Ɣ����@�ɑ_���邽�߁u�낤�������d�v�ƌ�����A
���d�����炢�̓��Ő��������Ă����B
����ł��A�Ɩ��e��������ƁA���͖͂��邭�Ȃ�A
�������w�����������͋��|�������Ă����B
�F�{���P�ł́A����Ď����A�߂��̔R���Ă��Ȃ��Ƃɂ͋@�e���ꂽ�Ղ������������B
�x���x���P�܂ł̎��Ԃ́A�����Ă��R�O���B
�K���ɖh�ɓ������B
���ł����Q��h���T�C�����̉�����Ɠ������v�������B

���v��S �l�ۂ���(90��)
�����m�푈���͂��܂������A���͏��w���ł����B
���͂P�X�S�R�N���납�玭�����ŌR���H����c��ł��܂������A�P�X�S�T�N�ɂȂ�A
�틵���������Ă����ƁA�u�A�����J����B�ɏ㗤���ė��邩�瓦���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƁA
�Ƒ��őa�J���邱�ƂɂȂ�܂����B
�a�J��́A��B�̒��S�Ƃ������ƂŌF�{�E�u�p���ɁB
�W���P�P���̖�A�ݕ���Ԃɏ�莭�����w����F�{�w�ցB
��Ԃɂ́A�w�k�������ꂽ���w���̎p������܂����B
�r���A�A�����J�R�̔�s�@�����P���邽�тɁA�u������v�Ƃ̊|�����ŁA��Ԃ��~�܂�
���̉��֓�������ł����̂��o���Ă��܂��B�{���ɋ��낵�������B
�����炪��F�{�w�ɒ����ƁA��������u�p���Ɍ������F���S���̎n���w
��F�{�w��ڎw���܂����B
�����A���̓��͌F�{���P�̒���ŁA�����͔R�������ꐅ�����j��A������
�|�^�|�^�Ɨ����鐅�����݂Ȃ���A�K���ɒ킽���̎�������ē�F�{�w�܂ŕ����܂����B
�u�p���ɂ����̂͂P�S���̖�B�����A�߂��̒×���ŁA�����܂݂�̊�Ƒ̂�܂����B
�����Č}�����I��B
�푈���I��������Ƃ�m���Ĉ�ԂɊ������̂́u���������Ȃ��Ă����B�B��Ȃ��Ă����v
�Ƃ������Ƃł����B

�F�{�s �j���i40��j
��N4���A���̑c�ꂪ100�ő��E���܂����B
�c���20�ŌF�{�ɗ���܂ōL���ŕ�炵�Ă��āA���O�͐푈�̋L������邱�Ƃ�����Ă��܂������A
����20���߂������A���C�Ȃ���b�̒��ŁA�펞���̑̌���b���Ă��ꂽ���Ƃ�����܂��B
���̘b�ɂ��ƁA�c��͐펞���A�L����ŏo�����镺�m�����̖�����쐬����d���ɏ]�����Ă��āA
���͂ɂ͑����̕��m���������������ł��B
1945�N8��6���A���̓��������������Ƃ𑱂��Ă����Ƃ���A
�ˑR����Ȍ��ɕ�܂�A���˓I�Ɋ��̉��ɐg���B�����Ƃ̂��Ƃł��B
�������������ꂽ�̂ł��B
�ӎ������߂������A����͖S���Ȃ������m�����̈�̂Ŗ��ߐs������Ă����Ƒc��͌���Ă��܂����B
�Ƒ��Ƃ̍����n�_���������ߐ��n��K�v������܂������A���͉��Ă��āA
�j���œn�邵������܂���ł����B
����܂ʼnj�����Ƃ��ł��Ȃ������c��ł����A�K���̎v���łȂ�Ƃ����n�肫���������ł��B
�������A����j���ł���Œ��ɗ���Ă�����ɂԂ���A�G�����䂵���ƕ����Ă��܂��B
�K���ɂ��A�픚�ɂ��g�̂ւ̒��ړI�Ȕ�Q�͂��̕G�̉��䂾���ōς����ł��B
���̌�A�����ɉƑ��ƍĉ�ł����c��́A�e�ʂł������c���̉Ƃɐg���A
��ɑc���ƌ������A���̕������܂�܂����B
�픚�O���ł��鎄���A���ƌZ��Ƌ��ɍK���ȓ��X�𑗂��Ă��܂��B

�F�{�s ���i����i70��j
����́A�F�{���P�����A�F�{��w�Y�w�l�ȂɈ�t�Ƃ��ċΖ����Ă������̐e���ɂ��L�^�ł��B
����������Ɉꕔ���������Ă��܂��B
�P�X�S�T�N6��30���[��i7��1���j�A���ɌF�{�ɂ��G�@���P�����܂����B
���̓����́A��ǂƎ���������邽�ߓ����ɏA���Ă��܂����B
�a���ł͑��̈�Lj��Ɛ����̊Ō�t���a�@�Ɗ��҂�����Ă��܂����B
���������x�ɂ킽��G�@�̔g��U���́A�h����h���S�����ɗ������A
�������͂��������̖�����邾���Ő���t�ł����B
��b�������a�@���S�Ă��A�킸���Ɍ������ƕa�@�̓S�ؕ����������c���āA
���̂����ɂ��ׂĂ��D���Ɖ����܂����B
�����c�������҂ƕa�@�̐E���́A�Ȃ�Ƃ�����̒�h��͌��ɔ��A
�����Ђ�����閾����҂��܂����B
��ʂ��삯���Ă��ꂽ�搶�́A�Y�w�l�Ȃ̑S���@���҂ƐE���̈�c�������A������A
�����̒��A��Ӓ����҂���蔲�������Ƃ����܂��A�S����̊��ӂ̌��t���q�ׂ��܂����B
���̒��ɂ́A�O���ɊO�ȂŎ�p�������Ō�t�����܂����B
�ޏ��͈�l�Ŕ��A�a�@���ւ̐��@�̒r�ɐZ����A
�������������Ȃ����ʂ�������҂��A������܂����B
�����Ƌ����̊F�́A���̂��Ƃ�m��A�����Ɗ�тɕ�܂�܂����B

�F�{�s ��{����i102�j
1923�N���܂�̎����I����}����O�A1944�N��21�ŌF�{����
���B�̈ƎR�i����j�ɏZ�ގo�v�w�̂��Ƃֈڂ�Z���̂��Ƃ����b�����܂��B
�ƎR�͓S�|���Y������ŁA���|������������܂����B
���̂��߁A�A�����J�R�̍U���ڕW�ƂȂ��Ă����悤�ŁA�����ƎR�œ����n�߂������A
�����̒��ŋ�P�x�苿���܂����B
20�`30�l�̓����͌��������яo���đ���o���A���������ł��̌��ǂ��܂����B
�ǂ��Ɍ��������̂��͎v���o���܂���B
��P�͌������A�F�{�Ōo�������ĈΒe�ł͂Ȃ��A���e����������A
���a��10���[�g���A�[����2���[�g���̊זv�����������ł��Ă��܂����B
���̂悤�ȏ��ł��A�����̓��{���{�͖��B�ł̎d�������サ�Ă��āA
�������{�y�̖�4�{���������߁A10�㔼�̒j�����������ڂ�Z��ł��܂����B
�ƎR�̊X�́u���̒��v�Ƃ��Ă�A�����̓��{�l�Ŋ��C�ɖ����Ă��܂����B
�������A�����m�푈�̐틵����������ƁA�����ɗ��Ă���10��̒j��������
��n�ւƏ��W����Ă����܂����B
���ł��o���Ă���̂́A�o�����Ă����j�������̕\��ł��B
����20��̎��ɂ͂܂����ǂ��Ȃ����c��u�j�̎q�v�Ƃ����������ŁA
�s�������ȋC�������\��Ă���悤�Ɋ����܂����B
�ނ�͓��{�{�y���痈�Ă��邽�ߐg��肪�Ȃ��A�e��Z��ɏo������p�������邱�ƂȂ�
��n�������̂ł��B
���́A�A���A�ƎR�w����o�����Ă����j�̎q�����������葱���܂����B
�ނ炪���̌�ǂ��Ȃ����̂��͕�����܂���B

�I���͉ߍ��ȓ��X���҂��Ă��܂����B
�����͓ˑR�Ȃ��Ȃ�A�����Ă������߂Ɏ����Ă����ߗނȂǂ��ĐH���Ȃ��܂����B
�X�̕��͋C���ς��ʂāA�ƎR�̊X�ɂ͋��\�A�R�������Ă��܂����B
���̍����珗���͋��\�A���ɏP���Ȃ��悤�A�����ۊ���ɂ��Ă��܂����B
�����{�y�ɋA�肽���B���̎v�����������̂́A�I�킩��1�N��̂��Ƃł����B
���͎q�ǂ�������������ԂŁA�v�Ɠ�l�A�����g���D�i�A���D�j�ɏ�荞�݂܂����B
�������A���̑D�͋q�Ȃ�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�S�����b�ɂ����Ԃł����B
8���Ƃ������Ƃ�����A���˓����𗁂ё����A�D�̏�Ŗ��������l�����܂����B
�����Ȏq�ǂ����������e���S���Ȃ������A���������炸����������q�ǂ������̎p�ɋ���ɂ߂܂����B
�܂��A�D�ŖS���Ȃ����l�����̈�̂��C�ɗ��Ƃ��Ă����́A�����]���ɏĂ��t���Ă��܂��B

��v��S �j��(40��)
�c��������c�����푈�̌���b���Ă��܂����B
�c���͗��R�ʼnq���������Ă���A�K���͒��тł����B
���B�ɂ����c���́A�I��ԍۂ̂P�X�S�T�N�B
���\�A�Q��ɂ�茈���̓��S���o�����܂����B
���Ԃ��e�Ō�����A���\�A�R�̒nj������킵�Ȃ���
�u�����̐S���̉������Œ��ڕ�������v�قǂ̋��|�𖡂���������ł��B
�y��ɉB��A�u�����ɗ�����h���Ⴆ�Ă�����Ă��v�ƃi�C�t�R�������肵��
�o������߂��u�Ԃɋ��\�A���̏W�c�������グ���Ƃ����b�́A
�c���̑̌��̒��ł����Ɉ�ۓI�ł����B
���̌�A�c���͒����ꂪ���\�������̂ŁA���O��ς������l�ɂȂ肷�܂��A
���{�������D�̏���҂������A�����ɋA�蒅���܂�1�N���̍Ό���v���܂����B
���A���܂������喴�c�������Ă��쌴�ƂȂ�A�����̒��Ԃ�������ӗ~���������A
�c���́u���͂����S�Ă��������A������x�A�������琶���Ȃ������v��
�O�r�Y�z�œ����n�߂܂����B
���������̂Ɋ������܂�A�ӔN�͔]�[�ǂ̌��ǂɋꂵ�݂Ȃ����
�u�푈�͓�x�Ƃ�����Ⴂ����v�ƌ��Ȃ̂悤�Ɍ���Ă��܂����B

�F�{�s ��������(40��)
�c���͓V���o�g�ŁA��s�@�̐����m�����Ă��܂����B
1945�N�̂�����A�����@�����A�c���͑��ڂ�����������A
�L���s���̍����a�@�ɓ��@���邱�ƂɂȂ�܂����B
�����A�a�@�ł͊F��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł����A
�c���͂�����Ȃ����Ă��܂��������ł��B
�Q�ĂĒT���ƁA��̓x�b�h�̉��ɗ����Ă��܂����B
�c�����x�b�h���~��ė���E�����Ɣ������������̎��A
��ɂ�B29�����Ă���̂������܂����B
B29�͉����������̂𗎂Ƃ��A���̏u�ԁA������͐^���ÂɂȂ�܂����B
�c���̑̂̏�ɂ̓x�b�h�⊢�I���̂��������Ă��܂������A
�Ȃ�Ƃ������o���ƁA���͂͊��I�̎R�Ɖ����Ă����Ƃ����܂��B
�߂��ɂ́A�ʎ��̂���Ō�t���|��Ă��܂����B
�ޏ��͔̑̂����قǖ��܂�A�����ł��Ă��܂����B
�c�����ޏ��������グ��ƁA�͔̂������炢�Ȃ��Ȃ��Ă��������ł��B
�c��������グ�ĒN�����Ȃ����T���ƁA
��l�̐����������A���I�̉��ɂ͌��܂݂�̐l�����܂����B
���̐l����������A����ɐl��T���ĕ��������܂������A
�����Ă����l�͖S���Ȃ��Ă����悤�ł��B
�A�������Ă��܂炸�A�������߂ĕ����Ă���ƁA�J���~���Ă��āA
�����Ă����e��ɉJ���߂܂������A
����͍������������̂ň��ނ��Ƃ��ł��܂���ł����B
����ɌE�݂ɂ͍����������܂�A
���h��̐l�X�����������Ă��̍������ɌQ����A
���̂܂ܑ��₦�Ă����܂����B
�c���͔픚�҂ƂȂ�A���̒���������ɕς��A
�����Ȃ��Ȃ������߁A���̎�p��3��s���܂����B
���̂悤�ȑc���ł������A96�܂Ő����A
�������ɐ푈�̔ߎS����`���Ă���܂����B

�e�r�S �c������i70��j
���̉Ƒ����o�������푈�Ɛ��̐����ɂ��āA�M�����点�Ă��������܂����B
���̕��͓������ŏI����}���A�Ⴊ�}���}�����A�ɜ늳���A
�����̋������܂���Ă��������ł��B
�㊯�͕������̂ĂċA�낤�Ƃ����悤�ł����A�����ɂ��������n��o�g�̕��m��
�u�����̐ӔC�ŘA��ċA��v�ƕ���w�����Č̋��A���Ă��Ă��������܂����B
���͌̋��ɖ߂�������a�C�������A�×{���Ɍ������܂����B
���̂��ߕ�́A�������܂ꂽ�������w�����ĕ������������߂ɕa�@�ɒʂ��l�߂܂����B
�������@����Â��ؑ��̕a�@�̔��Â������L���ŁA
���L�̌���ڂɋ����ĕa���ɓ������L��������܂��B
�x�b�h�̏ォ��A�������Ⴍ�鎄�����Ȃ��猩�Ă��܂����B
���ꂪ�A���Ƃ̗B��̎v���o�ł��B
����ȕ�������1�Δ��̍��ɑ��E���܂����B
���̂��߁A���̊�͈�e�ł����m��܂���B
����A��͐��A�a�C�×{���̕��ƌ����������ƂŁA��J�������܂����B
�y�n����ĎR���J���A�Ă����_�ƂŖ����Ă���A�\���������肵�܂����B
�܂��A���ق��ɏo�āA�j���Ɠ����悤�ɓy�؍�ƂŌ������҂��܂����B
�n�����܈ꖇ�ŗ͎d���𑱂������߁A���̒܂͕ό`���Ă��܂����B
��́A���̏o������v�܂œ����l�߁A�����Ŏ�����ĂĂ���܂����B
�������e�q�͒��ڂ̐푈��Q�҂ł͂Ȃ���������܂��A
�������푈���Ȃ������Ȃ�A�������������ł������Ȃ�A
��͂����ƕ��ʂ̍K���Ȑl������߂��̂�������Ȃ��Ǝv�����Ƃ�����܂��B

���k�S ��������i80��j
1945�N�A����3�̍��̋L���ł��B
�����A�����Z��ł����F�{�����k�S�ł��틵���������A���яd�Ȃ��P�Ɍ������܂����B
��P�x�邽�тɁA��Ɏ��������A�����200���[�g���قǗ��ꂽ�h��
���Ă������Ƃ��o���Ă��܂��B
���̒��ł��A���ɑN���ɋL���Ɏc���Ă����P������܂��B
����́A����炨�悻1�L���̏ꏊ�ɂ������g���l����_�����Ǝv����@�e�|�˂ł��B
���������h�ɓ�������A���ɂ��������܂����e�����B�u�o�b�o�b�o�b�o�b�o�b�o�b�c�v�ƁA
�A�����Đ퓬�@����e�����˂���鉹���A�܂��Ɏ�����������ꏊ�̏�畷�����Ă��܂����B
�A�����J�R�̐퓬�@�́A�g���l���ɔ��Ă���l�X�����邱�Ƃ�m���Ă������̂悤�ɁA
���x���U�����J��Ԃ��Ă��܂����B
���̎��̏e���̐Ղ́A80�N�o���������c���Ă��܂��B
�����āA���̎��̔����́A���̎����猈���ė���邱�Ƃ͂���܂���B

����s ���i����i98�j
���N98�ɂȂ鎄�́A���܂�Ă��炸���Ƃ��̒n�ŕ�炵�Ă��܂����B
18�������펞���̋L���Ƃ��đN���Ɏc���Ă���̂́A�G�@�̏P���ł��B
�u�O�H�[�v�Ƃ������𗧂Ăď���ʉ߂��邽�тɋ����Ă��܂����B
����ŁA�n���̂��N��肪�u�ƒ|�Łi�G�@���j���Ƃ��A�˂����Ƃ��v�Ƌ���ł������Ƃ��o���Ă��܂��B
���̂悤�Ȑ푈��̌��������ŁA���ł����������Ă���v��������܂��B
����́A���̂��傤�����̂قƂ�ǂ������ŁA��n�ɍs���҂��N�����Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
�����̎��́A���̏�S����u�p���������v�Ǝv���Ă��܂����B
�n��̒j�����������X�Ɛ�n�֍s�����A���i�Ƃ���͒N���s���Ȃ��B
�u�������̂����ɗ��ĂĂ��Ȃ��v�Ƃ����v������������A�������C���˂�����X�ł����B
���̎v���́A80�N�����������c�葱���Ă��܂��B
�푈�̂��Ƃ��v���o�����тɁu�����A�����v�ƂԂ₢�Ă��܂��܂��B
�푈�̋L����N���ɕۂ������Ă��邱�ƂɁA
���i����͍Ō�Ɂu�ǂꂾ���̋�J���������v�Ɛ[�����t�����݂��߂܂����B

���h�s ��{����i70��j
1918�N���܂�̎��̕��́A�����m�푈���A
�C�R���Ƃ��ē��{�̊e�n�ɂ���C�R��n�ɋΖ����Ă��܂����B
���A���͏��w�����������ɁA�[�H�̂��тɓ����̘b���悭���Ă���܂����B
���͐����m�ł���A�����p�C���b�g�ł����������߁A�퓬�@�̎��^�]�Ƃ��āA
��錧�̉����Y���玭�������̎����܂ŁA���x����s�e�X�g���s���Ă��������ł��B
���̍ہA������̒ė��ɔ����A�����m�̊C�ʂ��ꂷ����s���Ă����ƕ����܂����B
���̂悤�ɁA�����������Ő��������퓬�@�́A���ɂ͓��U���̋@�̂Ƃ��Ă��g���܂����B
�ʏ�A���U���̋@�̂ɂ͕Г����̔R������������Ă��܂���ł������A
���́u�ł���ΐ����ċA���Ă��Ăق����v�Ƃ����v������A
�㊯�̖ڂ𓐂�ʼn������̔R�������Ă��������ł��B
�������A���ۂɊ�n�ɖ߂��Ă��邱�Ƃ��ł������������l�����̂��͕�����܂���B
���X�ƎႢ���N�����������𗎂Ƃ����߂ɗ������Ă����p���������钆�ŁA
���͐��Ǝ�������d�̎���ł��������Ƃ�Ɋ����Ă����悤�ł��B
����ȕ���69�ŖS���Ȃ������ɂ́A
�������N���Ő����������l�������A�䂪�Ƃ�K��Ď�����킹�Ă���܂����B
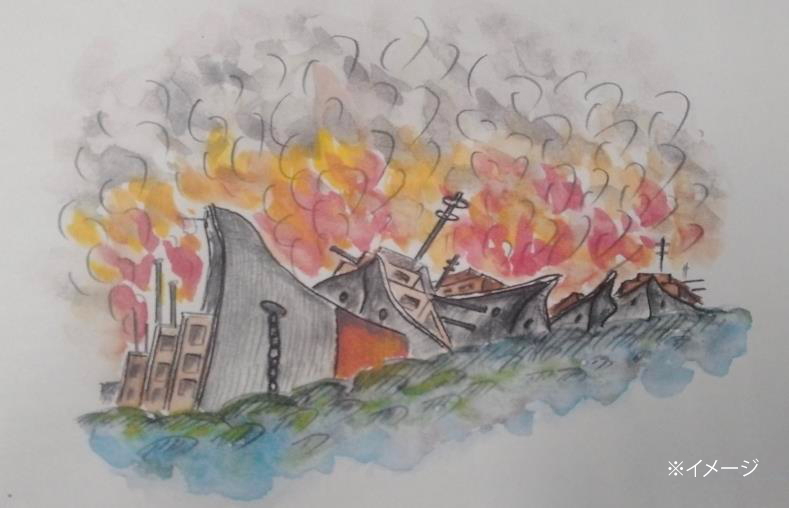
�l�g�s ���{����i50��j
1944�N�A�틵�͈����̈�r�����ǂ�A�H�Ǝ�����ɂ߂Č������Ȃ�܂����B
�c������n�Ō��ɂł����̂́A1���ɔu��t�قǂ̕Ă��������������ł��B
���̂킸���ȕ�2�A3���Ƃ�����̗t�Ŋ������A���ꂪ��H���������ƕ����Ă��܂��B
������A�c���͗A���D�u��a�v�ɏ�D���邱�ƂɂȂ�܂����B
�s����͒m�炳��Ȃ����������ł��B
�[�������ɌX���n�߁A���₩�ȊC��i�ޗA���D�̍b�Œ��Ԃƌ����Ă������̎��A
�u�h�[���v�Ƃ��������������n��܂����B
�ČR����̋����U���ł����B
�D�͈�u�ɂ��ďc���Ɉ�����A�u���Ԃɒ��ݎn�߂܂����B
�c���͊C�ɓ����o����A���������܂����B
�C�ɂ͏d��������o���A���̊댯�����������߁A�K���ʼnj���ł��̏�𗣂ꂽ�����ł��B
�~�������܂ł�5���ԁA�c���͂����Ђ�����j�������܂����B
���̌�3�����ԁA�c���͎��Â̂��ߖ��a�@�ɓ��@���܂����B
�����ė��N8���A�V�c�É��̋ʉ������ɂ��A�����ꂵ���푈�͂��ɏI���܂����B
�������A�I�킩��1�����A2�������߂��Ă��A�c�����Ƃɖ߂邱�Ƃ͂Ȃ��A
�펀�̒ʒm���͂��܂���ł����B
�c��͖����s���ł��܂�Ȃ������ƕ����Ă��܂��B
����ł��c��́A�c�����K���A���Ă���ƐM���đ҂������܂����B
�����ďI��̗��N�A1946�N5���A���O�ł����B
�R���p�Ńo�b�O���������j�������ւɗ����Ă��܂����B
�u����[�v�ƁA�c��͒����������������邩�̂悤�ɖڂ��ۂ����܂����B
�����ɗ����Ă����̂́A�c���ł����B
�c��ɂƂ��āA���̎����l���ň�ԍK���ȏu�Ԃ������ɈႢ����܂���B
�c���͂ɂ��₩�ɔ��݂Ȃ���u���C�ɋA���Ă��܂�����v�ƍ����������ł��B

�F�{�s ���c���� (80��)
�I��̔N�A���͂X�Ŗk��B�ɏZ��ł��܂����B
���S�������������߂��A�k��B�͕p�ɂɋ�P�ɏP���A
������킸��P�x�苿�����тɁA
��Ǝ���߂��̎R�Ɍ@��ꂽ�g���l���̂悤�Ȗh�֓�������ł��܂����B
�h�̒��͂��������Ă��āA���S�l���̐l�������g�������A
�G�@������̂�҂��X�ł����B
���̂悤�ȋ�P������Ɖ����Ă������ł��A1945�N6��29���̋�P��
���ɑN���ɋL���Ɏc���Ă��܂��B
�ߑO0��15���������1���ԁA
�������肪�����Ȃ��Ȃ�قǂ�B29�����X�Ɣg��I�ɏP�����܂����B
�h���璬��ՂނƁA�������[�Ă��������邭�R���オ���Ă����̂��o���Ă��܂��B
�����A��P�̔�Q������������ƁA
���e�����Ƃ��ꂽ�Ǝv����傫�Ȃ��蔫��̌����n�ʂɂł��Ă���A
���̋߂��̌����̉����ɂ́A�Ԃ���������Ԃ�����Ԃ̏������S���Ȃ��Ă��܂����B
���炭�A���e�Ő�������ꂽ�̂��Ǝv���܂��B
�܂��A���{�R�̍U�����ė�����B29�̋@�̂ɂ́A
�A�����J�R�̕��m���̂��o���o���ɂȂ�����ԂŌ�����A
���̓��Ђ���{�R�̕��m���W�߂Ă�����i���ڂɂ��܂����B
�����������Ă����ꏊ�ɁA�˔@�Ƃ��Č��ꂽ�����̈�́B
���̑s��Ȑ푈�̋L���́A���̔]�����猈���ď������邱�Ƃ͂���܂���B

�F�{�s ��������i90��j
1945�N�A�푈�̍Œ��A���{���D���ł���Ƃ����틵��M���đς��E�ԍ����̏����A
�G�@���I�X�Ɣ�ь����A�e�n�̓s�s�ւ̋�P���n�܂�܂����B
�G���̒��i���F�F�{�s����쒬�j�ɂ͌R�̔�s�ꂪ����A
���̉Ƃ͌R�̖��߂ɂ����U���̏h�����ƂȂ��Ă��܂����B
���N�������͓��X���邭�A�K�����������m�Ԃ�������Ă��܂������A
�ނ炪�A��̔R����ς�ł��Ȃ���s�@�ɏ���Ă��������ɁA
�Ƒ��͉A�ŗ܂𗬂��Ă��܂����B
���鏭�N���́A���U���Ƃ��ďo������ہA���e�̎ʐ^�����̃|�P�b�g�ɂ��܂��A
�������̉Ƃ̏�𗃂����E�ɌX���Ĕ��ł����܂����B
�u���U���ȂA�Ȃ��u�肷��̂��낤�v�ƐS�̒��ł͎v���܂������A
���̂悤�Ȃ܂Ƃ��ȍl�����͋�����ʂ܂܁A�傫�Ȏ���̗���̒��ɐ����Ă��鎞��ł����B
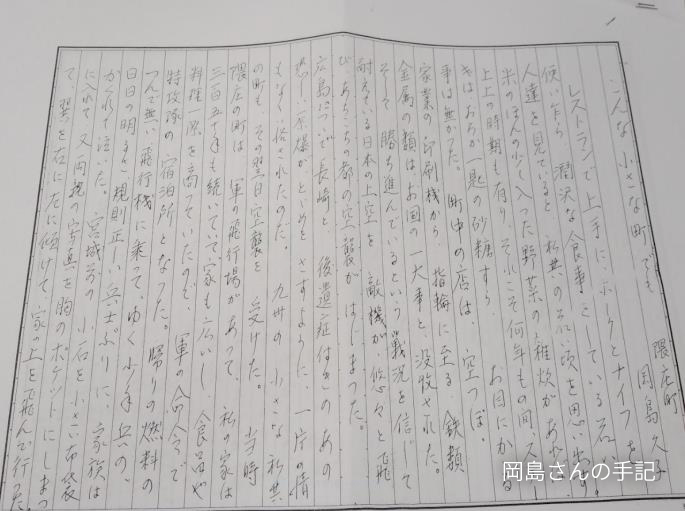
����A��P�͌������𑝂��Ă����܂����B
�s�C���Ȑ퓬�@�̉�������ƁA���x�����e�̉��������n��܂����B
�����Ŋw�Z�̌��֑O�̖h�ɋ삯���ނƁA���Α�����搶�������Ă��āA
�u�o�傹��Ƃ�������B���������܂����v�Ƃ������Ⴂ�܂����B
���́u�͂��v�Ɠ����A�u�Q�O�܂ł͐������Ȃ��B���U���̏��N���Ɠ������v��
���̎��v�������Ƃ��o���Ă��܂��B
���̌�̂��Ƃ͒肩�ł͂���܂��A
�R���������Z�ɂ���ɁA�ƂA�鎞�ɂ͂ւȂւȂɂȂ��Ă��܂����B
���̍Œ��A���������h�m�ɗ��e��������Ȃ���ʂ肩����A
�u�R���Ă��܂����v�ƂԂ₢�Ă��܂����B
�܂��A��̔��ʂ����Ȃ��قǏĂ���4�A5�l���D�l�`�̂悤�ɂ������܂��Ă��܂����B
�����āA���̉Ƃ��Ă������A��{�̑傫�Ȗ����������Ă��܂����B
���̎��A�f�����Ƃ̂������ꏊ�ɗ��āA�u�����Ƃ����v�ƌ����܂����B
���̎����́A�u�������A�ǂ���������x����푈�ł݂�Ȏ��ʁv�Ǝv�������Ƃ�Y��邱�Ƃ͂���܂���B

�F�{�s ���V���� (90��)
���̕��͑̂��������������߁A���͂��x���1944�N6���ɐ푈�ɏ��W����܂����B
��������10�ŁA�Ƃɂ�14�̒��Z���琶��6�����̓����ݎq�܂�7�l�̎q�ǂ��ƕꂪ�c����܂����B
�䂪�Ƃ͊������H�����ɂ��������߁A���m��������n���������߂ɌF�{�w�܂ōs�i����
�u�U�b�U�b�v�Ƃ������������x�������Ă��܂����B
�������W����Ė�2������̂��Ƃł��B���K���X�ɐ������������ʼnƑ����ڂ��o�܂��ƁA
�ꂪ�����J�����Ƃ���Ɏ��ɕ�܂ꂽ������A�u���s�����v�ƕ�������������������܂����B
�����������́A���̒��w�����A�����ČF�{�w�������܂����B
���̋@�]�̂������ŁA��͌F�{�w�ŕ��ɉ���Ƃ��ł��A�b�����Č����邱�Ƃ��ł��܂����B
���̌�A�c���ꂽ�Ƒ��ł����q8�l�Ƒc��́A
��1945�N7���̌F�{���P�܂ŁA��P�̓x�ɖh�ɔ��Ȃ��琶�����Ă��܂����B
���P�̍ۂɂ́A�����ɉ̊C�����Ȃ���Z��Ŕ��Ε����֑����ē��������Ƃ��o���Ă��܂��B
�䂪�Ƃ͊��S�ɏĎ����A�������Ԑe�ʂ̉Ƃɑa�J���܂����B
�I��サ�炭���ĉƑ��ŌF�{�ɖ߂��Ă���́A�������镺�m�̖��O��ǂݏグ��
���W�I�������Ȃ���A���̋A���҂��Ă��܂����B
�������A���N��ɕ����S���Ȃ����Ƃ����m�点���͂��܂����B
�⍜���i�͂Ȃ��A���������̂͏I��O�ɕa�œ|��A
�I�풼���1945�N9���ɕa�����Ă����Ƃ������Ƃ����ł����B
���ƕ�́A���̌F�{�w�ł̌����肪�Ō�̕ʂ�ɂȂ�Ƃ݂͌��Ɏv���Ă��Ȃ������Ǝv���܂��B
�I���1945�N8����������܂��A�c���ꂽ�Ƒ��ɂƂ��Ă̔߂��݂��J��
�����ŏI���ł͂Ȃ��A�����Ƒ����Ă����̂��Ǝv���܂��B

�v�钬 �q�{���� (60��)
���A���̉Ƒ����o�������펞���̘b�����`���������Ǝv���܂��B
���͐��O�A��P�x�邽�тɔ����ɐg���B���A
B29������ʉ߂��鉹���Ȃ��������グ�Ă����Ƙb���Ă��܂����B
�G�@���猩����Ȃ��悤�ɁA���̕��̂ɔ킹�Ă��������ł��B
����B29�̔�s�������Ő^���Ă��ꂽ���Ƃ�����܂����A
���ۂɂ��̉������҂łȂ���Ε\���ł��Ȃ��悤�ȁA�ƂĂ����͂̂�����̂ł����B
���̕���̑c���ƍȂ̑c���́A���ɐ펀���Ă��܂��B
�c�ꂽ���͐푈�ɂ��đ�������邱�Ƃ͂Ȃ��A�c�O�Ȃ��炻�̑��������ƂȂ��S���Ȃ�܂����B
�����A�����q�ǂ��̍��ɑc��̉Ƃ�K�˂��ہA
�c�����o����ɂ�������M�͂������Ă��ꂽ���Ƃ�����܂��B
�c�S�ɂ��A���̌M�͂̔�������������ۂɎc���Ă��܂��B
�܂��A�Ȃ̕���̎��Ƌ߂��̔��ɂ́A�K�т���Ԃ��c����Ă��������ł��B
�푈�͖{���ɔ߂����o�����ŁA�����̐l�X��s�K�ɂ��܂��B
��x�Ƃ��̂悤�Ȕߌ����N�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƌ����v���܂��B

�V���s �r�c����i70��j
���̕ꂪ���O����Ă��ꂽ�푈�̌��ɂ��Ă��`���������Ǝv���܂��B
���̕��2�l�̌Z�͋����B�E��V�s�ŏI����}���܂����B
�����A���͌R�ɒ�������A�ǂ��ɍs���Ă��邩���킩��Ȃ��܂܂ł����B
���{�̔s��Ɠ����ɁA��͎���ɖ߂�Ɩ\�k�ɏP����댯�����邱�Ƃ�m��A
2�l�̌Z��A��čH��Ւn�̓���e���g���������ł��B
�������A���e���̊��͑z����₷��قǗ������Ƃ����܂��B
�J���~��Ή������Q���ɂ܂ŗ��ꍞ�݁A�����̑�l��q�ǂ��������ԗ��Ɋ������A
�c���������X�Ǝ����Ă����܂����B
1946�N8���A���̂悤�Ȑ�����1�N���߂������A����5���������̌Z���ԗ��Ɋ������܂����B
���ɓ��ɐ��サ�Ă����Z�́A�����ɂ�����
�u���ꂳ��A�l�A�����ɂȂ肻������B���ʂ̂��|������ꏏ�ɗ��āv�ƌ�肩���A
�Ŋ��ɂ́u���ꂳ��A���ꂢ�Ȃ��Ԃ������ς��炢�Ă��邩��E��ł�����ˁv�ƁA
�Ԃ���n���悤�Ȏd�������āu�F�B���Ă�ł��邩��s���ˁv�ƌ����A
�Â��ɑ�����������������ł��B
����1������A���{�ւ̈����g���D�����B�ɓ������܂����B
��́u�Z�����Ə����撣���Ă�����A���{�̏��w�Z�ɓ��w����Ƃ��������������̂Ɂv�ƁA
�[���Q���Ă��܂����B
��͈⍜������āA���{�ɋA��ƁA������ɒʂ��܂����B
�J�̓��ɂ͎P���A�������ɂ͕��𒅂��ɍs���ȂǁA�Z�ւ̐[���������������Ă��܂����B
���ꂩ��1�N��A�V�x���A�ɗ}������Ă��������A�҂��A
��͂��̎����߂ĐS�䂭�܂ŗ܂𗬂����Ƙb���Ă��܂����B
�������܂ꂽ�̂́A���̏o�����̌�̂��Ƃł��B
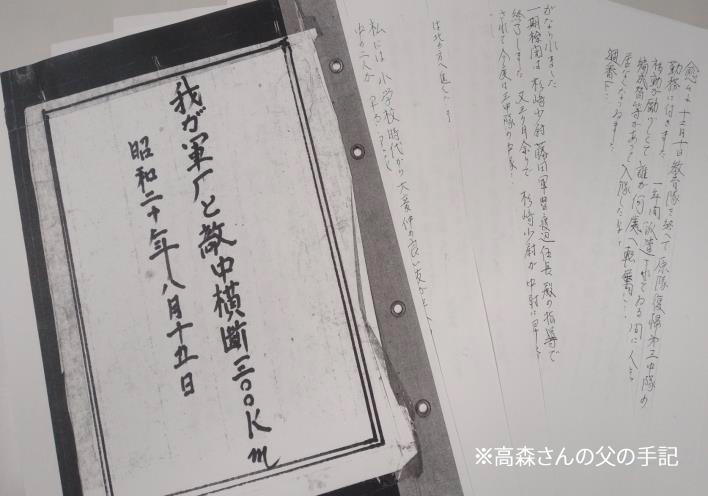
��v��S ���X����i70��j
����L�̌������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B
1945�N8��7���A���͖��B���k���̊X�n�C�����ւ̈ړ��𖽂����A��8���ɓ������܂����B
�������A���̗����̌ߑO4���ɂ͔�탉�b�p���苿���A�u�\�A�R��������˔j���n�C�������ʂi�U���v�Ƃ̏����܂����B
�ߑO8���ɂ̓n�C�����s�X���\�A�R�̋��n�߁A���̔����͎������قǂł����B
��������600�l�̕����́A�n�C�������狻����̖{���Ƃ̍�����ڎw���s�R���J�n���܂����B
�����͍�����i�ޗ\��ł������A�G�̐N�U�������A�v���v���̏W���ɂ͂��łɓG�e�����������߁A
���Ȃ�����i�ނ�������܂���ł����B
3���Ԃ̍s�R�Ő����H�����s���A�������I��������A���ގ҂������Ƃɑ����Ă����܂����B
����ł�����}�����߁A�菕������]�T�͂Ȃ��A������������̏d���ɑς����˂�
���X�Ǝ̂Ă�ł����B
�I���m�炳��Ȃ��܂܁A8��16���ɖړI�n�̑O����n�ɂ��ǂ蒅���A
���߂Ă܂Ƃ��ȗ[�H���Ƃ邱�Ƃ��ł��܂����B
����7���A�s�R���ĊJ����ƁA�������e���������n�߁A�㊯����u�U��A�U��v�ƌ���֎w�����o�܂����B

�ӂƌ��グ��ƁA�������u�̏ォ��G����Ďˌ��ŏe�e�𗁂т��Ă��܂����B
�������ɉ��킷��e�͂Ȃ��A���t�ł͕\���ł��Ȃ��قljJ�����̂悤�ɒe���~�蒍���܂����B
���͓y�����Ԃ�A�����Ă���ƁA�����ׂŒ��Ԃ��ߖ��グ�ċꂵ��ł��܂����B
�g������ł����A�����ڂ���Ēe����ނ̂��F�����ł����B
40������50���قnjo�������ł��傤���A�G��200���[�g���قǐ�܂Ŕ����Ă��܂����B
���͕�ɑ��u���͎��ɂ܂��v�ƂԂ₫�Ȃ��痼��������ė����オ��ƁA���r��e���ђʂ��܂����B
�����ɂ������ɂȂ�A�������ɏ��삪����̂������܂����B
���͖����Ŕ�э��݁A���̒���2�l�Ƌ��ɓG���猩���Ȃ��ꏊ�܂œ������т܂����B
���ꂩ��́A�����G�Ɍ�����Ȃ��悤���������܂����B
���鎞�́A�m�炸�Ƀ\�A�R�̖�c�n�̘e��ʂ��Ă��܂������Ƃ�����܂����B
�������Ă���ΎE����Ă����ł��傤�B
������8��28���̗[���A2�l�̒j���n�������Ă�����������Ă��܂����B
�P�l���u�����n�ɏ��v�Ɠ��{��Ō������̂ŁA���́u���{�l���I�H�v�Ƒ吺�ŋ���ł��܂��܂����B
����́u���O�����͂ǂ��̕����ŁA�ǂ����痈���H�v�Ɛq�ˁA���́u���Ƃ���600�l�̕������������A
�r���G�ɑ������e�Ō�����A3�l�����ɂȂ��Ă��܂����v�Ɠ`���܂����B
����ƂP�l�������������ԓx�ŁA�u���͓��{�͕������̂��B8��15���A�������Ő푈�͏I���A
�V�c�É����璼�ڕ������������v�ƍ����܂����B
���̌��t�Ɂu�A�A�A�v�Ƒ傫�Ȃ��ߑ����o�܂����B����l�߂Ă����̂���������Ƃ������o�ł����B
���Ԃ̂P�l�́u��������ł������ł���v�ƂԂ₫�Ȃ�������Ă��܂����B
���Ǝ��̕����ꓹ��H��Ȃ���A�������͐����������̂ł��B
���̌�A�������̓\�A�R�Ɂu���{�A��v�ƌ���ꂽ�ɂ��ւ�炸�A�V�x���A�ɗ}������܂����B

�F�{�s ��������i�W�O��j
����L����Ɍf��
�I��܂ł̂P�X�S�S�N�`�P�X�S�T�N�ɂ����ẮA��������P�ɑ����܂����B
�A�����J�R�̐퓬�@�͗ΐ�̏��Ⴍ���ł��ẮA�@�e�|�˂��J��Ԃ��܂����B
����A�e�r�s��������K�ꂽ�ہA
1945�N�����A���������w�Z4�N�����������̋L�����h���Ă��܂����B
�틵���������𑝂����A�������̓���͌ߑO���̔_��Ƃƌߌ�̐�V�т�
��₳��Ă��܂����B
���̂悤�ȏ��A�_�Ƃ̔[���̂Q�K�ɂ͕��m�������ʐM�@����������݁A
�A�����J�R�̏㗤�ɔ����Ă���l�q�ł����B
�������ʐM�@��ɋ����ÁX�̎��́A���������Ă��炢�ɍs���̂�
�y���݂łȂ�܂���ł����B
���ɁA�������o�g�̂��镺�m�̕��Ƃ͐e�������Ă��������A
�F�X�Șb�����Ă����������ŁA
�u���̎���͌N�������S���B�撣���Ăق����B�v�Ɨ�܂��ꂽ���̂��Ƃ́A
�q�ǂ��S�Ȃ���ɂ��g���������܂�v���������̂��o���Ă��܂��B
�܂��A�������ɂ͓��U���̒��p��n�ł������u�e�r��s��v������A
�������̃}�t���[��g�ɂ���4�`5�l�̓��U�����������g���b�N�ňړ����A
�������Ɍ����Ɏ��U��p���A���̖ڂɂ͊i�D�ǂ��A������ۂɎc��܂����B
���������̎��A�w�Z�̐�y����u���̐l�����̓j�R�j�R���Ă��邯�ǁA
�₪�Ď��Ȃ��Ƃ��B�v�ƕ������ꂽ���t���A���ł��[���S�ɍ��܂�Ă��܂��B
����ł����́A�g���b�N�ɏ���čs�����U���������̌��ǂ������A���U�葱���܂����B
���̓��́A80�N�̎����o�������ς�炸�����ɂ���܂��B

�F�{�s ��������v�ȁi�X�O��ƂW�O��j
�������v�w�͏I��̎��A�P�O�ƂX�B
�Q�l���ɍ��̏�쒬(�F�{�s)�ɏZ��ł��܂����B
�I��܂ł̂P�X�S�S�N�`�P�X�S�T�N�ɂ����ẮA��������P�ɑ����܂����B
�A�����J�R�̐퓬���͗ΐ�̏��Ⴍ���ł��ẮA�@�e�|�˂��J��Ԃ��܂����B
�퓬�@���甭�˂��ꂽ�e�͉J�̂悤�ɍ~�蒍���A��U����ʉ߂������Ǝv���ƁA
U�^�[�������Ă��čĂэU�������Ă��܂��B���X�ȍU���ł����B
�h�ɓ����Ă��A�e������鉹�������������Ă��܂����B
���炭�A���������Z�ޒn��ɂ́u�G����s��v������
�߂��̒|�тȂǂɔR����e��Ȃǂ��B����Ă������߁A
�����_���Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B
�������̐e�̘b�ł́A�_��Ƃ����Ă���Ƃ��ɋ�P������ƁA
�_�앨�̑傫�ȗt���ς̉��ȂǁA���낢��ȏꏊ�ɉB��Ȃ���
�h��ڎw���ē����Ă����Ƃ����܂��B
���v���Ƌ��낵���b�ł����A�q�ǂ��̍��̎��������ɂ́A
�܂��u�|���v�Ƃ������o������܂���ł����B
�I���A�u�G����s��v�ŌR�p�@�Ƃ��̊i�[�ɂ�
�����Ԃ����ăA�����J�R�ɂ���ďċp��������Ă����̂��������A
�q�ǂ��Ȃ���Ɂu�푈�ɕ���������d�����Ȃ��v��
�����Ă������Ƃ��o���Ă��܂��B

�����s �₳��i�U�O��j
*�₳��͔���s�o�g *��L����Ɍf��
�P�X�S�R�N�T���B
���R���狌���q����(�����q���� �y�ь����{�����̑O�g)�ɑ��A
�}�j��(�t�B���s��)�ɐ����H��J�݂̖��߂��������B
�R�Ƃ��ẮA���n�ŐV���p��������`��ɋ��͂���Ƃ������̂������B
�����A��`�͏d�v�ȍ��ŁA�R�Ƃ��Ă��������͓S�C�ʂƓ������炢�̕K���i�ŁA
�ł��邾���������̐����������Ă��炢�����Ƃ̈ӌ��������悤���B
���X�A�����q�����ł͎��̐����͍����ōs���A
���n�֎����Ă��������ǂ��Ƃ̍l�����������A
���̌R�̗v���ň�C�Ƀ}�j���i�o�ւ̑ǂ�邱�ƂɂȂ����B
�}�j���H�ꌚ�݂ɂ́A���ݑ��Ɨv���Ƃ��č����H�ꂩ���]�҂���������
�V�V�l���W�܂�A���̓��̂R�����ƂȂ�Q�V�l���F�{���ɂ���������H��(�����{����)��
��{�H�ꂩ��I�ꂽ�B
���̌��ݑ��Ɨv���́A�P�X�S�R�N�W�����痂�N�R���܂ł̊ԂɑD�Ő������C���Ă��������A
�A�����J�R�̐����͂ɂ��U�������������钆�A�����U���̊댯�Ɣw�����킹��
�������̓n�q�ƂȂ����B
�܂��A�v����q�������̂������ɂ��l��s���ɉ����A
�A�����J�R�̐����͍U���ɂ��A���D�s�����d�Ȃ�A
�@�ނ��}�j���ɃX���[�Y�ɓ͂��Ȃ��Ȃ��Ă����B
����ɁA1944�N�X���ɂ́A�@�ނ��ڂ����A���D���}�j���`�ɓ��`�������A
�A�����J�R�̋��͍ڔ����@�ɂ���ċ�P���p�ɂ����D�̂قƂ�ǂ����v���A
���@�ނ̔������C�ɒ��B
���̏ɁA�}�j���H��̏����͌��ݑ��Ɨv����O��
�u�G�̍U���ŁA�@�ނ̔����ȏオ���߂��A���{����@�ނ�����]�݂��Ȃ��B
�܂��A�G���i�U���Ă�����������Ȃ��B
���̒n�Ŏ����o�傹����Ȃ��ł���B�v�Ƙb���A�S���ɋْ����������B
���̏�ŁA�����́u��]�I�ȏ����A�����ʑO�Ɏ�����낤�����Ƃ���蔲�����v
�ƒ�Ă��ꓯ�����ӂ����B
�������A���̌��݂͓G�̋�P�Ə㗤�����肭�钆�Ŏn�܂����B
���̐����J�n�ڕW�͂R�������1944�N�P�Q��20���B
���肠�킹�̋@�B���i�����J�肵�Ȃ���A�������Ȃ���Ƃ�i�߂��B
�P�Q���P�X���ɂ́A���R����Ɩ����~���߂��o���ꂽ���A
���̐����܂ł�������̂Ƃ���܂ł��Ă������ƂȂǂ���A
�g�������h�v��͑��s���ꂽ�B
���̌��ʁA�ڕW������12���Q�O���ɂ͊Ԃɍ���Ȃ��������A
4����́A�Q�S���ߌ�S���Ɏ��̐������\�ƂȂ�A
�}�j���Łg�������h�Ƃ����肢�͒B�����ꂽ�B
���̓��͌��ݑ��Ɨv���V�V�l�S���ŏj�����J���A
�e�X���������|���I���钆�A�u�^�P����H�V�ɁA���������y���ނȂ�
�ߍ��ȓ��X�̒��ŋM�d�Ȋy�����ЂƎ��ƂȂ����B
���������̌�A�Ԏ��ߏ����q�����Ɉꊇ���đ����Ă��āA
���N��1945�N�P���V���ɂ͑S���������B
����ƍ��킹�邩�̂悤�ɁA�A�����J�R�����\����(�t�B���s��)�ɐi�U���Ă����B
���ݑ��Ɨv���̓�����͕̏������Ă��Ȃ����A
�V�V�l�̂قƂ�ǂ��펀���A���{�ɋA�҂ł����̂͂T�l�݂̂������B
72�l�����ǂ��Ő펀�����̂����킩��ʂ܂܂��B
�펀������l�ɂ́A���̑c��������B

�F�{�s �ɓ�����i�V�O��j
����L����Ɍf��
2020�N�ɖS���Ȃ���1919�N���܂�̕�́A�펞���A�����̐l�������ł������悤�ɁA
���g���u�R�������v�ƌ���Ă��܂����B
��͗��R�̗v���ɂ��A1938�N10������1943�N�܂ł̊ԁA
�k���N���f�i���a�@�A�R���ȑ�����⋕a�@�A�����č]�h�Ȓ��]���R�a�@
�i�a�@���͂��������̎�L�ɋL����Ă����܂܁j�ɊŌ�t�Ƃ��ċΖ��������܂����B
���Ԃ̋Ζ��ƎO�����Ƃ̖�Ƃ�����ςȓ��X�������悤�ł����A
�Ⴉ������́A���̂��߂ɓ������ƂɌւ�������A����t�w�߂Ă����Ƙb���Ă��܂����B
�R���ȑ����̕a�@�̒���ɂ͑����̃����̖��A�����Ă��āA
�����������~���z���A4���̏I��荠�ɂȂ�ƁA���������ɔ����̍���̍����Ԃ�
�炫�n�߂������ł��B
���a�������̖����ɂ��̉Ԃ�����A�Ԃ߂Ă������ƂȂǁA
�����̑N��Ȉ�ۂ͐��U�Y����Ȃ���̌����i�ƂȂ��Ă����悤�ł��B
���鏝�a���̕�����́A�މ@��ɒZ�̂�ʐ^�������Ă��āA
�莆�̂����������������ł����A�V�x���A�֏o������Ƃ����m�点���Ō�ɁA
�A�����r�₦�Ă��܂����ƕ����Ă��܂��B
�����炭�A���̂܂ܐ�n�ŖS���Ȃ�ꂽ�̂ł��傤�B
�I���A��͎�ŒZ�̂�n��ł���A�푈����̎v���o���r�̂��c���Ă��܂��B
�w�t���������̒��������炯��
�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ȃ������̖��ӂɊ���
�J���e����Ζ�������Ⴋ�����Ȃ肫
�@�@�@�@�@�@�@�@�V���̔@���ɐ����������
�Ŏ�肹�� ���̓��͂͂邩�킪���
�@�@�@�@�@�@�@�@�����炫���ւ� �����k�u�߁x
�t����𒆍��̐�n�ʼn߂�������ɂƂ��āA
�����̏ꏊ�͎v���o�[�����̂������悤�ł����A
�u���̎��̕a�@�́A�����l��ǂ��o���Ďg���Ă����̂��Ȃ��B�v�ƁA
�ӂƎ₵�����Ɍ���Ă��܂����B

�F�{�s �₳��i�X�O��j
1945�N�t�A����9�̎��̏o�����ł��B
���̓��́A�ǂ��܂ł��L����悤�Ȕ�������ł����B
�����A���͌F�{�s�̎��_�Ђ̋߂��ɏZ��ł��܂������A
�ˑR�A�u�u�����u�����v�Ƃ�����s�@�̉����߂Â��Ă������Ǝv���ƁA
�����{�R�̔�s�@���M�����Ȃ��قljƂ̂����߂��܂ō~��Ă����̂ł��B
���̎��A�Ƃɂ�����Ǝ���������グ��ƁA
��s�@�̑��c�Ȃɂ͌����ꂽ�炪����܂����B
����́A�������ƗV��ł���Ă����ׂ̂��Z�������̂ł��B
�����}�t���[��g�ɂ��A���ʂ݂̏Ŏ������Ɏ��U���Ă���܂����B
��x�����łȂ��A��s�@�͏�����A�Ăю������̑O�Ŏ��U���Ă��ꂽ��A
�܂�ŕʂ�������邩�̂悤�Ɏ嗃���㉺�ɗh�炵�Ȃ���A
���̋�ւƔ�ы����Ă����܂����B
�c�����́A���Z����̙z�X�����p�����āA�u�����Ĉ̂��l���v�Ɠ���܂������A
�ꂪ���̔�s�@�������ƌ��߁A�܂𗬂��Ă���̂����āA
�Ȃ������Ă���̂��낤�ƕs�v�c�Ɏv�����̂����ł��N���Ɋo���Ă��܂��B
���N��A���̎����U���Ă��ꂽ���Z���A���U�����Ƃ���
�펀�������Ƃ�m��܂����B
�����̎��ɂ́A�D�����������Z�����̂悤�ȉ^����H��Ƃ�
�z�������Ă��܂���ł����B
����܂ŒN�ɂ��b�������Ƃ̂Ȃ��L���ł����A
���̏o���������p���ł����K�v������Ɗ����A���b���܂����B

�F�{�s �ɓ�����i�V�O��j
����L����Ɍf��
���̗��e�́A�푈�Ƃ��������̎����t����ɉ߂����܂����B
1912�N���܂�̕��͐��O�A�܂ɐG��Đ푈�̑̌������Ɍ���Ă���܂������A
����͂��̋M�d�ȋL���͂ɂ������Ǝv���܂��B
���͕��i�A�푈�̘b��ϋɓI�ɂ��邱�Ƃ͂���܂���ł������A
���������ނƁA���̑s��ȑ̌�������Ă���܂����B
��x�̒������A�ŏ��͖k���̒n�ցA��x�ڂ͓���̃t�B���s���ցB
�����ŏI����}���������ł��B
�펞���A�㊯����G�����n�l��������܂��A�E�Q����悤���߂��o�����ɂȂ����ہA
�u�܂��҂��Ƃ��v�Ɠ����o�������Ƃ��������ƕ����Ă��܂��B
���́A���ڎ�������Đl���E�߂邱�Ƃ͂Ȃ������Ƙb���Ă��܂����B
�������A�t�B���s���ł̃A�����J�R�Ƃ̌������U�h�́A�z����₷����̂������悤�ł��B
�J�����ƍ~�蒍���e�e�̒��A�ӂƋC�Â��Ƃ����ׂɂ������Ԃ��I�̑��̂悤��
�e�e�𗁂тĖS���Ȃ��Ă����A�ƁB
�܂��A�ςݏd�Ȃ��������̈�̂����z���Ȃ���i���Ƃ������������ł��B
���鎞�A���͂���Șb�����Ă���܂����B
�����𗦂��Ă��ڒn�ɐ���ł������A�u�Ȃ���A�Ȃ���v�Ƃ�������
�ǂ�����Ƃ��Ȃ��������Ă����Ƃ����̂ł��B
�u�Ȃ���v�Ƃ́A�������̕����Łu�ꏊ���ڂ��v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�s�v�c�Ɏv���Ȃ�����A���̐��ɏ]���Ĉړ���������A
�܂��Ɍ��̏ꏊ�������W���C�������������ł��B
�㎀�Ɉꐶ���u�Ԃł����B
���́A���������̖������F���Ă���Ă�����e��
�����Ă��ꂽ�̂��낤�ƌ���Ă��܂����B
�틵����������ɂ�ĐH���͐s���A�F���Q���ɋꂵ�݁A
��������̂����ɂ����Ƃ����܂��B
���ɂ́A�ւ�߂܂��ďĂ��ĐH�ׂ����Ƃ������������ł��B
�������ĐX�̒���f�r���Ȃ���A�Ȃ�Ƃ��������тĂ����̂ł����A
�������E���Ǝv�������A�A�����J�R�ɕ߂炦���܂����B
���������x��Ă�����A���𗎂Ƃ��Ă������낤�ƕ��͌����Ă��܂����B
���炭�ߗ����e���ł̐����𑗂�����A���͖����ɋA�����邱�Ƃ��ł��܂����B
�������A�̋��ɖ߂������A�܂��Ⴉ�������̔��͐^�����ɂȂ��Ă����Ƃ����܂��B
���̐��҂́A�{���Ɋ�ՂƂ��������悤������܂���B
���͐푈�̌������ƁA�Ō�ɁA�������������Ă��܂����B
�u����ȋ���ȍ��ƁA���Ȑ푈�������B�푈�ȂA��ɂ��Ă͂�����B�v

�ʖ��S ���c����i�T�O��j
1931�N���܂�̎��̕ꂩ�畷�����b�ł��B
�ꂪ���w�Z�ɒʂ��Ă������́A�����y�ɖh�Ђ����Ԃ�A
�~�}�܂ƃ����h�Z�������ɂ����ēo�Z����̂�����̎p�����������ł��B
��̕��e�̎d���̊W�ŁA���w�Z6�N���̍��ɂ�
���茧�̍����ۂŕ�炷���ƂɂȂ�܂����B
�i�w�̂��ߖ�w�ɂ��ʂ��Ă�����́A��P�ɔ����ĊX�̊e�ƒ�̓d���������z�ŕ����A
�����R��Ȃ��悤�ɂ��Ă������߁A�铹�͐^���ÂłƂĂ��S�ׂ������悤�ł��B
����Ȓ��ł��A�y�����v���o�������������ł��B
����́A�C�R�̎w���ōs��ꂽ����M���̌���Ɉꐶ�������g���Ƃł����B
���w�Z�ɓ��w���鍠�ɂ́A�푈���������Ȃ�A
����R���H��֓��������悤�ɂȂ�܂����B
�G�@�͒�����킸�P������悤�ɂȂ�A�������܂����T�C�����̉����苿���ƁA
�l�X�͈�ڎU�ɖh�삯�������ł��B

������1945�N6��28���B
�����̂悤�ɏ��ɂ��Ă���ƁA�ˑR�Ƃ̒������Ԃ̂悤�ɖ��邭�Ȃ�܂����B
�O������ƁA������ɏƖ��e�����Ƃ���A
�X�S�̂��^���̂悤�ɖ��邭�Ƃ炳��Ă����̂ł��B
���̌�A�X�݂͂�݂邤���ɉ̊C�ƂȂ�܂����B
���ꂪ�����ۑ��P�ł��B
������������E����������l�X�����Ȃ���A�痎���Ă���ĈΒe������A
�R�ɂ���傫�ȍ���ڎw���ĕK���ɑ���܂����B
���̗����̉ƁX���R�����钆�ł̔��́A�̂�M���Ă��A
�h�Ηp���̃^���N�̒��ɉ��x����э������ł��B
�����2000�l�قǂ����ł���h�ɂ��ǂ蒅���ƁA
���ł͑吨�̑�l���������X�Ǝq���̖��O�����сA���Y��ĒT������Ă��܂����B
���낵����邪�����A������܂�ƁA
�����̑̂̂��������ɉΏ����A���Ă����m�����Ă��ł��Ă���̂����āA
�܂����t���o�Ȃ��������Ƃ��o���Ă���ƕ�͌���Ă��܂����B
���̂悤�ȏ��ł��A�����̐l�X�͕K����������ƍŌ�܂ŐM����
�撣���Ă��܂������A8��15���ɏI����}���܂����B
�������āA�炢���Ƃ�ꂵ�����Ƃ��䖝���Ċ撣�����͉̂��������̂���
�v�������ʁA�����������т��ĕ�炷�K�v���Ȃ��Ȃ������ƂɋC�Â��������ł��B
�푈��m��Ȃ��F�l�ɁA�푈�͓�x�ƋN�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ�
�ǂ����Y��Ȃ��łق����ƁA��͊���Ă��܂��B

�F�{�s �R�{����i�U�O��j�V���s �Ό�����i�T�O��j
�V���s���{���ł́A�����ߌ�5���ɂȂ�ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ����̉����������Ă��܂��B
���̉��́A�s�m�ΊC�������낷����ɘȂމ~�����Ƃ��������狿���Ă�����̂ł��B
�������A���̏��̉��́A1940�N��Ɉ�x�r�₦�Ă��܂��܂��B
�����m�푈�J�킪�߂Â����A���{������̌����Ƃ��邽�߁A�S���̎��@�ɑ�
�����Ȃǂ̋����ނ̋��o�𖽂����u�����މ���߁v�ɂ����̂ł����B
�~��������O�ł͂Ȃ��A���N�n��̐l�X�ɐe���܂�Ă������̉���
��������ƂɂȂ����̂ł��B
�I���A�S���I�ɞ������Č����悤�Ƃ����������N����܂��B
���̈�ɁA�펞���ɉݕ��D��R�͂Ȃǂ��������Ă����������D�i���݂̃J�i�f�r�A�j
������܂����B
�J�i�f�r�A�Ɏc�铖���̎����ɂ́A
�u���S�N�Ԃ����a������Ă������������ׂ���R�����i�ƂȂ�A
���ꂪ�܂������ɖ߂邱�Ƃ͕����ł����։�����̂��v�ƋL����Ă��܂��B
�I��ƂƂ��ɌR�����i����Y�ƕ���ւƓ]����}���Ă����������D�ł́A
�q���́u�ق����傤�v��u���炬�v����̂���A
���̍����ł���X�N���b�v�������̍ޗ��̈ꕔ�Ƃ��Ďg���邱�ƂɂȂ����̂ł��B
���̓������D�̎��g�݂ɋ������̂��~�����ł����B
���݂̏Z�E�ł���Ό��j������i55�j�ɂ��ƁA
1948�N�A�ޗǂ̖@�R���ŏZ�E�����Ă����c�����V���ɖ߂�Ƃ�����
�����Č��̂��߂̊�t����܂����B
�Ό�����́A�c���̂��̐v���ȍs���́A�@�R���Ŋ���
�������D�Ƌ��ɞ����̍Č��Ɍg����Ă����o������A
�l�̐S�ɋ������̉��̑����[���F�����Ă�������ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B

��t�͒n��̐l�����𒆐S�ɖ�1000�l����W�܂�A
�c�����V���ɖ߂��Ă����2�N���1950�N�A���ɞ����͍Č�����܂����B
���ꂾ���̐l�����t���W�܂������R��Ό�����́A
�����A�����̐l���푈�Ŏq�ǂ���e��S�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ��A
���̂悤�ȏ̒��Łu���̉����������邱�Ƃŋ��{�ƂȂ�A�݂�Ȃ��~�����
�v�����̂ł͂Ȃ����v�ƁA���̓����̐l�����̎v���𐄂��ʂ�܂��B
���a�ւ̊肢�����߂�ꂽ�~�����̏��́A
�����ς�炸�A�Â��Ɏ������������Ă��܂��B


�F�{�s ����i�U�O��j
���N�X�R�ŖS���Ȃ�����́A�F�{�`(�F�{�s)�߂��Ő��܂�炿�A
10�l�ȏ�̌Z�������܂����B
�������w���̍��A�ꂪ�푈�ɂ��Č���Ă��ꂽ�̂́A
1945�N�̌F�{���P�̂��Ƃł����B
�u���̓��̖��̖��邳�́A�Ⴆ�悤���Ȃ����炢�����������v�ƁB
��͐푈�̋��낵���ł͂Ȃ��A��P�̌��i���u�����������v�Ƃ����\����
���ɓ`�����̂ł��B
���炭��P�̔�Q�̑傫����`�����������̂��Ǝv���܂��B
�������A�c���������ɂ́u���̋�P�ő����̐l���S���Ȃ����̂Ɂv�ƁA
���G�ȋC�����ɂȂ����̂��o���Ă��܂��B
����ŁA�ꂪ�Z��ł����n��ł͋�P�̔�Q�͏��Ȃ����������ł����A
��ԉ��̖���3�̎��ɁA�s���e���������ĖS���Ȃ����ƕ����܂����B
�����A�����܂��q�ǂ��ŁA���̘b��^���ɕ������Ƃ��ł��܂���ł����B
�������A�����e�ƂȂ�q��������A���j������Ԃ��Ȃ��a�����A
����ɓ���20�����������������Ŗ���D��ꂽ���ƂŁA
�ꂪ����S���������̋ꂵ�݂��A�悤�₭�����ł����C���������܂����B
���U��Ԃ�ƁA��ɑ��Ă��������v���������ׂ��������ƒɊ����Ă��܂��B
�������������̕�̋ꂵ�݂́A�z����₷����̂������ł��傤�B
�푈�ł́A�F�{�ł������̐l�������S���Ȃ�܂����B
�푈�́A�S�Ă̐l��s�K�ɂ�����̂��Ǝv���܂��B
���̎Ⴂ����̕��X�ɂ́A���Đ푈�Ƃ������オ���������Ƃ�
�����ĖY��Ȃ��łق����Ɗ���Ă��܂��B
�������A�����ɂ��Ăق����ƐS�������Ă���܂��B
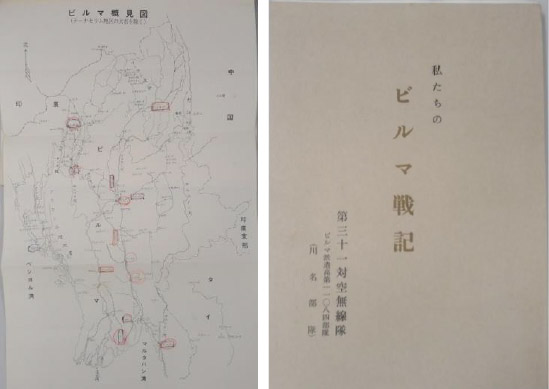
�F�{�s �b�コ��i�V�O��j
1916�N���܂�̕����������߂Ă�����L�ł��B
�ȉ��A��L���甲���������e���L�ڂ��܂��B
���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B
�哌���푈�i�����m�푈�j�ɂ���
1941�N11���A���̍��̂��ߑ�p�őҋ@���Ă��܂����B
����܂ł̎x�ߐ���Ƃ͈قȂ�A�@�B�����i��ł��܂����B
��X�͍ŋ��̊C�������Ƃ��āA�G�O�㗤����Ƃ��镔���ł����B
���Y�ɏW�����A�ҋ@���ɐ퓬�����𐮂��A���̌�A�C��ҋ@�ƂȂ�܂����B
12��5���ɂ͏o�w�����s���A�c���ɍŌ�̕ʂ�������܂����B
12��7���A�A���D�c�͏��������������l�q�ŁA�C��ɓ��X�Ƃ����p�������Ă��܂����B
12��8���A��{�c���甭�\������܂����B
�u�����ɂ킽��o�ϕ����A���邢�͑Ύx��ɂ�����ĉp�̑Ύx�x���Ȃǂ���A
�ĉp�Ƃ̐퓬�J�n�v�Ƃ̂��Ƃł����B
12��17���A�n���i��p�j��邩�ɏo�`���A60�Ljȏ�̑�A���D�c��
�C�R�̌�q�́A�d���m�́A�쒀�́A��s�������X�ƃt�B���s���ւƐi�����܂����B
�V�\���i�t�B���s���j�t�߂ɂĐi�����A�ČR�̉ݕ��A���Ԃ��b�l�i�납���j���܂����B
���̍ہA�s�^�ɂ��䂪�C�R�̔����@�����Ɍ���A�b�l�����A���Ԃ�
�G�̑ދp�ƌ�F���A�O���̔��e�𓊉����܂����B
���e�����������̂��m�F������X�́A��l�ɑ��a�ɐg���܂������A
����ɐ��܂����������N����܂����B
���̔����ɂ��A�����̒��Ԃ��]���ƂȂ�A����͈�u�ɂ��ďC���Ɖ����܂����B
�ɍ��̋ɂ݂ł���܂��B
���̌�A�Ԃ��Ȃ����āA�����C�R�����@���Ăь���A������Ă���܂����B
���炭�́A�딚��l�тɂ������̂Ǝv���܂��B
���̌�A�����@�͎R�A�ւƏ����Ă����܂����B
��ɕ������b�ɂ��܂��ƁA���̔����@�̑��c�m�́A����̎��Ԃ̐ӔC�����A
�������ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B
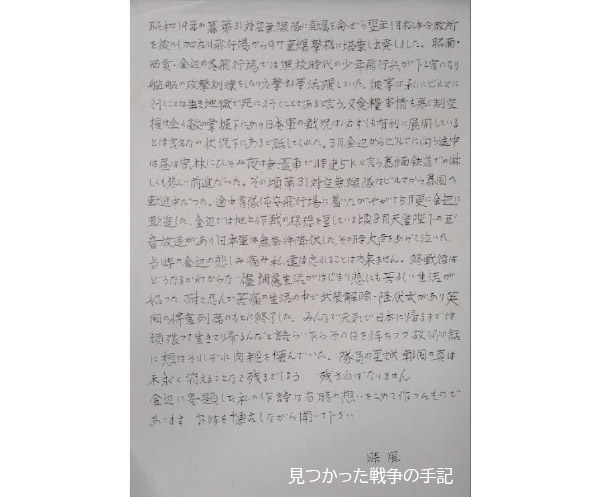
���āA1942�N2���A��X�̓W�������U���ւƌ������܂����B
40�Ǘ]��̑D�c�́A�R�́u�����v�u�H���v�Ƃ������d���m�͂ȂǂɌ�q����A
��ւƐi�����J�n���A�����ɐԓ���ʉ߂��邱�Ƃ��ł��܂����B
�����āA�X���o�����C��ɂ����āA�䂪�C�R�͎����̔@���O�i�������܂����B
��C�̐[��ɖC���M���A�邪�����ėA���D���猩��ƁA
�G�̊C�R���m���C�ʂ�Y���Ă���܂����B
�ǂ����A�䂪�C�R�ɂ���ăC�M���X�E�I�����_���m�͑��͑S�ł����悤�ł��B
3���ɂ́A�W���������̃N���K���ɓG�O�㗤���ʂ����܂����B
�G�͒�R�̂��ߑ����̕��͂�z�����Ă���܂������A�K���ɂ��F�R�̔�Q��
�͏��ł������ƕ����A���g���܂����B
3��8���A�䂪�R�͖��������Ă̑��U�����J�n�������܂����B
����ɁA�`���[�����ւ̐i�����J�n����A�䂪�����̓}���[�����֓]�o�̂��߁A
�o�^�r���`���o�`���A4��26���ɃV���K�|�[���֓��`���܂����B
�����͏㗤���̔C���ɂ��Ă��܂����̂ŁA
�A�����J�{�y�ւ̏㗤��킪�v�悳��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����b���o�āA
���ӌ������x�����������X�ł����B
���̂悤�Ȑ������������A�ǂ�����Ƃ��Ȃ��I��̒m�点���͂��܂����B
�c���̂��߁A���̓G�ɏ��܂ł͂Ƌ��������Ă����C�͂��A
�܂�ŖA�̂悤�ɏ�������A�͂������āA�Ƃ߂ǂȂ��܂�����܂����B
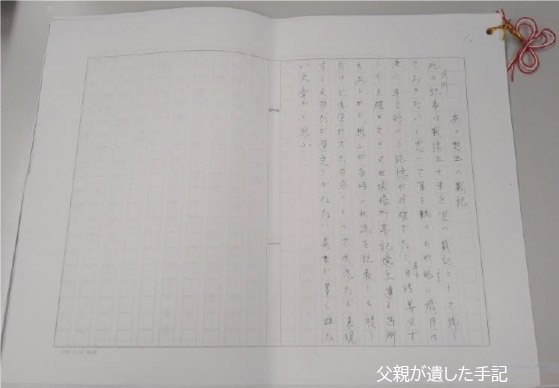
�F�{�s �|������i�U�O��j
���Ƃ���펞���̎ʐ^�Ȃǂƈꏏ�ɁA
�r���}�ł̐킢�Ƃ݂����L��������܂����B
���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B
1944�N�̕��ɑ�31�����ւ̓]���𖽂����A
���N1���ɏd�����@�ɓ��悢�����܂����B
����i�V���K�|�[���j�A���Ӂi�v�m���y���j�Ȃǂ̊e��s��ł́A
�F�{���R���N��s���w�Z�i�F�Z�j����̏��N��s�����������m���ƂȂ��Ă��āA
�ނ�͎��Ɂu�r���}�֍s�����Ƃ͐����n���ł���A���ɍs�����Ƃł���v�ƌ��܂����B
�܂��A�H�Ǝ���̈�����A�������S�ɓG�̏������ɂ���Ƃ�������������������܂����B
3���A�r���}�����������́A���Ԃ͖��тɐg����߁A��͉����̂Ȃ��ݎԂɏ��A
����5�L���Ƃ������x�ł̎₵�����߂����S���ړ��ł����B
���̍��A��31�����̓r���}������i�^�C�j�֓]�i���Ă��āA
�₪��5���ɂ͂���ɋ��Ӂi�v�m���y���j�ւƈړ����܂����B
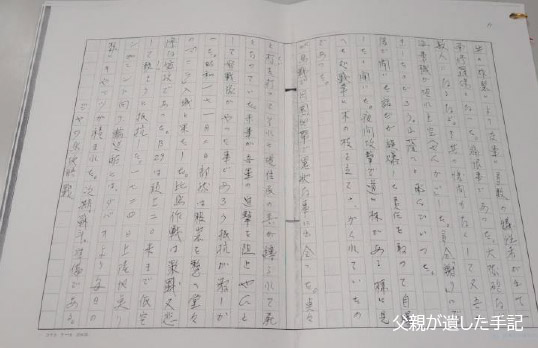
���Ӂi�v�m���y���j�ł́A�n����̗l����悵�Ă��邳�Ȃ��A
8���ɓV�c�É��̋ʉ�����������A���{�R�͖������~�����܂����B
���̎��A���͑吺�������ċ����܂����B
�����̋��Ӂi�v�m���y���j�ł̔߂��݂ƒɂ݂́A
���������ĖY��邱�Ƃ͂ł��܂���B
�I���A��̌����Ȃ��ߗ��Ƃ��Ă̐������n�܂�A
�߂��݂Ƌꂵ�݂ɖ��������X�𑗂邱�ƂƂȂ�܂����B
���̂悤�ȑς�������̒��A��������E�~����������s���A
�p���̏����̗�Ȃ̂��ƂɏI�����܂����B
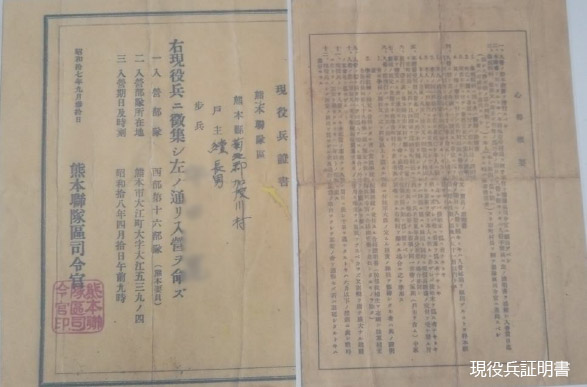
�F�{�s ���삳��(70��)
1922�N���܂�̕��̐펞���̌o����Ԃ�����L�ł��B
���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B
�����m�푈�ɓ˓����A�������퓬���Ɖ]���B
1943�N4��10���A���Ƃ��Đ���16������1�@�֏e�����ɓ����B
�����̏��N���͑���24�l�ŁA�F��ڌ��������ŋ����ȑ̊i�̎҂���B
���̂悤�ȏ��Əo�g�̎҂��A�ނ�ƑΓ��Ɍ��������K��P���ɑς��邱�Ƃ�
�ł���̂��낤���ƁA�s���������悬�����B
���������̒��H�͐Ԕтŏj���A�ߌ�͌��N�f�f�ɌR���p��̐����ƂȂ����B
�������ČR���̋K�����݂ɐ�y��y�̌������Ŋ����A
�R�K�Ƃ����ْ����Ə�ɗׂ荇�킹�̒��ŁA�R��������g�������đ̌������B
���̐�́A����ȓ��̂肪�����ł��낤�Ɗo�債�Ă��āA
�͂̌��萸�i����݂̂ƌ��ӂ�V���ɂ����B
�e�Z����͂��߁A�e�ʂ̕��X�ɂ́u���x����́A���̔����낤�v�Ɗo���`���A
�Ƃ���ɂ��Ă����B���͂����A�R�l�Ƃ��Ă̖{����s�������Ƃ�����S�ɐ����Ă���B
�S�g�̖Ғb�B�͊o��̏ゾ�������A���K�̉ߍ����A�A���Ă���悤�ɐh���v�����������A
�Ȃ�Ƃ��l���݂ɋC�������������A�����ւ̊�]�Ƃ��đς��E�ԓ��X�������B

�����āA�Y������Ȃ�7��18���̖�B
�_�Ă̑O�ɁA���N���W�̕����玄�����S���ɑ��߂ɏW�܂�悤�w�����������B
�ǒ������i�Ƃ͗l�q���قȂ�A��F�������A���������o���ɂ����悤�ȕ��͋C�������B
���̂悤�ȏ̒��A�ǒ��̌�������ꂽ�̂́A��F�Ƃ̕ʂ�ɂ��āB
���݁A�u�[�Q���r�����ŋ����������Ă��镔���ւ̕�[�v���Ƃ���
�h������镺�m�����̎��������\���ꂽ�B
���O���Ăꂽ�̂́A���N��24�l�̂���14�l�B
���̖��O�͌Ă�Ȃ������B
��������100���قǂ����o���Ă��Ȃ��������A��y�����ɏ��������Ă�����F�B
���̕ʂ�́A���t�ł͌����s�����Ȃ��قǐh�����̂������B
�܂��A�Ƒ��Ƃ̘A�����ւ����Ă������߁A�����F�͎��ɉƑ��ւ̘A��������Ă����B
�܂�����҂͗܂Ȃ���Ɂu�����ɂ͕�e���P�l�������Ȃ��B�ق�̏����ł���������A
��e�ɉ���Ƃ͂ł��Ȃ����낤���v�Ƒi���Ă����B
�����āA7��23���̖�10���B
��n���������m�����̑s�s��s��ꂽ�B
�^�V������핞�ɐg���݁A�����i����Ɏ�������F�����́A���t���o�Ȃ��l�q�Ɍ������B
�ꉞ�̈��A���I���ƁA��������擪�ɓ���Ɍ��������̌�A��Ԃɏ�Ԃ����B
�擪�ԗ��̕�����J���A��3���������Ǝv���ƁA��Ԃ͋D�J���炳�������n�߁A
��Ԃ͍����e�ƂȂ�A�F�{�w���ʂɏ����Ă������B

�F�{�s ���삳��(70��)
1922�N���܂�̕��̐펞���̌o����Ԃ�����L�ł��B
���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B
1945�N7��1���̐^�钆�B
�F�{�t�c�i�ߕ�(�F�{�s)�ɂ������̂��Ƃ������B
�ˑR�A�x���x��̃T�C�������苿���A�����ɋ�P�x��ɃT�C�����̉����ς�����B
���̂Q�`�R����ɂ͌F�{�w���ʂ���ŏ��̔����@�����A
����s�̂܂ܗ��c�R(�F�{�s)�̕����ɐi��ōs�����B
���c�R�ɂ͉��̕��ɂ�����A�����_�����Ǝv����B
���c�R�̕��ŁA�Q�`�R��������Β����オ�������Ǝv���ƁA���̔����@���B
���̌���Q�`�R���Ԋu�Ŕ����@�����X�Ɣ��A���Ɩ��e�𗎉���
�F�{�s���́A�����̖�̂悤�ɖ��邭�Ȃ�A���|��Y�ꂠ�R�ƂȂ����B
���̌���A�����@�͖ڑO����Œʂ�߂����쉈����k�サ�A
���O���A��]���ʂ͉Ή��ƍ����ɕ�܂ꂽ�B
�����A�݉c�����͂قƂ�NJe�n�ɑa�J���Ă��āA��ˌ��͂ł����A
�G�@�̂P���Ԉȏ�ɋy�Ԗ����ʍU���ŁA�t�߈�т͏Ă������ꂽ�B
�����A�؈�쉈���ɍL�����瓡��{�̒�����������ƁA
�Ă��Ղ͂܂����X�����A���������ɂ����Ԃ��Ă��錚���������������B
����Ȓ��A��ԍ������̂́A�Ȃ�Ƃ��\�����������ĈΒe�̓����ł������B
���̌�A�����甒�������ƁA�ĈΒe�̊k�������ɎU�����A
���ɂ͂Q�`�R�O�L�����炢�̏����e���������B
�A�����J�R�͋���W�I�ɂ����̂�������Ȃ��Ǝv�����B
���̎��̋L���͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B

�F�{�s �`����i80��j
1910�N���܂�̎��̕����A1987�N���ɑ��푈�̌���������ۂ�
�^���L�^���܂Ƃ߂����̂ł��B
����1941�N9����2�x�ڂ̏��W�ߏ���A���}���i�����s�j�������܂����B
����3������ɂ͑����m�푈���n�܂�A���������́u���A�����J�R���U�߂Ă���̂��v��
�s���ȓ��X�𑗂��Ă��܂����B
��1942�N�ɂ́A���}������k�C���ֈړ����邱�ƂɂȂ�܂����B
����́u�k����A�����J�R���U�����Ă���\���ɔ�����v�Ƃ������߂ɂ����̂ł����B
�����z�u���ꂽ�̂́A�瓇�̓��[�Ɉʒu�����瓇�i����ނ���Ƃ��j�ł����B
�G�̍U����H���~�߂邱�Ƃ�C���Ƃ��A3�N�]�肪�߂���1945�N8��15���A�I����}���܂��B
���̎��A���͐푈�ɕ��������Ƃ͉������������̂́A����ƌ̋��ɋA���ƈ��g���������ł��B
�������A�I�킩��킸��3�����8��18���ߑO0���A�˔@�Ƃ��Č������C�����n�܂�܂����B
���\�A�R���㗤���Ă����̂ł��B�������悤�ȑ�C�̔j�B
�s�ӂ�˂��ꂽ�U���ł������A���X�A�����J�R�̍U���ɔ����Ēz���Ă����w�n�����������߁A
����̏����͂ł��Ă��܂����B
�������́u�����Ȃ��Ɠ��{�ɋA��Ȃ��v�Ƃ��������v���ʼn��킵�A�킢��D���ɐi�߂܂������A
���{�����łɐ��E�Ɍ����Ĕs���\�����Ă������߁A�푈�𑱂��邱�Ƃ͂ł����A
�~���Ƃ������f�Ɏ���܂����B
���\�A�R�ɕ����v������A����1�����Ԑ�瓇�ɗ��ߒu����܂����B
������1945�N9��12���A���V�A�R�̑D�ɏ悹���A
�u����ł���ƋA���v�Ǝv�����̂����̊ԁA�D�͌̋��Ƃ͔��̖k�֖k�ւƐi��ōs���܂����B
�D�����������̂́A��ʐ^�����Ȑ�ɕ���ꂽ�V�x���A�ł����B
�㗤��A�R���֘A�s����A�ߍ��ȋ����J���̓��X���n�܂�܂����B

�`�����80�L�����ꂽ�R�̏�ɐ݂���ꂽ�ߗ����e���ł́A
���\�A�R����u���O�����̓\�A�̌����Ƃ���ɓ����v�Ɩ�����ꂽ�����ł��B
1�N�A �܂�1�N�ƁA�d�J�����ۂ����܂����B
���鎞�A�u���̓��H�̏��������v�Ƃ������߂��A�����܂�30�l�قǂ�
����ɘA��čs����܂������A�җ�Ȑ���ƂȂ�A�����Ƃ͑S������܂���ł����B
���߂��ꂽ�d�����ł����A���\�A�R���}���ɗ��錩���݂��Ȃ��ƍl�����ꓯ�́A
��̒���Ⴂ���֒Ⴂ���ւƈ��ɂȂ��ĕ����n�߂܂����B
�r���ŋ��R�����������ȏ����ɂ͂P�l�̂��������Z��ł��āA
����t�������̂悤�Ȃ��̂��Ă��炢�A�Q�������̂��܂����B
�����āA��������Ȃ�Ƃ��ߗ��Ǘ��������ɂ��ǂ蒅�������A
�v�������Ȃ��o������̗}�������ɕω��������炵�܂����B
�Ǘ��������Œʖ�����Ă����l�����A�Ȃ�Ɠ��{�ŕ��̂��Ƃ�m���Ă����Ƃ����̂ł��B
���̌�A���̕�����H�ו����Ă��炤�ȂǁA�l�X�ȏ������A
���̓V�x���A���烂�X�N���ւƈڑ�����邱�ƂɂȂ�܂����B
4�N�Ԃ̋��\�A�ł̐������I���A���͂悤�₭���{�ւ̋A�����ʂ������Ƃ��ł����̂ł��B

�e�r�S ���R����i40��j
�S���c�ꂩ�畷�����A�Y����Ȃ����i�ɂ��Ă��`�����܂��B
1929�N���܂�̑c��́A1945�N8��9������16�ł����B
���̓��A�c��͓����i���茧�j�̑Ί݂Ɉʒu����F�y�s�i�F�y�����j�̏��r�Ƃ����W����
�����ɏo�Ă��������ł��B
���̎��A�Ί݂��狭��ȑM�������������Ǝv���ƁA�Ԃ��Ȃ��n��k�킹��悤��
�u�ǁ`����v�Ƃ����������S�g��h�邪�����Ƃ����܂��B
����Ɠ����ɁA��͂܂�ŁA������F�̊G�̋��n�����悤�ɐF�N�₩�ɐ��܂�A
���̌��ɏƂ炳�ꂽ��̗l�q���A�c��́u�������ƂȂ��������������v�ƌ���Ă��܂����B
���̌�A���̍����Ƌ�̕ω��������ɂ����̂������ƒm�����c��́A
���̎��ڂɂ������i���A�D��ꂽ�����̌�삪�`���o�������Ƌ����̂��낤�Ɗ����������ł��B
�����āA���̏o�����������ČJ��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�����ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁA
�c�����ɋ�������ĕ������Ă���܂����B
�������̘b�����̂́A�������30�N�O�B
�c��ƈꏏ�ɂ���ہA�e���r�Ő푈�Ɋւ���b�肪�o�邽�тɁA
���g�̌o����l�X�Ȋp�x����b���Ă���܂����B
�����̘b���܂������A���`���������i�ɂ��Ă̘b���A
���ł����̐S�ɍł��[���A�N��ɏĂ��t���Ă��܂��B
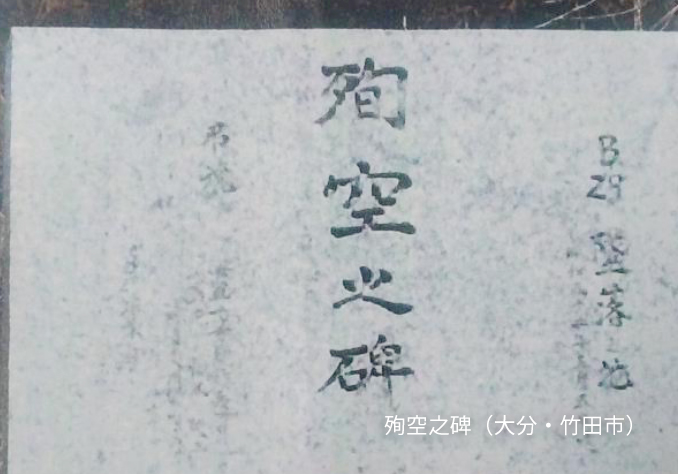
���h�s �◜����i90��j
�푈��̌������҂Ƃ��āA�ł��L���Ɏc���Ă���̂́A���h���ł̋�ł��B
1945�N�A�A�����J�R�ɂ����{�{�y�U�����n�܂�A
���h�n��ł��ْ��������X�������Ă��܂����B
�����A���͐N�w�Z�ɒʂ��T��A�h��Ď����i�{�n�j�ɋΖ����Ă��܂����B
�����Ď����Ԃ�����5��5���ߑO7�����߂��̂��Ƃł��B
���̕����甚�����������A�ዾ�ŋ��`���Ə��^�@1�@�������܂����B
�����ɖ{���Ɂu���^�@��@�A���x5000���[�g���A�G�����s���A�����琼�ɒʉ߁v
�ƕ����u�ԁA���͂ɂ͋�P�x�苿���܂����B
����ƁA�y����ϕ���ɋ�F�̗���A�˂�B29�����@��12�@���Ă��܂����B
�������̌��i�ɋ��|�������A���R�Ƃ��Ă���ƁA����̕���������{�R�퓬�@3�@������A
�������킪�n�܂����̂ł��B
���{�R�@��B29�̕ґ��ɑ��A�㉺���E����ʊ��ɍU�����d�|���܂����B
����ɑ�B29������B
���{�R�@1�@����e���A�����グ�Ȃ�����A���̂܂�B29�ɑ̓�����������̂ł��B
���̏u�ԁA���{�R�@�͉���܂ƂȂ�A�܂�ʼnԂ��U��悤�ɗ������Ă����܂����B
���̂܂ܒė�����̂��Ǝv���Ă�����A
�@�̂��牌�𐁂��o���Ȃ�����A���{�R�@��B29�ɑ̓�����������̂ł��B
���̎��A����B29�͍��x�������Ȃ��瓌�̕��֔�ы���A
���̗����P���m�F�ł��܂����B

�킸��2�����炸�̋�ł̌��ł������A�܂�Œ������Ԃ��߂����悤�Ɋ������܂����B
���̌�A���h�c�͗��������A�����J���̊m�ۂɌ������A
�������ߗ��ƂȂ�A�����̈�̂���������܂����B
���ꂩ��3�����ԁA�n��ł͋�P�x��ƃO���}���퓬�@�̊�P��
���т�����X�������܂������A8��15���ɏI����}���܂����B
���݁AB29���ė������n�ɂ́A
���m��Ǔ�����ԗ��u�}��V��v����������Ă��܂��B

�F�{�s �X����(70��)
�S���Ȃ������́A1920�N���܂�ŁA���R��U�t�c�P�R�A���̏��тƂ��āA
�t�B���s���̃l�O���X���ŏI����}���܂����B
�������A���̕���B����ƂƂ��či��Y�������n����A
�����v���Y��(����)�Ɏ��Ă���܂������A��ɉ��͂��o�����܂����B�i���ڍׂȏo�������s���j
�Ȃ�B����ƂƂȂ����̂��A���͎��ɑ��������܂���ł������A
�u�t�B���s���ł́A�R���𒅂������Ă��āA�����W�ɂ������Ă����B�v
�Ƃ����b�������Ƃ�����܂��B
�܂��A�i��Y�̔����������̎v���ɂ��ẮA
�u���������l�����Ȃ��Ă��܂����B�������������ē��{�ɋA���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B
�i��Y�̔����͎d�����Ȃ��B�v�Ƃ�����Ă��܂����B
���������v���Y���ŋL�����u�����L�v���c���Ă��܂��B
�y�ȉ��A�����L�z���قڌ����̂܂�
�i�����g�̌Y�����s���ꂽ�ۂɁA��i�Ƃ��ĉƑ��֓n�����Ƃ������́j
���̒��ʂ́A���Y�̐鍐���Ă���E�����܂ł�
�Ɩ[�������A���̓����̓��A���ɕ������̂��A���̓s�x���������̂ł���B
��Ƃ��Đ����Ȃ���Ԕ��̓Ɩ[�A�l�ʂƓV��͑傫�ȓS�̊i�q�B���̓R���N���[�g�B
�K�˂ė���l���Ȃ��A������l�����Ă��̒��ʂɌ������Ă��铙�̎p�Ɗ���
���ɕ����ׂĐÂ��ɂ��̒��ʂ�ǂ�ł��������B
�������L�͎��̃G�s�\�[�h�u�����v���Y�� �����ŏ����ꂽ���L�v�ɑ����܂��B

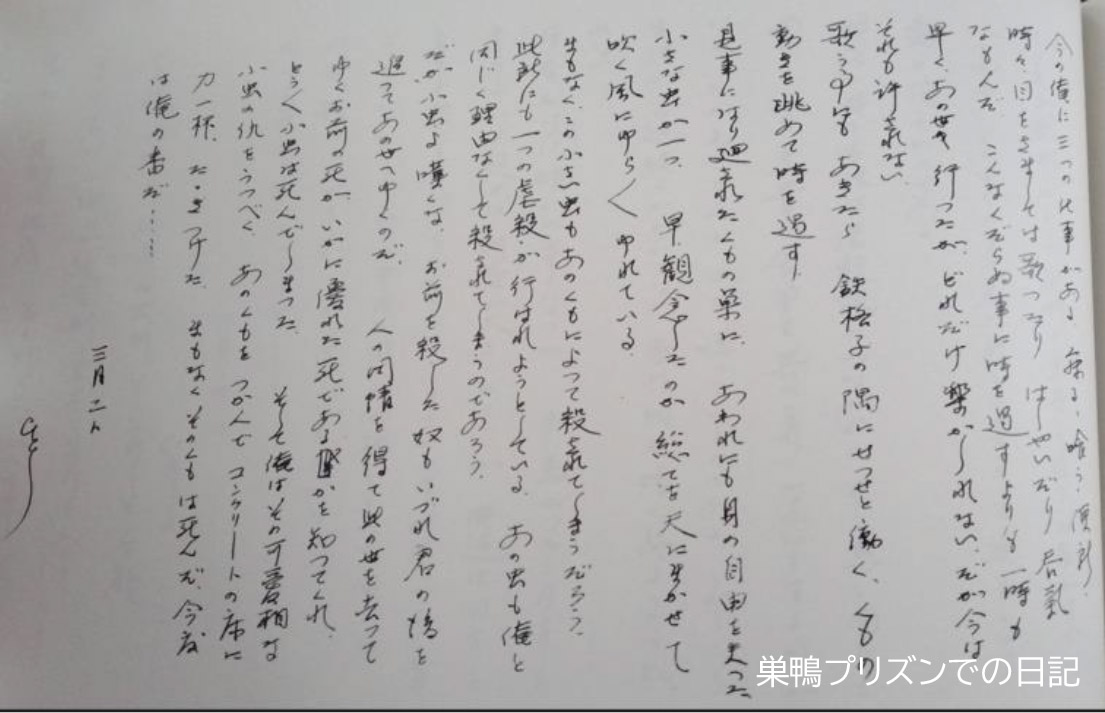
�F�{�s �X����(70��)
B����ƂƂ��āA�i��Y�̔��������Ă��ꂽ���̓��L
�y�ȉ��A�����L�z���ꕔ�����قڌ����̂܂�
�S�i�q�̋��ɂ������Ɠ����N���̓����߂Ď����߂����B
�����ɂ͂�ꂽ�N���̑��ɁA�����ɂ��g�̎��R�������������Ȓ�����B
���A�ϔO�����̂����Ă�V�ɔC���Đ������ɂ����h��Ă���B
�Ԃ��Ȃ��A���̏������������̃N���ɂ���ĎE����Ă��܂����낤�B
�����ɂ���̋s�E���s���悤�Ƃ��Ă���B
���̒������Ɠ��������R�Ȃ����āA�E����Ă��܂��̂ł��낤�B
����������Q���ȁB���O���E�������������N�̏��ǂ��Ă��̐��֍s���̂��B
�Ƃ��Ƃ������͎���ł��܂����B
�����ĉ��́A���̉������ȏ����̋w�����ׂ��A
���̃N��������ŁA�R���N���[�g�̏��ɗ͈�t�����������B
�Ԃ��Ȃ����̃N���͎��B���x�͉��̔Ԃ��E�E�E

��v��S �x����(50��)
�S0�N�قǑO�B
���w�Z�̏C�w���s�Œ��茧�ɍs�����B
���a�����ł́A�����̔�Q�ɂ���������T�����ƂɁB
�A���݂�T���ƁA�M�ŗn���Ăł������A�̌ł܂����悤�ȐՂ����銢�����������B
���v���A�푈�̔ߎS�������������u�Ԃ������悤�Ɏv���B
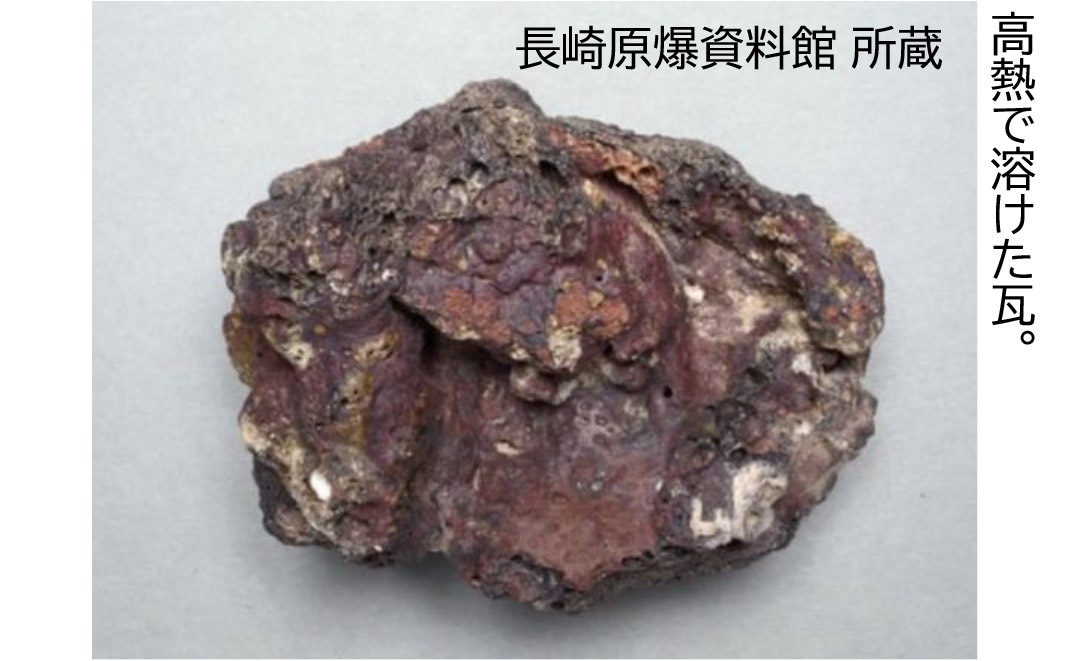

�F�{�s �Ћ˂���(80��)
�P�X�S�T�N�̌F�{���P�������������A�قږ����A���W�I����uB�Q�X���@�A
�i�����j���痈�Ă���v�ƌx������������A
�����@���߂Â��Ɓu�E�[���A�E�[���v�Ƌ�P�x���Ă����B
�h�ɓ����Ă��A�O�ł́u�h�[���v�u�h�[���v�Ɖ����苿���Ă����B
��́A�Ƃ𖾂邭���Ă���Ɣ����@�ɑ_���邽�߁u�낤�������d�v�ƌ�����A
���d�����炢�̓��Ő��������Ă����B
����ł��A�Ɩ��e��������ƁA���͖͂��邭�Ȃ�A
�������w�����������͋��|�������Ă����B
�F�{���P�ł́A����Ď����A�߂��̔R���Ă��Ȃ��Ƃɂ͋@�e���ꂽ�Ղ������������B
�x���x���P�܂ł̎��Ԃ́A�����Ă��R�O���B
�K���ɖh�ɓ������B
���ł����Q��h���T�C�����̉�����Ɠ������v�������B

���v��S �l�ۂ���(90��)
�����m�푈���͂��܂������A���͏��w���ł����B
���͂P�X�S�R�N���납�玭�����ŌR���H����c��ł��܂������A�P�X�S�T�N�ɂȂ�A
�틵���������Ă����ƁA�u�A�����J����B�ɏ㗤���ė��邩�瓦���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƁA
�Ƒ��őa�J���邱�ƂɂȂ�܂����B
�a�J��́A��B�̒��S�Ƃ������ƂŌF�{�E�u�p���ɁB
�W���P�P���̖�A�ݕ���Ԃɏ�莭�����w����F�{�w�ցB
��Ԃɂ́A�w�k�������ꂽ���w���̎p������܂����B
�r���A�A�����J�R�̔�s�@�����P���邽�тɁA�u������v�Ƃ̊|�����ŁA��Ԃ��~�܂�
���̉��֓�������ł����̂��o���Ă��܂��B�{���ɋ��낵�������B
�����炪��F�{�w�ɒ����ƁA��������u�p���Ɍ������F���S���̎n���w
��F�{�w��ڎw���܂����B
�����A���̓��͌F�{���P�̒���ŁA�����͔R�������ꐅ�����j��A������
�|�^�|�^�Ɨ����鐅�����݂Ȃ���A�K���ɒ킽���̎�������ē�F�{�w�܂ŕ����܂����B
�u�p���ɂ����̂͂P�S���̖�B�����A�߂��̒×���ŁA�����܂݂�̊�Ƒ̂�܂����B
�����Č}�����I��B
�푈���I��������Ƃ�m���Ĉ�ԂɊ������̂́u���������Ȃ��Ă����B�B��Ȃ��Ă����v
�Ƃ������Ƃł����B

�F�{�s �O�c����(40��)
�����ɏo���������Ƃ�����c��(1919�N���܂�)�́A�c�����̎��̖����ŁA
�����m�푈�����̘b�����Ă���邱�Ƃ�����܂����B
�Ȃ��ł����ɋ�����ۂɎc���Ă���̂́A��n�ŏo����������l�̌ǎ����������A
�]�R���ɖʓ|���݂Ă����Ƃ����b�ł��B
�H���͂������ړ��̍ۂ͎q�ǂ����R�n�ɏ悹�A���g�͂ł��邾���k���ōs�R������
�������L��������܂��B
�����̐�F�������Ȃ�����A�h�����Đ����Ȃ��炦�I����}���������ł��B
���g���̍ہA���̏��N�͑c���ɑ��A�u���{�Ɉꏏ�ɂ�Ă����Ăق����v��
�����č��肵�������ł��B
���40�`50�N�قnjo�߂�������c���́u���̏��N�͂ǂ����Ă��邾�낤���A
�����Ă�����������炢���낤�A�����̂Ȃ������B�v�Ƙb�����Ƃ�����܂����B
���̓����A���͂��������b�ɕ����������ł������A���d�˂����܁A���߂đc���̘b��
�v���o�����Ƃ������Ȃ��Ă���̂́A�푈��������̂������Ȃ�����ƂȂ��Ă��邩��
�ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B
�u�푈�����͐�ɂ����炢����v�Ƃ����N�ɂƂ��Ȃ�������c���̌��t���A
���x�������ŕ����܂����B

�F�{�s ���i����(80��)
���͎����Q�̎��A�o����̑�p�ŖS���Ȃ��������ł��B
�P�X�S�T�N�P���X���̂��Ƃ������������ƕ����Ă��܂��B
���ꂩ��W�O�N�B
�����o���������A���͐���U�����B
���͕��̊���A�����A���̂ʂ������������Ȃ����A��x�͕����S���Ȃ����ꏊ��K��A
�Ǔ��������Ǝv�������A���̎v��������Ɗ����܂����B
���N�P���A�o�Ƌ��ɑ�p�E���Y��K�ꂽ�̂ł��B
���̕����͑�96����������B
�����ɂ��ƍ��Y���R�U�L���̒n�_�ŁA��U�����A���v�����悤�ł��B
�����̐�F�Ƌ��ɊC�̒�ɒ����B
�₽���C�ɒ��݁A�⍜�A��i��������ꂸ�A���O�������Ǝv���܂��B
���̎�����W�O�N�B
�R�U�L����ɕ�������Ǝv���Ƃ��ꂵ�������B
���̑̌����A�q�⑷�ɓ`���A�Ⴂ����Ɉ����p�����Ƃ��������̐Ӗ����Ǝv���Ă��܂��B
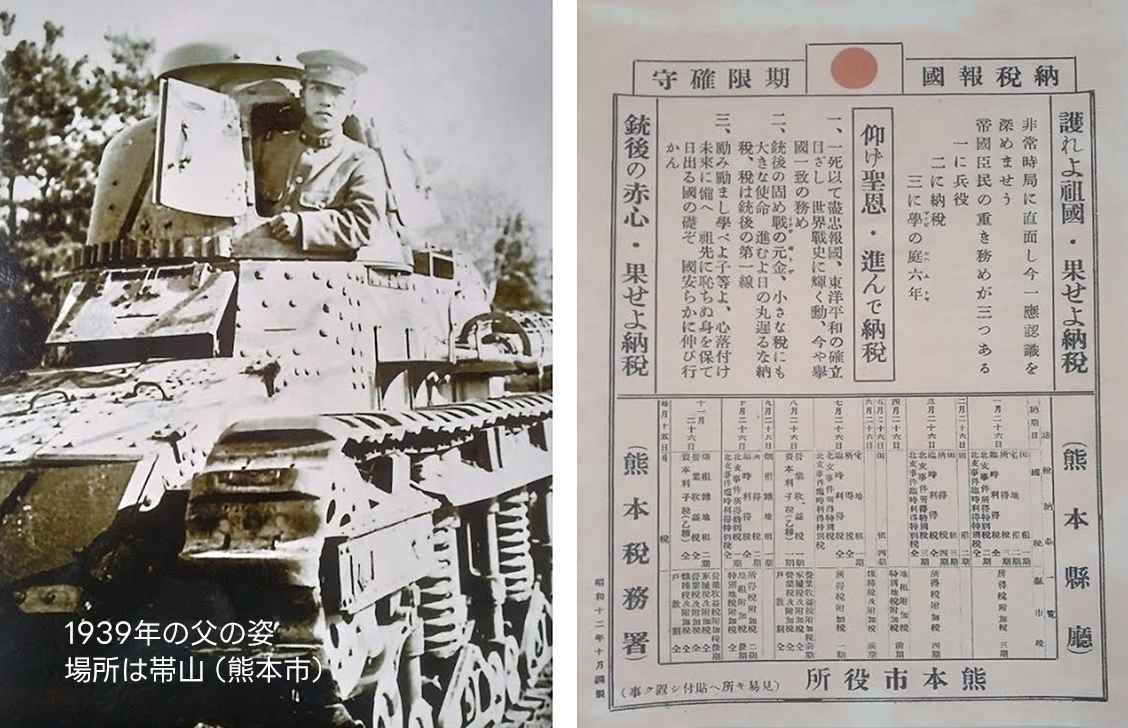
�F�{�s �b�コ��(80��)
�P�X�S�T�N�B�����Q�̍��̋L���ł��B
��s�@�̉���������A�h�֓�����B
������J��Ԃ��Ă��܂����B
�h�܂ł́A�Ƃ�������Ė�T���B
��Ɏ��������čs���Ă��܂����B
���ł����m�Ɋo���Ă���̂́A�O���}���퓬�@�Ǝv�����s�@�̉��ł��B
���̏��^�@�����b�������������ƋL�����Ă��܂��B
�h�̒��ł́A�ꂪ���Ă��ꏡ�r�ɓ���āA�|�ł��āA
���Ă��Ă������Ƃ��o���Ă��܂��B
�����Q�ł������A�N���ɋL�����c���Ă��܂��B
�܂��A����ł́A��ɂȂ�Ƌ�P�̖ڕW�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂƁA
�d���̊}�̕����ɍ����z��킹�A�����O�ɂ���Ȃ��悤�ɂ��Ă������Ƃ��o���Ă��܂��B
�I���A������������g���Ă���������́A�푈�̘b�����Ƃ͂���܂���ł����B
���炭�A��n�ł͂��낢��Ȃ��Ƃ�����A�b�������Ȃ������̂��낤�Ǝv���܂��B
�Ō�ɁA�����푈��(1937�N)�ɌF�{���ƌF�{�s�̖��O��
�z�z���ꂽ�Ƃ݂��鎑�������܂��B
B�T�T�C�Y�قǂ̎��ɂ͌��o���Ɂu�[�ŕv�u�����m��v��
������Ă��āA���͂̒��ɂ́A
�鍑�b���̏d�����߂��R����B
��ɕ���
��ɔ[��
�O�Ɋw�т̒�Z�N
�����āu�e��̐ԐS�v�Ƃ��L����Ă��܂��B

�F��s �{�c����(90��)
����L����Ɍf��
���A���{�̑����̎�҂��������ꂽ�ٍ��̒n�ʼnߍ��ȉ^����w�����܂����B
�������̈�l�ł��B
��� ���̓V�x���A�ɗ}������A�Ɋ��̒n�ʼnߍ��ȘJ�����������A
�Q���⊦���Ɠ����܂����B
���̉ߍ�������A�����̒��Ԃ��������̐�������܂����B
����ŁA�l�̉������ɂ��G��܂����B
�Ď��̂Ȃ��_��ŁA�n���̐l��������H�����Ă��炢�܂����B
����́A�Ɍ��̏ł��l�Ɛl�����������邱�Ƃ������Ă���܂����B
�� ���́A�ꍑ ���{�ɋA�邱�ƂȂ��A�V�x���A�̒n�ŖS���Ȃ���
��F�����̖��O���~�߁A�ނ�̐��𖢗��ւȂ����Ƃ�������Ӗ��ƂȂ��Ă��܂��B
�V�x���A�}���̗��j�́A�푈�������炵�������ł��B
������A�����������p���ł����ׂ����Ǝv���Ă��܂��B
�����`�������̂́A�u�푈���D�������̂̑傫���v��
�u�ǂ̂悤�ȏł��l�̉������͎����Ȃ��v���ƁA
�����āu��x�Ɣߌ����J��Ԃ��Ȃ��悤�ɁA���a�����v�Ƃ������Ƃł��B

�F�{�s ���삳��(70��)
�������e���畷�����b�ł��B
�P�X�Q�U�N���܂�̕��́A�P�W���납�璆���E���֍s���A
�R�������H��œ����Ă��܂����B
���̎��A���W�ߏ�ƂȂ�u�Ԏ��v�����ɓ͂��܂������A
���͍H��Ő����̎w���ғI���ꂾ�������Ƃ��e�������̂��A
�ŏI�I�ɂ͓������Ə��i�P�\�j���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
���������\�肾���������́A���V�x���A�ɘA��Ă����ꂽ�ƕ����܂����B
���̎��A�����������V�x���A�ɍs���Ă�����A���͓��{�ɋA�邱�Ƃ��ł����A
�������Z�������̐��ɐ��܂�Ă��Ȃ�������������Ȃ��Ǝv�����Ƃ�����܂��B
����A��͎O�p���Ő��܂�炿�܂����B
�펞���́A��P�̓x�ɖh�ɓ�������ł��܂������A���Ă���ہA
�퓬�@���甭�˂��ꂽ�@�֏e�̒e���h�̔����ђʂ��A
���̋߂��ɂ������l���S���Ȃ����Ƙb���Ă��܂����B
���̂悤�ɁA�����̕��̋]���������ē��{�͕�������W���A
���̕��a�Ȑ������ł��Ă���Ǝv���Ă��܂��B

�F�{�s ���{����(�X0��)
�P�X�R�Q�N���܂�̎��́A�P�Q�`�P�R�̎��ɋ�P���o�����܂����B
�F�{�s�ւ̋�P�͂P�X�S�S�N�㔼����P�X�S�T�N�ɂ����ĕp�����A���̓O���}���퓬�@�A
���B�Q�X�Ƃ�������ł��B
�A�����J�R�@������͐�������Ȃ����炢�̕p�x�ł����B
�����A���w���ƂȂ������́A�w�Z�̎w���̂��ƌF�{�s���S���ɂ������Z�ɂɂ͒ʂ킸�A
����̂����K��������ĂR�O���قǂ̓c���ŃR���┞���͔|���邱�Ƃ�
�]�����Ă��܂����B
���̍ہA��P�x���͂ɖ苿���ƁA�߂��𗬂��ΐ�ɂ����鋴�̉���
��������ł��܂����B
�퓬�@�͎��������瑀�c�m�̊炪�����邭�炢�܂ō~�����Ă��āA
�u�_�b�_�b�_�b�_�b�c�v�Ƌ@�e�|�˂��Ă��Ă��܂����B
���Ɨׂ荇�킹�̏������Ă��܂������A��������P�ŁA
�Ȃ����|���Ƃ������o�͖����Ȃ��Ă��āu�܂��������v�Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂����B
�܂��A��̋�P�ł̓A�����J�R�@����̏ォ�猚���ɖ��̂悤�Ȃ��̂��܂�����ŁA
�����Ă��܂����B
���̂悤�Ȃ��̂̉e���Ȃ̂��A�������Ƃ͈�u�ɂ��ĉ��ɕ�܂�Ă��܂����B
�����́A��P����g����邽�߁A���ւ̃h�A��ȂǂɃJ�M�������邱�Ƃ͂Ȃ��A
�钆�ł������ɉƂ��яo���āA�h�ɓ������߂�悤�ɂ��Ă������Ƃ�
���ł��o���Ă��܂��B
�푈���o�����č�������̂�
�u�푈�ň�Ԃ��킢�����Ȃ̂́A��ʎs���ł���B�v
���̂��Ƃł��B

�F�{�s �R������i�U�O��j
����L����Ɍf��
�����P�T�̖S���ꂪ����Ă��ꂽ�A�P�X�S�T�N�W���P�O���̌F�{���P�̘b�ł��B
���̓��A��ƗF�l�͂Q�l�Ŋw�Z�i�F�{�s�j�̉^����̓��ő��������Ă��܂����B
���̎��A�ˑR ��̕�����Ⴂ���Łu�u�[���v�Ƃ�����s�@�̉����������Ă������Ǝv���ƁA
����Ɠ����Ɂu��P�x��I�v�Ƌ��Ԑ����������܂����B
�����A��ƗF�l�͓ˑR�̏o�����ɁA�ǂ��֓���������̂������炸�A
���̏�ɗ����s�����Ă��܂��܂����B
����Ƃ��̎p���������m�̈�l�ɁA
�u�����A���������B�������ɗ����B�����ɓ���B�v�ƁA
�R�p�ɐ������ꂽ�h�ɓ���Ă��炢�A�����~��ꂽ�����ł��B
���炭���āA�h����o��Ə��w�Z�̍Z�ɂ͂��̂��������ɕ�܂�Ă��āA
���̎��A�h�ɓ������߂Ȃ������疽�͂Ȃ��������낤��
�����̂��Ƃ�����Ă��܂����B
�܂��A���̋�P�ł́A
��̂�����l�̗F�l���s��Ȍo�������Ă��������ł��B
���̗F�l�̕��́A��P���瓦��悤�ƁA�c�����Q�l��A���
����̖h�ւƋ}���ł��܂����B
�R�l�̌�납��́A�퓬�@���o���o���o���Ƌ@�e�|�˂��Ȃ���
���̂����������ŋ߂Â��Ă����Ƃ����܂��B
�F�l�́A�E��ƍ��肻�ꂼ��ɖ��̎�����肵�߁A
�Q�l����������Ȃ��疳�䖲���ő����Ă��܂����B
�퓬�@�́A�傫�ȉ������ĂȂ��瓪����z���Ă����܂��B
���̎��A�n�b�ƋC�Â��ƁA�Q�l�̖��������Ă���͂��̕Е��̎肾����
�y���Ȃ��Ă���̂ɋC�Â��������ł��B
�Q�ĂĐU������ƁA�P�l�̖��̕Иr�����������đ����Ă����̂ł��B
���͈ꖽ����藯�߂����̂́A�Иr�������܂����B
�F�{���P����W�O�N�B
���ꂪ�A���ۂɐg�߂ł������푈�̘b�ł��B

�F�{�s �ēc����i�U�O��j
�Q�O�P�U�N�A�F�{�n�k�Œz��P�R�O�N�̎���͑�K�͔���B
�ǂȂǂɑ傫�Ȕ�Q���o�܂����B
���̕Еt���̍ۂɌ������A�Q�K�̗������яo�������̕��́B
��ɁA�F�{���P�Ő퓬�@����@�e�|�˂��ꂽ�ۂ̋@�e�e��
���ɂ߂荞���̂��ƕ�����܂����B
���ɂ��n�k�Ŕ�Q�����ޖ������Ă݂�ƁA
���̒����瓯���悤�ȋ@�e�e���o�Ă��܂����B
�F�{�n�k�̌�ɖS���Ȃ������́A�F�{���P�̎��P�O�B
��P�́u�{���ɕ|�������B�v�Ƙb���A
���A����̒���@�肩��������A�@�e�e����������o�Ă����Ƃ������Ă��܂����B
�����A�������P�̏ڂ����b�����Ƃ͂���܂���ł����B
���A�l����ƕ��ɂƂ��Đ푈�͖Y�ꂽ���L���������̂�������܂���B
���W�O�N�B
���߂čޖɎc���Ă����e�������Ă݂�ƁA���̏d����
�u���̂悤�Ȓe���A�l�Ԃɓ������Ă�����A�ЂƂ��܂���Ȃ������Ǝv���܂��B
�����{���ɕ|���������낤�B�v�Ɗ����Ă��܂��B


�F�{�s �j���i�Q�O��j
����ɏZ�ޑc��(90) �͂P�O�̎��ɒ���s�Ŕ픚���܂����B
�c��͖��N�A�������������ꂽ�W���X���̕��a�F�O���T�����邽�тɁA
�܂𗬂��Ă��܂������A�c��̌�����푈�̘b�����Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���ł����B
�������A�P�O�N�O �������Z���̎��ł��B
�n���V���Ђ���Â����u�픚�̌���`�����v�ŁA�c�ꂪ�����̌o����������̂ł��B
�Ȃ�������̂��B
�c��́u�푈���o�����Ă���l�������Ă��Ă���B
������Ɛ푈�̌�����`���Ă��������B�v�Ƃ��̎v����b���Ă���܂����B
���̎��ɕ��������e���A�`�������Ǝv���܂��B
�P�X�S�T�N�W���X���ߑO�P�P�������B
�����P�O�������c��́A���S�n�����P�O�L�����ꂽ�ꏊ�ɏZ��ł��������ł��B
�c��́A���e�̑���ɂR�̖��̖ʓ|���݂Ȃ���A�ق��̎q�ǂ������ƈꏏ��
�V��ł������������Ƃ����܂��B
�s�J�b�Ƃ����M���Ɠ����ɂ��̂��������ɏP���A�����Ă��������ƁA
��������ꂽ�����ł��B
�C���t���Ƒc��̘r�͉Ώ������悤�ɔM���Ȃ�A���͉����ɂԂ����̂��A
�����猌�𗬂��Ă����Ƃ����܂��B
����ɁA��������Ɛ�����n���Ă����^���Ԃɐ��܂�A
�n�������ƌ����炯�̐l��A�Ώ������l������
���낼��ƕ����Ă����̂��������Ƃ����܂��B
�픚�����l��������́u�������܂��Ă��������v�Ƃ̐���������A
���͂̐l���A�߂��̈�˂��琅�����݁A�����Ă����l������
�������܂�����A�̂ɂ������肵�Ă��������ł��B
�Q����A���S�n�̋߂��ɘA����čs���ƁA�����ɂ͋��낵�����i��
�L�����Ă��܂����B
���ɂ͉����オ��A���S�̂����������Ԃ��Ă���ŁA
�l�⋍��n���A���������ɓ|�ꂽ�܂܂������Ƃ����܂��B
���������̌��ǂɋꂵ�߂���c�ꂪ�J��Ԃ����t�B
����́u�푈���Q�x�Ƃ��Ă͂������v�Ƃ������Ƃł��B

�F�{�s �R������i�U�O��j
����L����Ɍf��
�P�X�R�O�N���܂�̖S����ɂR�O�N�قǑO�ɕ������b�ł��B
�펞���Ŏv���o�����Ƃ͂ƕ����Ɓu�Ƃɂ����Ђ����������B�v�ƌ����Ă��܂����B
�H�Ɠ�̎���A�H���͑卪��J�{�`���̎G�����قƂ�ǂŁA�Ƃɂ��������������ł��B
�u�������сv������܂������A��������ɂ��ї��������������Ă��邮�炢��������
�����܂��B
���x���A�߂��̓c��ڂœc�A���̎�`���������Ƃ��ɁA
�_�Ƃ̕��������������Ă����̂��ɂ��肪�A�ƂĂ��������������Ƙb���Ă��܂����B
�����A�����w�Z(�F�{�s)�̉^����́A���ɂ���A
�Z�ɂ͗��R�̕����h�ɂƂ��Ďg���Ă������Ƃ���A
�q�ǂ������͋߂��̐_�Ђ⎛�ɕ�����ĕ����Ă��������ł��B
�����A�㋉��(���݂̒��w��)�͑�����Ƃ�A�|���P���Ȃǂ�
�قƂ�Ǖ��炵�����͂ł��Ȃ������ƁA������U��Ԃ��Ă������Ƃ�
�L���Ɏc���Ă��܂��B

�F�{�s �n�ӂ���i�V�O��j
���̉Ƒ��ʐ^�Ɏʂ�j�����A�P�X�S�Q�N�����A
�����Y�C�R�q����i���j�ɏ������Ă����`���i�����Q�U�j�ł��B
�`��(����24)�ɕ������Ă���̂��A���̕v(�����T����)�ł��B
���̎ʐ^���`��ɓ͂��āA��P������̂T���P�X���B
�`���͉Ƒ��Ɉ��Ď��̂悤�Ȏ莆���L���Ă��܂����B
�u�����Ď��̂��Ƃ͐S�z����ȁB���Ă͉^���B���^�͋����A���S���ċ��Č���B�v
�u�{�����ɑO�i����B�v�i�����̂܂܁j
���̌�A�`���̓p�C���b�g�Ƃ��čq���́u�v�ɓ��悵�A
�~�b�h�E�F�[���������܂����B
�������A�U���T���A�`�������u�v�̓A�����J�R�̍U�������v�B
�A��ʐl�ƂȂ�܂����B
���̔N�̂P�P���A�����ۂŎ���s��ꂽ�u�����C�R���v
�Q���`�ꂪ�܂𗬂��Ɓu�R�l�̍Ȃ͗܂𗬂��ȁB�v�Ǝ��ӂ��ꂽ�����ł��B
��Ȑl�̎��𓉂ނ��Ƃ��ł��Ȃ�������������`��́A
�����u�푈�͉Ƒ���D���B�v�Ƙb���Ă��܂����B
����ȋ`�ꂪ�A�̂Ă���Ȃ������̂��`���̊C�R���X�ł��B
�������Đ������Ŏ������`�����A�����ł������Ă����������̂��Ǝv���܂��B
�܂��A�`���̈⍜���߂��Ă��Ȃ��������Ƃ���A
�`��́u�܂��C�̂ǂ����Ɏ�l�̑̂�����B�v�ƌ��A
�u�C������Ɣ߂����Ȃ�B�v�ƌ��Ȃ̂悤�ɘb���Ă������Ƃ�������ۂɎc���Ă��܂��B


�ʖ��s �X����i�W�O��j
1945�N�W���̋L���ł��B
�R�Δ����������́A�V��(�F�{�s)�������F�V�H���ɏZ��ł��āA
���̓��͂Q�K�łR�Ώ�̌Z�ƈꏏ�ɗV��ł��܂����B
���̎��ł��B
��P�x��̃T�C�������苿�������Ǝv���ƁA
����������ɂ���h�ɔ���Ԃ��Ȃ��A
��u�o�b�o�b�o�b�v�Ƌ@�e�|�˂��n�܂�܂����B
�U�����Ă����̂́A�����炭B�Q�X�̌�q�@���@�������Ǝv���܂��B
�����Z�ɕ������߂��Đg�������ł��Ȃ���Ԃł���ƁA
�@�֏e�̒e���Ƃ̑��K���X���ђʂ��A
�������Z�킪�����ꏊ�����P���[�g�����ꂽ�ꏊ�ɂ���
�^���X�Q��(����)��ł��������̂�������܂����B
���̌�A�߂��̊w�Z(���F���R���w�Z)���������A
�R���オ�錚���𑋂�����o���Č��Ă��܂����B
���̓��̂��Ƃ́A���܂�̋��|�ɍ��ł��L���ɑN���Ɏc���Ă��܂��B
�����푈�����g���Ă����u�h�Ёv�Ƌ��ɁA
���������Ă����u��l�j�v���푈�̋L���Ƃ��ĕK�v�Ǝv���A�����ۊǂ��Ă��܂��B
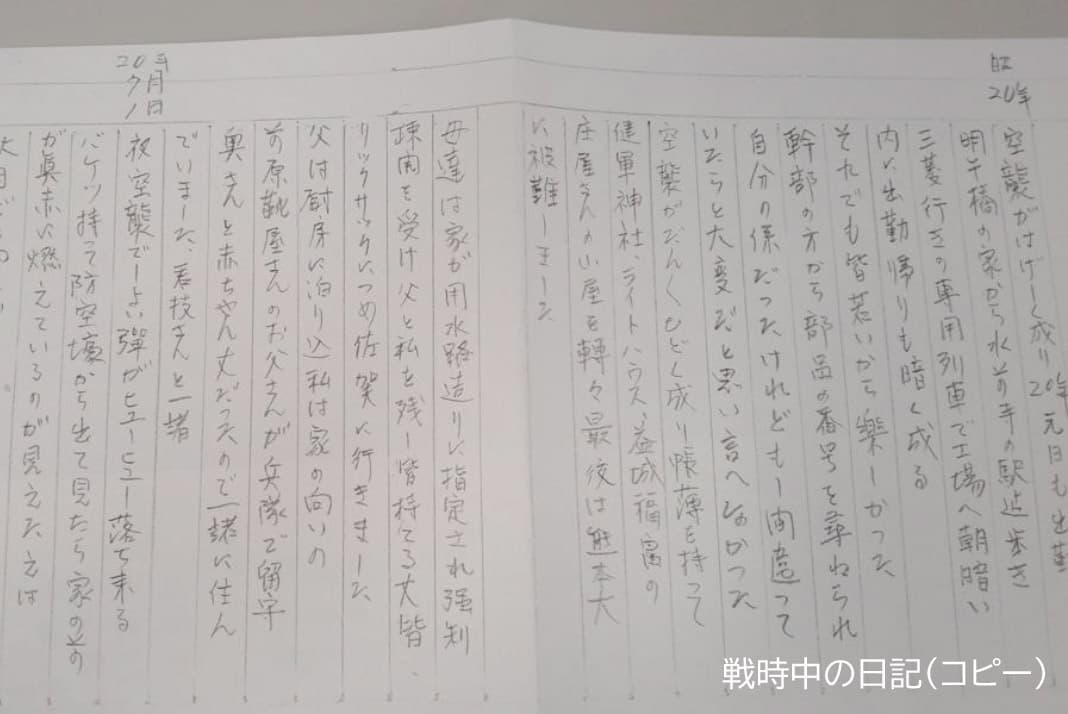
��v��S ����(70��)
��Q�N�O�ɂX�U�ŖS���Ȃ����ꂪ�A�F�{���P�̏��������߂Ă��܂����̂ŁA
�����肵�܂��B
�y�ȉ��A����l�̓��L�z���ꕔ�� �قڌ����̂܂�
�P�X�S�T�N�A��P���������Ȃ�A���������R�n��i�F�{�s�j�̎O�H�d�H�Ƃ֏o�B
���Â���������o���A�A����Â��Ȃ��Ă������A����ł��F�Ⴂ����y���������B
�����̕����畔�i�ԍ���q�˂��A�����̒S�����������ǁA�Ԉ���Ă������ς��Ǝv��
�����Ȃ������B
��P������Ђǂ��Ȃ�A����������Ĕ��܂����B
�V���P���A��A��P�Œe���q���[�q���[�Ɨ����Ă���B
�o�P�c�������Ėh����o�Ă݂���A�Ƃ̑O���^���ԂɔR���Ă���̂����������́A
�_�����Ǝv���B���̂܂܂S�l�œ����܂����B
�K���ɑ���A�G�@�̋@�e������A�c��ڂɔ����������B
�Ԃ���������Ԃ��Ă��������A���̉��̓c��ڂ̐����܂�ɗ������̂ŁA
�������ɂ���āA�����グ�܂����B
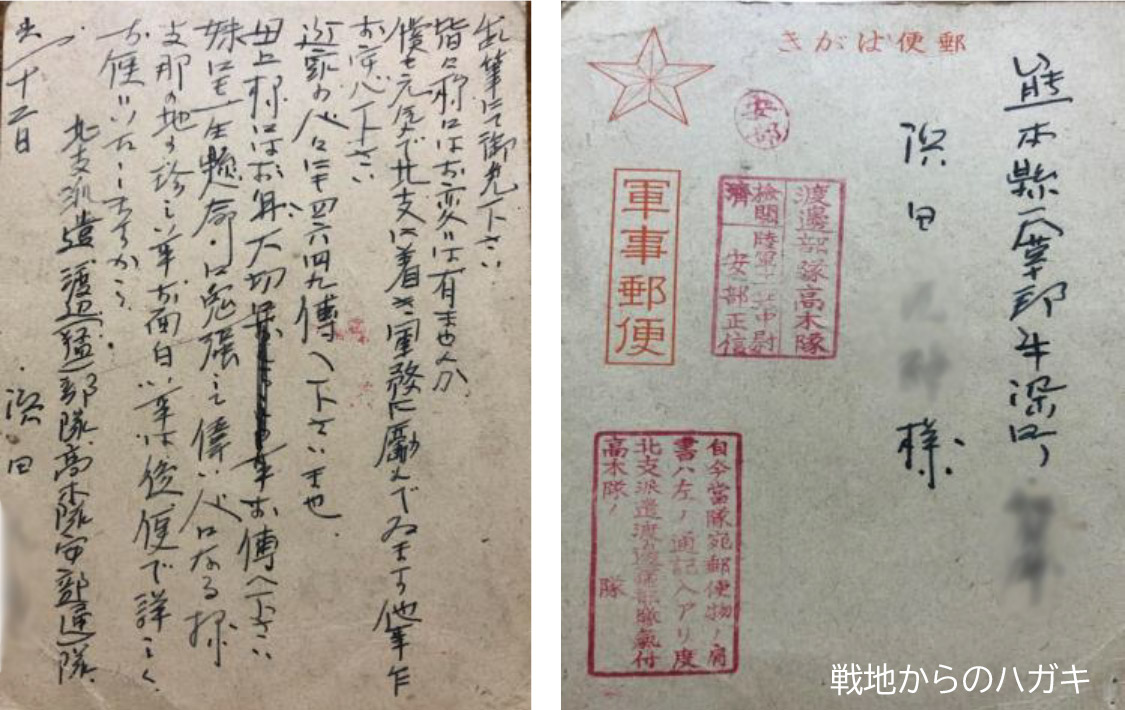
�F�{�s ���삳��(50��)
��S�N�O�A���e�����E���A���d�����Ă����ۂɏo�Ă����n�K�L�ł��B
�c���̒�i�����P�X���Q�O�j�������푈�̂����A��n���畃�e���Ăɑ��������̂ł��B
�n�K�L��ǂƂ��́A�����M���Ȃ�܂����B
���̎莆�����S�N��A�c���̒�͕a�������S���Ȃ�܂����B
�y�ȉ��A�n�K�L�L�ڂ̓��e�z���قڌ����̂܂�
���M�ɂČ�Ƃ��������B
�F���܂ɂ͂��ς�肠��܂��B
�l�����C�ŁA����(�k�x)�ɒ����A�R���ɗ��ł��܂��B
�����S���������B
�ߏ��̕��X�ɂ���낵���i�l�Z�l��j���`�����������B
���l�ɂ́A���g�̑�ɂƂ��`�����������B
���ɂ��A�ꐶ�����ɕ����āA�̂��l�ɂȂ�悤�ɁB
����(�x��)�̒n�̒��������ƁB�ʔ������Ƃ́A��̕ւ�ŏڂ������`���������܂��B

��v��S �x����(50��)
40�N�قǑO�B
���w�Z�̏C�w���s�Œ��茧�ɍs�����B
���a�����ł́A�����̔�Q�ɂ���������T�����ƂɁB
�A���݂�T���ƁA�M�ŗn���Ăł������A�̌ł܂����悤�ȐՂ����銢�����������B
���v���A�푈�̔ߎS�������������u�Ԃ������悤�Ɏv���B
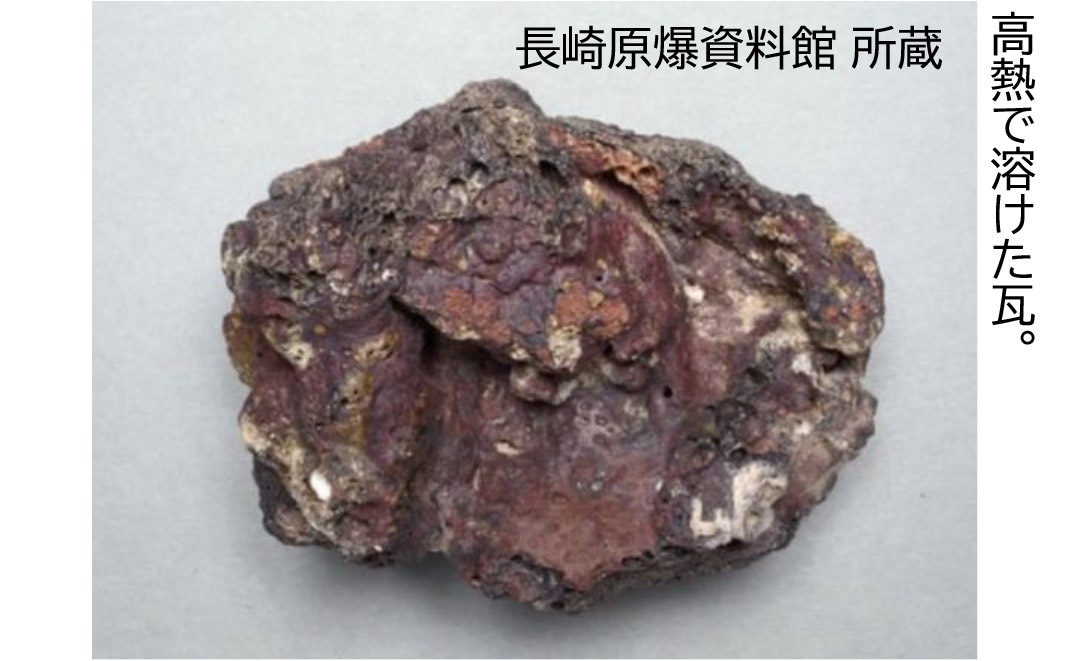

�e�r�s ��������(60��)
�`��̎��Ƃɕۊǂ���Ă����푈�̎����ł��B
�����푈�ő�p�ɔh�����ꂽ�`���B
�A�҂����ۂɌ�t���ꂽ�ł��낤�x�ߎ��ύs�� �������ɍ��B
�i���{���������B�̂��߂ɔ��s�������j
���a15�N(1940�N)���s�ƋL����Ă���B
�A�Ҍ�̋`���̐����͌����������ƕ����Ă��邪�A
1�����g���Ă��Ȃ������B
�`���͐푈�ɂ��āA��������̎v�����������̂�������Ȃ��B
�܂��A���������Ă������ɏo�Ă���
�����R�品����s��i�����j�ŏf�����B�e���ꂽ�Ƃ݂���ʐ^�B
�����ɂ́u��������@�@�v��u�����v�Ə����ꂽ��s�@���f���Ă����B

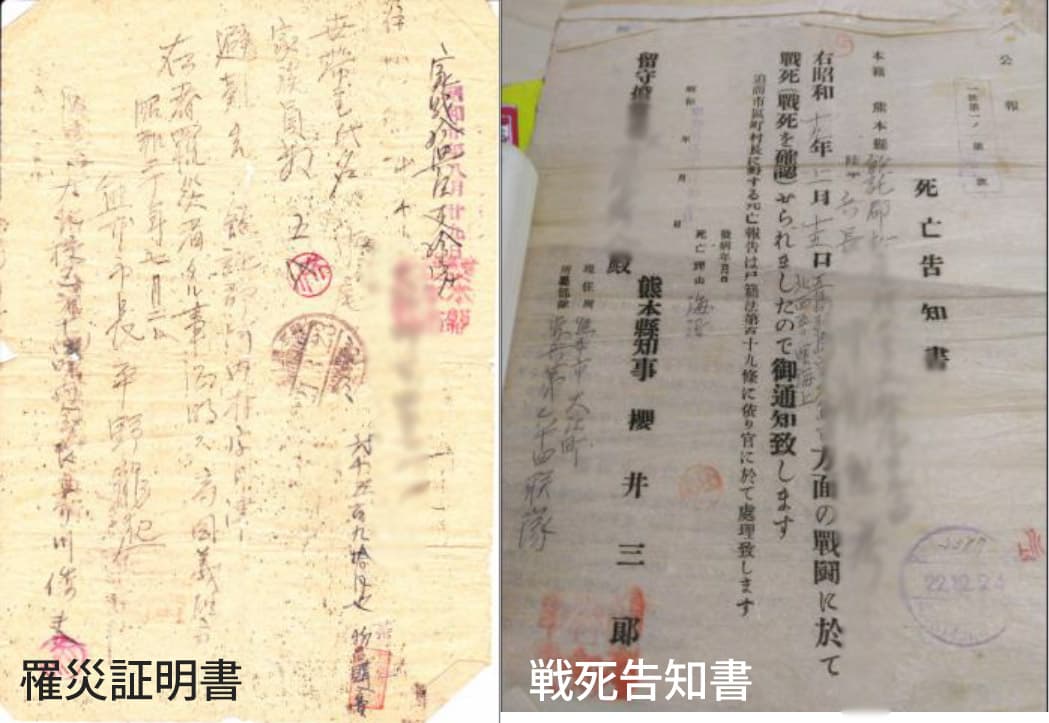
�F�{�s ��������(50��)
�c���́A�����t�Ƃ��Ċ��Ă��܂������A�푈�ŊC�R�ɒ�������A
�C�h�͂ɏ���Ă����悤�ł��B
�킸���Ȑ푈�̋L����������܂��A�����Ƃ��Ďc���Ă�����Ǝv���A�����܂����B
��́A�P�X�S�T�N�F�{���P���̋�P�ɂ���Q���ؖ�����u��Џؖ����v�B
�c��̖��O�����ю�ɂ���܂����B
������́A�c���̒�́u�펀���m���v�펀�������Ƃ�������Ƒ��֓`�������́B
�c������푈�̘b�͕��������Ƃ��Ȃ����A�c���̈�i�Ƃ��ĕۊǂ��Ă��܂����B

�F�{�s ����(90��)
�P�X�S�T�N�V���P���̌F�{���P�ł́A�t�͊w�Z(�F�{�s)�̗��ɂ��܂����B
�u�q���[�b�v�Ƃ��������āA������w�Z�i�F�{�s�j�ɏĈΒe��������̂�
�����܂����B
���͏��Δǂ������̂ŁA�唪�Ԃɏ悹�����ΐݔ����W�l������ňړ���������
������܂����B���̍ہA�����̍b��唪�ԂɂЂ���A�Վ��̋~�쎺�ɘA��Ă�����܂����B
���̌�́A�ߏ��̐l�����A�J�[�Ō}���ɗ��Ă���ƂɋA�������Ƃ��o���Ă��܂��B

�F�{�s �{�c����(80��)
���̐푈�̋L���ł��B
�I��O�̎����S�̂���A(�P�X�S�T�N)
�ԉ��R(�F�{�s)���z���ē�̕����甚���@�����Ă����B
��P�x��Ƌ��ɁA���͕ꂩ��h�ɕ��荞�܂ꂽ�B
�h�̒�����O�����Ă���ƁA
�����@���ĈΒe�𗎂Ƃ��̂��������B
�܂�ʼnԉ̂悤�ɂ��낢��ȐF������Ă����̂���ې[���L���Ɏc���Ă���B
�ĈΒe�́A�ŏ� �c��ڂɗ����A�����Ď��̉Ƃ���
��Q�O�O���[�g�����ꂽ�w�Z�ɗ����A�Z�ɂ��R���オ�����B
�h����O�ɏo��ƁA�Ύ��̉e���������̂��A�Ƃɂ����M�������B
����ŁA������U��Ԃ�Ɓu�|���v�Ƃ������o����
�����@�̔�����A�������̗����鉹���Ƃɂ��������������Ƃ��o���Ă���B

�F�{�s ����(80��)�`��
�����U�B
���̌F�{�s������؈�Ōo��������P�B
�h�ɓ����悤�Ƃ������A�u�h���̂��R���Ă���v�ƌ����c�����܂ǂ����B
�l�̎p����猩����Ƒ_����Ǝv���A�p���B�����߂ɁA�T�g�C�����̑傫�ȗt�̉���
�������ނƁA�����ɂ͂��łɂQ�O�l�قǂ̐l���g���Ă����B
����ɁA�߂��̏���ɂ͏ĈΒe�̖������o���A���̖��ɉ��������̂��A
�u�삪�R���Ă����v���̌��i�͍��ł��o���Ă���B

�F�{�s ���{����(60��)
��P�̎��A�u�O���}���퓬�@�̑��c�m�����Ȃ��猂���Ă���̂��������v
���̘b��ꂩ�畷�������A�q�ǂ��S�Ɂw�푈�͐l��ς���x�Ǝv���܂����B
�퓬�@�̑��c�m���A�N���̎q�ǂ��ŁA�N���̕��e��������Ȃ��Ǝv��������ł��B

�F�{�s ����(80��)
�F�{���P�̂��̓��A���͂S�ɂȂ�������ł����B
�F�{�s�̔���̓y��ɂ�������̐l����̕��ɑ��������ĐQ������Ă��܂����B
���̎��A�ˑR�Â��Ȃ�A��s�@(B29)���X�b�[�ƁA�Â��Ɉړ����Ă��܂����B
�����āA���Y�̂悤�ȍ��������U�@�[�b�Ƃ����������ĂĐ�ʂɗ����āA
��͖��𗬂����悤�ɂʂ߂��ƂȂ�A���̏u�ԁA���������Ɖ�����ʂ𑖂�܂����B
����̑Ί݂͉̊C�B
���̒��ɂS�`�R�K���Ẵr���̒����Β��ɂȂ��ĔR���������Ă��܂����B
�W�R�̍��ɂȂ��Ă��A���̒��ɂ��邱�̉f������������Əo�Ă��܂��B
�S�̎q�ǂ��ɋ��낵���Ƃ����C�����͖����B
���������A�������̉f���͓��̒��ɏo�Ă��Ă��܂��܂��B
�E�N���C�i�̎q�������̐S�̏��͌v��m��܂���B

�F�{�s �]������(70��)
�P�X�T�O�N���܂�̎��ɂ͐푈�̎��̌��͂���܂���B
�����A�푈�̏��Ղ͑̌����Ă��܂��B
�������������w�R�l���V�s�X(�F�{�s)�̓�����ŁA������Ă����S����p�B
�߂����A�R�[�f�B�I���̉��F���Y����܂���B
�Ƒ���{�����ߎd���Ȃ�����̎p�����炵�Ă����Ƃ킩�����͍̂ŋ߂̂��Ƃł��B
����A�푈���o������1910�N���܂�̎��̕��͏I��̎���34�ˁB
�푈�����͌}��(�F�{�s)���ӂɏZ��ł����悤�ł����A�����ŕČR�̋�P�ɂ����������ł��B
��c�`���̑��Ⓛ�A�Z�����ׂĔR���Ă��܂��������ł��B
�ČR�͍ڋ@�̋�P�����т��т������悤�ł��B
�@�e�|�˂̂��ƁA�j�����Ɣ������ׂȂ����ы���Ⴂ�ĕ��B
�����炭�q��@�̋@��̓O���}���e�U�e�Ǝv���܂����A�������Ă��܂�Ȃ�������
�����Ă��܂����B

�F�{�s �j��(40��)
�P�V�N�O�A�W�R�ŖS���Ȃ����c���̘b�ł��B
���̎��ɓˑR�c�����푈�̘b�������̂́A�c�����W�Q�̎��B�S���Ȃ�P�N�O�ł����B
��ԋL���Ɏc���Ă���b�́A�c�����{��ɏo�����A�{�艫�ɑ����̐��̃A�����J�R�̊͑���
�������A���̊͑��̐��Ƒ�C�̑��������āu���{�͕�����v�ƑO���ɂ������ԓ��Řb���Ă���
�ƌ���Ă��ꂽ���Ƃł��B
�����A���̂悤�Șb���㊯�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ƌ����Ă��܂����B
�c���͖{���͐푈�̘b���������Ȃ������Ǝv���܂��B
�푈�̘b������c���́A��������z���Ă���悤�ł����B
�푈�̌o����N���ɓ`����K�v������Ɗ����Ă����悤�Ɍ����܂����B

�F�{�s ���{����(80��)
�P�X�S�T�N�V���P���̌F�{���P�B
�F�{�s�̖{�����w�Z�̋߂��ɏZ��ł������́A�R�l���傤�����̒��j�ŏ��w�R�N���������B
�钆�A��P�x�钆�A�ڂ��s���R�ȑc���ƁA�S�̖������Ԃɏ悹�A
�����ĂV�̒�������A�ꓦ���܂ǂ����B
�ĈΒe�����������Ƃ���A�����������x�ƂȂ��苿���Ă����B
��P���Q���ԂقǑ������A�R���Ă��Ȃ����A�R���Ă��Ȃ����ւƓ��������ʁA
�Ȃ�Ƃ�������藯�߂����A���̎��̂��Ƃ́A���ł��L���ɑN���Ɏc���Ă���B
��P�̌�A�邪������ƊX�̎p�͕ς���Ă����B
�����̉Ƃ��猩����͂��̂Ȃ����h�̎R�X��������悤�ɂȂ��Ă����B
�������R���ĂȂ��Ȃ��Ă������炾�B
���̓��̊X�ɕY���u����Ȃɂ����v�͍��ł��o���Ă���B
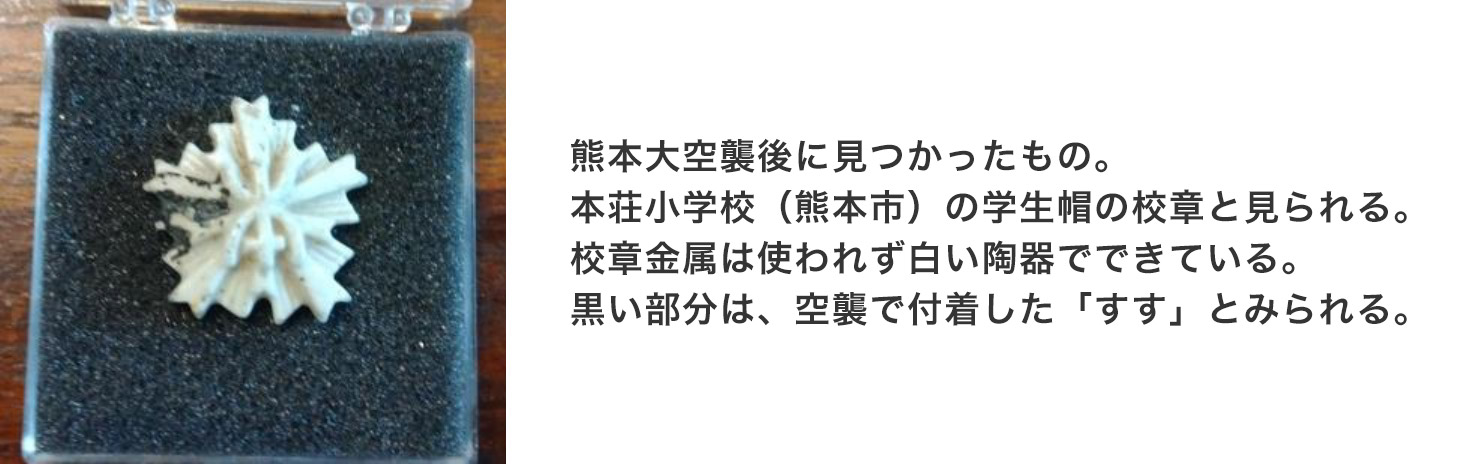

�F�{�s ���{����(80��)
�����o������O�ɁA�{��(�F�{�s)�̎���ŎB�e�����ʐ^�ł��B
��n�t�B���s�����畃�́A�S�N�Ԃɂ킽���Ď������q�ǂ���
��Ɏ莆�𑗂葱���Ă���܂����B
�y�ȉ��A�n�K�L�L�ڂ̓��e�z���قڌ����̂܂�
���V�^�J�́A���w�Q�N���ɂȂ�܂������B
�����āA�����w�Z�ɍs���Ă��܂����B
�悭�搶�̋���������āA�ǂ����{�l�ɂȂ��Ă��������B
�����l���R�͂̊G�������܂����B
�����������B
�̂��ɗ��݂܂��B
�T���i���B
1944�N4��18��

�ʖ��s ���c����(40��)
1923�N���܂�̑c�ꂩ�畷�����b���ł��B
���̑c��͑����m�푈���ɖ��F�̖k�A���\�A�Ƃ̍����t�߂̍����]�ȂŁu�i�R�H���v
�Ƃ������̌R�w��̐H�����A�����l�̌Z�ƒ��3�l�Ōo�c���Ă��������ł��B
�틵���������Ă���1945�N��5����6������ɁA�̋��̋ʖ��s�������̑�������A
���Ƃ̕�e�̑̒����ǂ��Ȃ��̂Ŗ߂����ق��������A�ƘA���������炵���A
���̃^�C�~���O�ŐH�������ŋA�����邱�ƂɂȂ��������ł��B
�����āA���B�S���ŋA�����Ă������Ƀn���s���w������ł��Z�����
�u�Y�ꕨ������������ɋA��B��ɍs���Ă����Ă���v�ƌ����A��U�ʂ�A
���ǂ��̌�Z�Ƃ͉���A�c�ꂾ�����A�����������ł��B
���ꂩ�琔�������8���ɋ��\�A�R�����F�ɐN�U�B
���Z����͂���Ɋ������܂ꂽ�̂��A���NjA�����邱�Ƃ͂Ȃ��A
�c��͓�x�Ƃ��Z����ƍĉ�邱�Ƃ͂Ȃ����������ł��B
���̎��Y�ꕨ�����Ȃ�������Z�������ɋA���ł����̂ɁA�Ƒc��͌����Ă��܂����B

�c��ɂƂ��Đt������߂��������F�ł̐H���̎v���o�͖Y����Ȃ��炵���A
���ʂ܂łɂ�����x���F�֍s�������ƌ����Ă��܂������A���N�O��99�ŖS���Ȃ�܂����B
���͗��j���D���ł����̂ŁA�c����c�ꂩ��푈����̍��̘b�������������܂����B
���̎�������l�B�������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ɂȂ��Ă��܂����B
��ɖY��Ă͂����܂���B
���͂ł������`���Ă��������Ǝv���܂��B

�F�{�s ����(80��)
�P�X�S�S�`�P�X�S�T�N�ɂ����ē������w�����������͋ʖ��s�ɏZ��ł��܂����B
�����@�����P���鋰�ꂪ����ۂɖ�u�x���x��v�̉����ƁA
���ɕ������Ŗh�ɓ������݂܂����B
��́A�X�����Ȃ��^���Âȓ��𑖂��ē������L��������܂��B
�܂��AB29���ґ���g��ŗ��P����ƃK���X�̌˂��K�^�K�^�Ɨh��A
���|�������Ă��܂����B
1945�N�̌F�{���P�̍ۂ́A�ʖ��s����F�{�s�̕���������ƁA�^���ԂɂȂ��Ă��āA
��P�̔�Q�ɂ����Ă���Ǝv���܂����B
�I�풼�O��1945�N�W���X���ߑO�A�_��Ȃ����V�ł����B
�e�r��̒�h�ɂ�����u�h���h���h���[�v�Ƃ������������A
����̕����ɃL�m�R�_���݂������Ƃ��o���Ă��܂��B

�����s�E���� �쒆����i70��j
���͐��̐��܂�ŁA�푈�ڑ̌������킯�ł͂���܂��A
���Z���̍��A�����⑰�ł��镃���畷�����b���F�l�ɂ��`���������Ǝv���܂��B
1945�N�̏I��ԍہA����ɏZ��ł������́A
�Z�p�n�ł��������ߏI��̖�3�����O�ɕ����ɏ��W����܂����B
�����o�����m���悹����Ԃɏ��ہA�w�ɂ͑����̌�����̐l�X���삯���Ă��������ł��B
���̒��ɂ͕��̕�e�̎p������܂������A���ڐ��������邱�Ƃ͊����܂���ł����B
�����Č}�����I��B
�̋��ł��钷��͌����ɂ���ĐՌ`���Ȃ��Ȃ�A�S�Ă̖����D���܂����B
��ȕ�e���A�o���A�����Ŗ��𗎂Ƃ��܂����B
�o���̍ہA�w�Ŗڂɂ�����̎p���A���ɂƂ��čŊ��ƂȂ��Ă��܂����̂ł��B
���͐푈�̌��ɂ��āA����ȏ㑽������낤�Ƃ͂��܂���ł����B
�������A���̂悤�ȕ������ɖ₢���������t�ŁA�����Y����Ȃ����̂�����܂��B
�u�A�����J���A�ǂ̍�������ł͂����Ȃ��B
���ꂩ��̐l�X����x�Ƃ���ȋ����Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ�����������B
��l�ЂƂ�͔�͂�������Ȃ����A�����Ė��͂ł͂Ȃ��B
�q�⑷�����ɁA����Ȏv���������邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁB�v
���̕��̌��t���A�F�l�ƕ��������������Ƌ�������Ă��܂��B
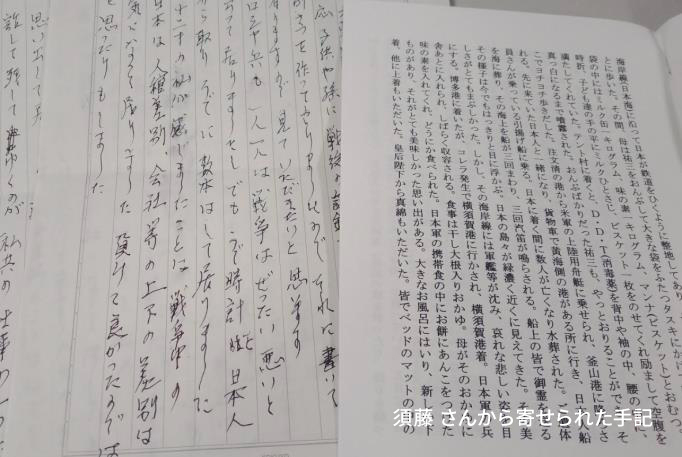
�F�{�s�E������ �{������i�X�O��j
�X�O��̎��́A�I����Ƒ��ƂƂ��Ɍ��݂̖k���N�A���R(�E�H���T��)�Ō}���܂����B
�I�킩��3����A���\�A�R�̕��m���㗤���A
���{�l����D�����r���v�𗼘r��4�`5�{�͂߁A�e�����ɂ����A
5�l�قǂ��Ƃ̒������������Ă��܂����B
�����A�ˑR�A���N�l�̈ē���5�`6�l�̋��\�A�����䂪�Ƃɉ��������Ă��܂����B
�ނ�͕��Ɍ������āu�������o���I�v�Ɠ{����܂����B
���͉Ƒ�����ׁA�u���ɂ͂��Ȃ��v�ƒf��܂������A
���m�Ɉ��������A�����A�w�̒܂��h�����Ȃǂ̖\�s���܂����B
���͒ɂ݂ɂ��߂��Ȃ���u������I������I�v�Ƌ��сA
���͕�▅�����ƂƂ��ɑ������э~��A�ǂ��ɂ�����邱�Ƃ��ł��܂����B
���m�����͎�������ǂ������ė��܂���ł������A
��ʼnƂɋA��ƁA�ѕz�Ȃǂ����������Ă��܂����B
����ŁA�P�O�ゾ���������������펞���̓��{�́A
�l�퍷�ʂ��Ђł̏㉺�W�̍��ʂ������������ƋL�����Ă��܂��B
�����l����ƁA���{�͐푈�ɕ����ėǂ������̂ł͂Ȃ����Ɗ����邱�Ƃ�����܂����B
���80�N���o���܂������A�푈�����̏o���������p���A�c���Ă������Ƃ��A
�������푈�o���҂̈�̎d�����ƍl���Ă��܂��B

�F�{�s�E������ ��������i40��j
�P�X�P�U�N���܂�̑c���̎�L�ł��B
�y�ȉ��A�c���̎�L����z
�P�X�R�V�N�A�����푈���n�܂����N�A���͂Q�P�ł����B
�P�O���ɂ͓Ɨ���s��P�T�����̈���Ƃ��ď�C����s��ɒ������܂����B
�����̏�C�s�X�n�͐�ɔR���A��s��t�߂ɂ͓G���̈�̂��U�����Ă��܂����B
�e���͒�����킸�苿���A�O�i���镺�m�͓D�ɉ���A
�Ă����������Ƃɂ͐l�̎p�͂Ȃ��A�c���͌R�n�ɓ��ݍr�炳��Ă��܂����B
���̂悤�ȏ̒��A����2�����ԁA�G�̗v�_�ɔ��e���^�ђ��Ԃ̑O�i���x�����A
���ɂ͓G�̔�s����U��������X�𑗂�܂����B
���N����͒����̖k���A�����A�암���щ��A�n��틦�͂Ȃǂɏ]�����܂����B
�������A���̌�Q�x�قǃ}�����A�Ɋ������A���𗣂�邱�ƂɂȂ�܂����B
�����āA�����m�푈���n�܂����P�X�S�P�N�ɂ́A�����s����ӂ̊C���
�����͂�{���E�T�m����ΐ��������s���܂����B
���̌�͔�s���̊w�����k�̎w���ɏ]�����A�I����}���܂����B
�I��ْ̏��������́A�R��h�Ɖ����h�̊Ԃł����������N����A
�M��������������Ƃ��o���Ă��܂��B
���̌�A���͋��E��ԂɊׂ����Ǝv���܂��B
���O�A�c������푈�̘b�ڕ��������Ƃ͂���܂���B
�����Ƃ��낢��Șb���Ă����悩�����ƁA���X�Ȃ���Ɏv���܂��B

���h�s ���V���� (70��j
�F�{�s�E�k��@�������(70��)
���Ƃ��ł��鎄�����́A���80�N�Ƃ����ߖڂ̔N�ɁA
���O����Ƃ̂Ȃ������f�����푈�Ŏ������������K��܂����B
�f���́u�����攪�\��A���v�ɏ������Ă��āA�����̑O�͖��B�ɒ��Ԃ��Ă����悤�ł��B
�����̎ʐ^�ɂ́A���B�̊�����邩�̂悤�ɖh���d�l�̌R���𒅂��f�����ʂ��Ă��܂����B
���B���牫��������f�����ǂ̂悤�ȋC�����������̂��A�������@�������ł��B
1940�N4���ɖ��B�E�����Ȃ�����Ƃ̒�ɑ���ꂽ�f���̎莆���c����Ă��āA
�����ɂ͏f���̐푈�ɑ���l�����Ԃ��Ă��܂����i�ꕔ�����j�B
�u�푈�͂܂�1�������Ă��Ȃ��B����Ă��Ȃ�����܂������Ă���̂�������Ȃ��B
�푈�̎蕿�b���莆�ɏ�����悤��������A��قlj^���ǂ��̂�������Ȃ��B
�푈�Ƃ����A�����ɂ��m���n���퓬�i�����j�ɎQ�������l���啪����B
���̐l�����̘b�ɂ́w�����ꂵ�������x�Ƃ��蓪�Ɏc���Ă���悤���B
�����Ƃ��ꂵ���Ȃ��푈�͐̂���Ȃ��B�ꂵ���ڂɂ����ď��߂Đ푈�͏��̂�����B�v
���̎莆��ǂނƁA����Ƃ͂���������������ɂȂ�܂��B
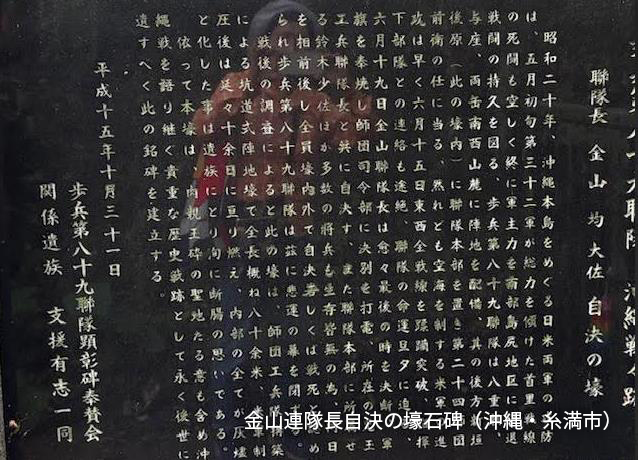
�������͏f���������̋��R�A�����ƂƂ��Ɏ��������ꏊ�����ꌧ�����s�V�_�ɂ���ƒm��A
���N9�����̒n��K��܂����B
���̏ꏊ�͏����ȍ��ŁA�����d���𗊂�ɓ����Ă����܂����B
���ۂɑ��ݓ���Ă݂�ƁA�f�����Ŋ��𐋂����ꏊ�ł���ɂ�������炸�A
�s�v�c�Ƌ��낵����߂����������邱�Ƃ͂���܂���ł����B
��������A�����̋Ɍ��ɉʊ��ɗ������������f���̋C�T��S�g�Ŋ����邱�Ƃ��ł��A
���ɕs�v�c�Ȋ��o�ł����B
�X��łł������͎��C���Ȃ��A�ӊO�ɂ��u�₩�ȋ�Ԃł��������Ƃ���ۓI�ł��B
���̂悤�ȏ����ȍ��̒��ŁA�f���������v���A�ǂ̂悤�ɉ���̒n�ł��̐��U���I�����̂��B
���80�N�B���̎������A�c���Ă��������Ǝv���܂��B
©RKK2025