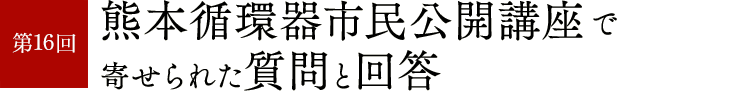
�y�ҁz
�F�{��w�a�@�z����� �����@�ғc ����搶�ق�
�o�d�����搶���ɂ��������������܂����B
��������̂���������������܂������A�z�[���y�[�W�̃X�y�[�X�̓s����A
����������������̒�����I���Ă��������A���������Ă���܂��B
�ǂ����������������B
������ꗗ
- �i����1�j
�s���苷�S�ǂǂ��A�E�������J�e�[�e���}���A���e�܌������������ʁA2�ӏ����������F�߂��܂����B
1�ӏ��̓X�e���g�}���ݒu�A����1�ӏ��͊������ׂ��׃o���[���Ŗc��܂�����ӏ��ɖ�ܓh�z���A����ȏ㋷�Ȃ��悤�ɂ��܂����B
�������A�p�㖢���ɋ��ɁA�������A���ꂵ���Ȃǂ̈�a���������܂��B�Č���������S������������܂���ł����B
�S����t����́A�s���苷�S�ǍĔ��ƐV���ȋ���ӏ��͔F�߂�ꂸ�S���_�o�ǂƐf�f����܂����B���̐S���_�o�ǂ����P������@���܂ȂǂȂ��ł��傤���H - �S���̕\�ʂ̑傫�Ȋ������̋�����g�������ɂ��ւ�炸�A���邢�͋��Ȃ��ɂ��ւ�炸���S�ǂ�L����ǗႪ�������݂��鎖�����ڂ���Ă��܂��B�����Ƃ��āA����������ߐ��Ɏ��k����h�����k�h��J�e�[�e�������Ō����Ȃ��قǂ̊��������ǂɌ�����Q�̂���h�������Nj��S�ǁh���l�����A����2�̌��������������@���J������Ă��܂��̂ŁA���̂��{�݂ő��k����邱�Ƃ������߂��܂��B
-
�i����2�j
�����̎�p��ɕ��ː����Ê�����A�A�Q�O�ɋ��̒��ߕt���������ꂵ���Ȃ�܂��B
�S���̌����ł͖��Ȃ��B�������킩��܂���B -
��ʓI�ɁA���Î����S�ǂ͏A�Q���E��Ԃ⑁���̋��̒��ߕt���Ǐ����Ƃ���܂��B�������������͒ʏ펞�i�쎞�j�Ɍ��������Ă���肪�S���Ȃ����Ƃ������ł��B����āA�Ǐ�̓T�^����j�g���y���̌��ʂȂǂ̏�������ł́A�������f�����ق����悢��������܂���B
�����A�����̎�p�ƕ��ː����Ê����ォ��o�������̂ł���A�S�����ł͂Ȃ������邢�͓����Â��e�����Ă���\�������肦�܂��̂ŁA��������̐搶�ɂ����k����Ă݂Ă͂������ł��傤���B -
�i����3�j
���̒ɂ݂�����������킯�łȂ��A���鎞�}�ɒɂ����b�u�A�b�ɂ��ȁv�Ɗ��������ɂ݂��Ȃ��Ȃ鎞�́A�a�@�ɍs�������������̂ł��傤���H - ���b�̒ɂ݂̏ꍇ�A�S���������Ƃ͍l���ɂ����Ƃ���Ă��܂����A����ȊO�̕a�C�𐳂����f�f���邽�߂ɂ͐f�@�⌟�����K�v�ɂȂ�܂��B
-
�i����4�j
���ӂ��ׂ��A���̒ɂ݂́H �S�؍[�NJ��҂̒��ӂ��ׂ��������́H - �������̒��ߕt�����̏ꍇ��A��⌨�A����{�ɒɂ݂��g����i���U�Ɂj�̏ꍇ�͗v���ӂł��B�܂��A�S�؍[�ǂ̌o����������͍Ĕ����X�N�������̂ŁA�u���ł����������^���Ö@�A�H���Ö@����{�ɖ��Â��p�����������Ǝv���܂��B
-
�i����5�j
�����Ȃ�Ƌ����ꂵ���Ȃ邱�Ƃ������Ă��܂��B���퐶���ŋC��t���Ă����������ǂ����Ƃ������Ă��������B - �����ꂵ���Ȃ邱�Ƃ̌�����������ł����A���������S�ǔ���Ȃǂ̌��ǎ����ł���A����h���͌��ǂ̎��k��U�������܂��̂ŁA�}���Ȋ��g���̎��o�͔�����K�v������܂��B���̂悤�Ȋ��җl�̏ꍇ�͊��������͏\���ȕۉ��̂��ƊO�o���������B�B
-
�i����6�j
10��̍�����X�|�[�c�����Ă����������̂��珙���ň��Î���40��ł��B
���͑��v���Ǝv���܂����A����ɂȂ��Ă���������̂܂܂��ƐS�@�\�I�ɐS�z�ł��B����S�����͑����Ȃ��̂ł��傤���H - �X�|�[�c���������ŁA���Î��ɕ������_�o�ْ̋������܂菙���ƂȂ邱�Ƃ͂����݂��A�a�I�ł͂���܂���B�X�|�[�c����߂Ă��璷�����Ԃ��o�߂��A�N����d�˂Ă����ƁA�X�|�[�c�̉e�����������Ȃ蓯�N��̕��Ɠ������x�̐S�����ɂȂ��Ă������Ƃ������ł��B����ɂȂ��ď������������A�S�s�S��߂܂��A���_�Ȃǂ̏Ǐ���ꍇ�͎��Â��K�v�ɂȂ�܂��B
-
�i����7�j
���ɂ��o��������܂����A�w���ɂ������悤�Ȓɂ݂��N���������Ƃ�����܂��B���������ꂵ�������ł��B
������A�z��n�ł��傤���B - �w���ɂ��g���鋹�ɂ̌����Ƃ��ẮA�S���̑��A�哮���A�x�A�H���E�݂Ȃǂ̏�����ȂǑ����̑��킪�l�����܂��B�����Ǐ����悤�ł��̂ŁA��������̐搶�ɂ����k�Ȃ���A����������邱�Ƃ������߂��܂��B
-
�i����8�j
�S���̎���i���e�A�E�������Ȃǁj�`�N�`�N����Ƃ�������܂��B
�ɂ��قǂł͂Ȃ��A���Ԃ����ĂΎ��邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B��́A�ǂ�Ȃ��Ƃ��l������̂ł��傤���H - �`�N�`�N����ɂ݂͐_�o�ɂ̉\���������ł��B
-
�i����9�j
�S���ɓ���ᎂ�����܂��B�����ƕs�����̖�p�ŁA3�����Ɉ�x��f�B
�ߋ��ɐS�[�ד��ŁA�J�e�[�e���A�u���[�V������3�Ă��܂��B�ŋ�7�N�Ԃ�ɔ���ǂ��܂����B
�d���V���b�N�Ŏ��܂�܂������A�������������Ǝv���Ă����̂ł��Ȃ�V���b�N�ł����B
�ꂪ�Γ���ᎂ̉𗣂����A���̐��N�㓮��ᎂ̔j��ŖS���Ȃ�܂����B���������悤�ɂȂ�̂ł͂ƕs���ł��B
�\�h�Ƃ܂��O���Ƃ��āA�ǂ�Ȓɂ݂�����̂������Ă��������B - �哮��ᎂ͊�{�I�ɏǏ���܂���B���X�ɐi�s����5-6cm�ȏ�ɂȂ�Ɣj��a�C�ł��B����I�Ȍ����ŃT�C�Y�𑪒肵�A�댯��������Ύ�p���s���܂��B��U����ᎂ��o����Ə������Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���ɑ傫���Ȃ�Ȃ��悤�Ɍ����̊Ǘ��Ƌ։�����ł��B�����s���ł���Α�w�a�@�Ɏ�f���Ă��������B
-
�i����10�j
���S�ǂƃX�g���X�̊W�������Ă��������B - �g�̓I�E���_�I�X�g���X��������Ƌ��S�ǂ�}���S�؍[�ǂ������邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B�܂��A���ǂ��z���ɂ���ċN���銥���k�����S�ǂ̔���ɂ��X�g���X�͋����W���܂��B�Ȃ��֘A����̂��͏\���𖾂���Ă��Ȃ��_������܂����A������ɂ��Ă��X�g���X������邱�Ƃ͋��S�ǂ̗\�h�ɏd�v�ł��B
-
�i����11�j
�x���p��7�N�ɂȂ�܂����A���܂��ɒɂ݂�����A�S���������ړ����Ă������������܂� - ��ʓI�ɁA���S�ǂ͂��ߐS���������̋��ɂ̕��ʂ͈ړ����Ă������Ƃ͏��Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B�x���p�ォ��̒ɂ݂̂悤�ł��̂ŁA��������̐搶�ɒɂ݂̐����Ȃǂ𑊒k����āA���ꂪ�{���ɐS���������Ȃ̂��������Ă��炤�̂͂������ł��傤���B
-
�i����12�j
�R�N�O�ɖS���Ȃ��������V�O�̎��ɐS�[�ד��ŐS��~���܂����B
�]�ቷ�Ö@�łU����^�ǂ����҂��AICD�ߍ��݂W�N�قǃS���t���y���݂Ȃ��猳�C�ɉ߂����܂����B
�������N�A���i52�ˁj�����J���Ɉ�x���炢�ł����A���������鎞������܂��B
�����̒�����15�����炢����A�P���Ԕ����炢�̂��Ƃ�����܂��B��`���邱�Ƃ�����̂ł��傤���H
�܂��A�z��ɂ͎�f���Ă���܂���B
�ǂ̂悤�Ȍ�����������ǂ��̂��m�肽���ł��B�i�l�ԃh�b�N������f�ł��j �X�������肢���܂��B - ���炭�����l�ɋN�������s�����͐S���ד��Ƃ����댯�ȕs�����ł������Ǝv���܂��B�S���ד��͂͂����肵���������������ɋN���邱�Ƃ�����܂����A�S�؍[�ǂ�S�؏ǂȂǐF�X�ȐS�����������ŋN���邱�Ƃ������ł��B�����l�̐S���ד����ǂ̂悤�Ȍ����ŋN�������ɂ��܂����A����̐S�؏ǂȂǂł���Έ�`����\��������܂��B������ɂ��Ă��A�����Ƃ����Ǐ�͂���Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA��x��Ë@�ւ���f���ĐS�d�}�����Ȃǂ��邱�Ƃ������߂��܂��B
-
�i����13�j
�ǂ̃^�C�~���O�ŗ��@���ׂ��ł����H - ���җl���ꂼ��ŏ������قȂ邩�Ƃ��l���܂����A�S�������^�������Ǐǂ����������̂��Ɋւ��ẮA�����{�����搶�̂��u�����e���Q�l�ɂ���Ă��������B
�܂��A�w����ȂƂ��͖��킸119�ԂցI�x�Ƃ��������e�ŁA�����J���Ȃ��z�[���y�[�W���ɏ����s���Ă��܂��B��̓I�ɂ͈ȉ��̂悤�ȓ��e�ł��B
�E�ˑR�̌���
�E�}�ȑ���A�ċz����
�E���̒��������ߕt������悤�ȁA�܂��͈��������悤�Ȓɂ݂�2�`3������
�E�ɂޏꏊ���ړ����� -
�i����14�j
�S�[�ד��́A�����ł��Ȃ��̂ł��傤���H - �S�[�ד��̎��Âɂ́A�Ö@��J�e�[�e���A�u���[�V�����Ƃ�����p�Ȃǂ�����܂��B�Ö@�ɂ��Ă��J�e�[�e����p�ɂ��Ă��A���������邱�Ƃ͏o���܂���B�����A�J�e�[�e����p�ŕs�������삪�N���邱�Ƃ�������x�\�h���邱�Ƃ͉\�ł����A����̒��x�ɂ���Ă͂����Ŕ���Ȃ��߂������Ƃ��o���������������Ⴂ�܂��̂ŁA�厡��̐搶�ɂ��Ђ����k���������B
-
�i����15�j
30�N���炢�O�i20���炢�̎��j����s����Ɂi��1�`2��j���炢�������ߕt������悤�Ȓɂ݂�����܂��B
�����Ɏ��̉��i�����ӂ�j���d���ɂ݂��������܂��B
20���`30�����炢�Ŏ���܂��B������ۂ��5�`10�b���炢�ɂ݂�����܂��B
�z��Ȃ�l�ԃh�b�N�ł��`���܂������A�w�Ǐ�͋��S�ǂ̏Ǐ��ǂ��̌X�����Ȃ��x��w�Ǐo�Ă鎞����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ�����24���ԏǏo��܂Ō������邵���Ȃ��x�ƌ����Ă܂����A�Ȃ��Ȃ������������Ԃ����Ȃ��ł��B
���̒ɂ݂͋C�ɂȂ�܂����A�g�̂���Ȃ͕̂������Ă��܂����c
���܂łɂ��̂悤�ȏǏ�̊��҂���͂�������Ⴂ�܂����ł��傤���H
�܂��A���炵���炱�̋��̒ɂ݂͉��Ȃ̂ł��傤���H
�����ƒ��N�C�ɂȂ��Ă��܂��B
�����悤�Ȏ��Ⴊ�ߋ��ɂ���܂����琥���Ă������������ł��B - ���̂悤�ȏǏ�̊��҂���͂悭��������Ⴂ�܂��B�m���ɏǏ�̂��鎞�̐S�d�}���݂�̂���ԏd�v�ł�����A�^�����Ȃ���̐S�d�}������A24���ԐS�d�}�ł̌���(����łł��܂�)���s�����ƂŁA�S�����������ǂ����f����K�v������܂��B
-
�i����16�j
�S�������d��������A���e���S�؍[�ǂŖS���Ȃ����̂ōu���������Ǝv���Ă��܂��B - �Ƒ����͏d�v�Ȋ댯���q�ł��B��������̐搶�Ƒ��k�̏�A�����A�����A���������i�ɊǗ����A�܂�����I�Ȍ������s�����ŁA�����d���̐i�s���ǐՂ���邱�Ƃ������߂��܂��B
-
�i����17�j
�ߓ����߂ĐS��CT�������܂����B
�摜�f�f�̌��ʁA�������̈ꕔ�ɂ��̑��̐���Ȍ��Ǖ���50%���炢�����Ȃ������������܂����B
�v���[�N�����܂��Ă�Ƃ̂��Ƃł����B
���̃��x���ł̐S�؍[�ǂ̃��X�N�ƃv���[�N�����炷���Ƃ��ł���p������̂ł�����A���̕��@�������Ă��������܂�����A���肪�����ł��B - �v���[�N�����������ꍇ�A���������ʂ�v���[�N�����炷���Ƃ�S�؍[�ǂȂǂ̔����\�h���邱�Ƃ��d�v�ł��B�����Ă����ƃv���[�N�͒ʏ푝�����Ă����܂����A�X�^�`���Ƃ������ʃR���X�e���[�����������p���A���ʃR���X�e���[�������͂ɉ����邱�ƂŁA�v���[�N�͌��邱�Ƃ����҂���܂��B�܂��A�X�^�`���Ƃ�������̓v���[�N���j�郊�X�N�������Ă���A���̂��Ƃ��S�؍[�ǔ���̃��X�N�ቺ�Ɍq����܂��B
-
�i����18�j
����2.3�N���A�ڂ��o�߂�Ƌ����ɂ��a�@�ɂ������Ă��܂����������͂����肵�܂���A�N��̂������Ǝv���Ē��߂�ׂ����B - �����ɂ����̐S�d�}���m�F���邽�߂ɁA24���ԐS�d�}�����������߂��܂��B�ڂ��o�߂���Ɍ��肵�Ă���̂ł���A�Q�p���Ȃǂ̉e�����l�����܂��B
-
�i����19�j
����搶�Ƀp�C�o�X��p�Ŗ����~���Ē�����������Ă��܂��B����A���������邽�߂ɁA�ǂ�Ȃ��ƂɋC�����Đ���������悢�ł����H
�܂��A�i���҂ł����̂ŁA�ߋ��̃^�o�R�������̈�ƌ����A�^�o�R���Q������Ɖ��߂ĔF�����܂����B
�^�o�R�̉e���̌[�����y������A�����ł��a�C�͌�������̂ł́A�Ǝv���܂��B - ���肪�Ƃ��������܂��B�����⌌���A�����Ȃǂ̊Ǘ����d�v�ł��B����ȊO�ɋ։��A�X�g���X�����A�ǎ��Ȑ����A�K�x�ȉ^���Ȃǂ��d�v�ł��B���������w���ʂ��ċ։��̕��y�Ɏ��g��ł��܂��B
-
�i����20�j
�����̐e�A�Z�킪�S���̕a�ŖS���Ȃ��Ă܂��B��`����̂ł��傤���B
�ǂ̂悤�Ȓɂ݂�����A�܂��Ǐ���Ύ�f����ׂ��ł��傤���B -
���ɂ��Ƒ������Ⴂ���ɐS�����ǂ���Ă���ꍇ�́A�����g�̐S�������ǃ��X�N���㏸����Ƃ����Ă��܂��B
�܂��A�����K���������Ƒ��Ŏ��Ă��邱�Ƃ�����܂��̂ŁA������ɂ��܂��Ă����ӂ��K�v�ł��B
�ǂ��������ɂ݂����ӂ��ׂ����Ƃ��������e�Ɋւ��܂��ẮA20�Ԃ̉����Q�Ƃ��������B -
�i����21�j
����ҁi�U�O�Έȏ�j�́A�u�哮���ً���ǁv�����Q�N�O�̎�p��A�Q�T�Ԗ��ɓ��ȏz���@�Ń��[�t�@�������j���̂W���Ŏ��Â��Ă��܂��A���ݖ�̉e�����ŗ���b�����t�F�ɕϐF���Ă��܂����A����̌��N�Ǘ���̗��ӓ_�́A�ǂ�Ȃ��Ƃ�����܂����H - �哮���ً���ǂɑ��ċ@�B�ق�p�����ْu���p����ꂽ���̓��[�t�@�����̓������K�v�ƂȂ�܂��B���[�t�@�����͌��t���T���T���ɂ����܂ŁA��̍�p�Ƃ��ďo�����₷���Ȃ�܂��B�悭���鍇���ǂ͔牺�o���ł��B�牺�o���̍����ǂł���Βʏ�̓��[�t�@�������Â̌p���̕��j�ƂȂ�܂��B�o�����d�Ăȏꍇ�̓��[�t�@�����𒆎~���邱�Ƃ�����܂����A�K����t�̔��f�Œ��~���Ă��������B��̍b�����t�F�ɂȂ��Ă���̂��牺�o�����ǂ����s���̂��߁A����������畆�Ȃł̑��k�������߂��܂��B
-
�i����22�j
�s�����ŏz��ɂ������Ă����86��BNP��300�ʂ���A���t�T���T���̖������ł܂��B
BNP���ǂꂭ�炢�ɂȂ�Γ��@�Ƃ������������̂ł��傤��? -
BNP�͐S�s�S�̐f�f�⎡�Â̖ڈ��Ƃ��đ�ϗD�ꂽ�}�[�J�[�ŁA��ʓI��BNP��gt;100�ȏ�͐S�s�S�̑��݂���������Ƃ���Ă��܂����A�S�s�S�����ł͂Ȃ��l�X�ȕ��������������ő������܂��B�Ƃ���86�Ƃ�������̕��ł���ƈ�ʓI�ɕ��������������ł��̂ŁABNP�̖ڈ��͌X�l�ɂ���đ傫���قȂ�܂��B
�܂�ABNP�̒l����T�ɂǂ̂��炢�Ȃ���@�Ƃ����̂͌X�l�ɂ���ĈقȂ�A�Ǐ��X�l��BNP�l�̕ϓ��Ȃǂ��܂߂đ����I�ɓ��@�̓K�X�͔��f�����Ǝv���܂��B
��������̐搶�ɂ�������BNP���ǂ̂悤�Ȕ͈͂Ő��ڂ��Ă��邩���q�˂��āA�������Ō����c�����Ă����̂��悢�ł��傤�B -
�i����23�j
�ɂ݂����ɂȂ̂��ݒɂȂ̋t�����H�����Ȃ̂�������Ȃ��B - �ɂ݂��o�����̐S�d�}�������ł���ΐf�f�ɋ߂Â��܂��B��x�z����Ȃ���f���Ă݂Ă͂������ł��傤���B
-
�i����24�j
�E���i����C��t���邱��
�E����̐e�ɁA�ǂ̂悤�ȏǏł���A�a�@�֘A��Ă����悢�̂��H
�E�~�}�Ԃ��Ă�ŋ}���ꍇ�̏Ǐ�́H
�E�����̖��낢�날��̂ŁA���������Ăق���
�E�����͕K�v�ł����H -
���i����C�����邱�Ƃ́A��͂茒�N�I�ȐH���Ɖ^���K���A����Ɏ��a�̂�����͒���I�Ȓʉ@�Ƃ���̕��p�ł��B��������S���a�A�t���a�̂�����̏ꍇ�͓��Ɍ����͏d�v�ł��B
�a�@�֘A��čs���ׂ��Ǐ�͎����ɂ����܂����A���ɂ⑧�ꂪ����悤�Ȃ���Ȃ�z��Ȃ̎�f����x�͂��������ǂ��Ǝv���܂��B���ɁA�Ǐ�̕p�x����������ǏЂǂ��Ȃ�����A30���ȏ�Ȃǒ����������Ȃǂ́A�ً}���������Ǝv���܂��B�����A��T�ɂ͌����܂���̂ŋC�ɂȂ�Ǐ��鎞�͂���������ɂ����k���������B
�����̖�ł悭�g����̂�ARB�Ƃ��������J���V�E���h�R��A���A�܂Ƃ��������Ǝv���܂��B���ꂼ��̓����ɂ��ẮA�l�X�ȃz�[���y�[�W�ŏЉ��Ă��܂��̂ŁA�����̏�Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B -
�i����25�j
����̐������K������������̂���ԓ���Ƃ������܂��B�ꌾ�Ō����̂͊ȒP�ł����B
�ǂ������炢�����ȂƁA�l���܂��B - ���������ʂ肾�Ǝv���܂��B�S���a�̗\�h�ɂ͂����郁�^�{�̗\�h����P���d�v�ł��̂ŁA�̏d�⌌�������ł��A�����L�^����K�������Ă͂ǂ��ł��傤���H�ŋ߂͂��̂悤�ȃA�v����\�t�g�Ȃǂ��F�X�Əo�Ă��ĕ֗��ł��B�����A�������������A�܂���1���ɉ��x���L�^���悤�Ƃ���Ɣ��Ă��܂��̂ŁA���X�Y��Ă��ǂ��A�Ƃ����C�����Ŏn�߂�Ɨǂ����Ǝv���܂��B
-
�i����26�j
��N9���ɕꂪ�����ڌ^�S�؏ǂɂȂ�A4���قǓ��@���܂����B
�X�g���X�������ƌ����܂������A���܂�v�������邱�Ƃ��Ȃ����퐶���ł̒��ӓ_�Ȃǂ������Ă��炦�܂���ł����B
�Ĕ����Ȃ����߂̒��ӎ����ȂNj����Ă������������ł��B - �����ڌ^�S�؏ǂ͐g�̓I�A���_�I�X�g���X��U���Ƃ��Ĕ��ǂ��邱�Ƃ�����܂����A���݂̂Ƃ��댴���s���̎����ł��B�Ĕ����邱�Ƃ�����܂����A�Ĕ��\�h�ɗL���Ȏ�i�͖��炩�ł͂���܂���B��ʓI�Ȍ��N�ɂ悢���������Ă������Ƃ͏d�v�ɂȂ�܂��B�̒��Ɉٕς����������͑��߂ɕa�@��f�������߂��܂��B
-
�i����27�j
1�N�O�ɋ}���S�؍[�ǂ��o�����A����ȗ��։����ċC�����Đ������Ă܂����A�Ĕ��̉\���͂ǂꂭ�炢����܂����H - �S�؍[�ǂ̌o���̂Ȃ����Ɣ�ׂ�Ɩ��炩�ɍĔ��̃��X�N�����܂�܂��B���Ái�X�e���g�j���s���Ă��Ȃ������ɂǂ̒��x����i�v���[�N�j���c���Ă��邩���d�v�ł��B���Â��s������t�Ƃ悭���k����邱�Ƃ������߂��܂��B
-
�i����28�j
�������̋���ɂ��āA��p�ŃX�e���g�����̊�́H�����u���Ȃ���́H - �ɂ߂č��x�̋���̏ꍇ�i���̏ꍇ�A�X�e���g�K���Ƃ���ꍇ�������j�������āA�X�e���g�̊�́A���̋������i�������K�v�ʂɖ���������Ȃ����j��U�����鎖�ł��B���݂ł́A�����̏ؖ��Ȃ��X�e���g�𗯒u���邱�Ƃ͐�������܂���B�����̏ؖ��@�́A�S�،����V���`�A�����������̈��r���ȂǑ��ʂȕ��@�����݂��܂��B
-
�i����29�j
���X ���̐^�� ���̋� ���������悤�Ȓɂ݂��o��B �������� 20�b 30�b �䖝���Ă���Ǝ��܂�B
��T �钆�Ƃ� �������ɂȂ�B - ��������Ŏ���ꍇ�́A�H���̏Ǐ�̉\���������ł��B
-
�i����30�j
H�Q�T�N���ԕa�@�ŃX�e���g���u�p�܂����B�o�ߊώ@�͖��N�����ق����ǂ��ł��傤���B - �o�ߊώ@�̂��߂̌����͒���I�ɎĂ��������������S�ł��B����J�e�[�e�����K�v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA��������ł̌����Ŗ��Ȃ��Ǝv���܂��B�X�e���g���u�̍ۂɏǏ������̂ł���A���̏Ǐ�̍Ĕ����Ȃ����@�Ƃ����_����ԏd�v�ł��B
-
�i����31�j
�@�S�d�}�����ʼn����킩��܂����H
�A�����ɂ����ǂꂭ�炢�Őf�@���Ă���������������ł����H
�B�S��������������@�͂���܂����H -
�@�S�d�}�����ł͗l�X�Ȃ��Ƃ��킩��܂��B�s�����A�������S�����A�S�s�S�ȂǑS�Ă̐S�����ɂ����ďd�v�ł��B
�A��T�ɂ͌����܂���B�ˑR�̓����Ȃ��قǂ̌��ɁA�}�ȑ���A�ӎ�����т����Ȋ��o��߂܂��A��⊾���l�ȏꍇ�͖��Ɋւ��a�C�̏ꍇ�����邽�߂����ɋ~�}�O����f�����Ă��������B
�B���N�ȐS����ۂ̂��߂̊�{�́A�H���A�^���A�����A�։��ł��B���ʂȂ��Ƃ�����킯�ł͂Ȃ��A��{�I�Ȍ��N�ɂ悢�����𑗂邱�Ƃ��ł��d�v�ł��B -
�i����32�j
���ݒ��w3�N���A15�̖��ł��B
���X�A�ˑR�ɍ����̉������肪�ɂ��Ȃ�Ƃ̂��Ƃł����̂ŁACT��G�R�[�ȂǍl�����錟���͑S�Ă��܂����������͕�����܂���ł����B
�����z�����ɓ��ɃL���[���ƒɂ��Ƃ̂��Ƃł��B���w4�N�����납�玞�X�������悤�ł����A��N�������܂����B
�ēx�����������������̂ł��傤���B�������ɂ��邱�ƂȂ̂ł��傤���B - �]�Ԑ_�o�ɂ̉\���������悤�Ɏv���܂��B�������̂ݏǏo��ꍇ����������܂��B
-
�i����33�j
��N5���ɃA�u���[�V�����̎�p�����܂����B
�ŋߎ��X����������A�����������Ȃ����̂ŕa�@�i���ȁj�Œ��ׂĂ��炢�܂������ُ�Ȃ��ƌ����܂����B
���v�ł��傤���H - �A�u���[�V������p�̌o��������ŋߓ����̎��o������̂Ȃ�A�s�����Ĕ������O����Ă��邾�Ǝv���܂��B�u�ُ�Ȃ��v�̍����ƂȂ����������e�͂킩��܂��A�s��������͂P�x��24���ԃz���^�[�S�d�}�ł͌��o����Ȃ����Ƃ�����܂��B���܂�ɓ����̎��o�������̂ł���A�J��Ԃ��z���^�[�S�d�}���Ƃ�����A�P�T�ԘA���S�d�}���Ƃ��{�݂�����܂��̂ŁA�A�u���[�V�������{�s���ꂽ���a�@�ւ����k����Ă��悢��������܂���B